
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
法律事務所ZeLo・外国法共同事業
早乙女 明弘弁護士
さおとめ あきひろ
取材弁護士事務所
法律事務所ZeLo・外国法共同事業
早乙女 明弘(東京弁護士会)
2012年一橋大学法学部卒業、2014年一橋大学法科大学院修了。2015年弁護士登録(東京弁護士会所属)。2016年日本生命保険相互会社に入社し、契約書審査、法改正対応、知的財産管理、海外子会社管理など、幅広く企業法務に従事。 University of Michigan Law School(LL.M)への留学を経て、2022年法律事務所ZeLoに参画。主な取扱分野は、ジェネラル・コーポレート、ヘルスケア、広告・表示(景品表示法など)、金融規制、データ保護、知的財産、国際法務など。
 本文
本文No.1表記の関連法規と「広告表示」「(検証)調査」する際の注意点・リスク、過去の訴訟や裁判凡例 など
今回は、初めて第三者(調査機関)に「No.1」「国内No.1」などの「No.1調査」を依頼する企業にとって役立つ情報として、関連法規と「広告表示」「(検証)調査」する際の注意点・リスク、過去の行政処分などについて紹介する。尚今回の記事を作成するにあたり、法律事務所ZeLo・外国法共同事業の早乙女明弘弁護士へのインタビューを実施した。
No.1調査では、広告主が調査を依頼する「依頼者」となり、依頼を受けて調査をする側が「実施者」となる。景品表示法に準拠して広告を作成する場合、責任を問われるのは「依頼者」だ。早乙女弁護士によれば、「商品やサービスに「No.1」と表記して宣伝をしても、No.1の中身が実態と大きく差があれば、景品法表示違反に該当し行政処分の対象となる可能性が高い」と指摘する。広告主としても調査会社に調査を任せっぱなしにすることはリスクが伴うのだ。
誰の目から見ても「No.1」と示すためには以下の3つのポイントが重要だ。
- 適切な調査結果を導くための質問の設計
- 許容誤差を考慮したサンプル数の設定
- 対象者の選び方
この3つを調査時に意識をすることで、自社調べの調査結果であったとしても優位性を示すことができる可能性が高い。しかし、これだけでは調査結果に偏りが生まれてしまう可能性もあり、調査方法の中身(何が具体的に問題とされるのか)を詳しく知っておかなければならない。
実際に2023年6月13日ドッグフード会社への措置命令の対象となったものは、「食べやすさ」「愛犬におすすめ」など計7つの項目の「顧客満足度No.1」だ。客観的な評価ができないという理由で措置命令の対象となった。
この時に行われていた調査方法は、日頃から商品に接する機会の多い当該事業者の会員が回答者となっており、質問内容もウェブサイトの印象を問うものに過ぎず、客観的な調査方法とは認められないという指摘があったのだ。
※https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230614kyushu.html
外部の調査機関に依頼をしても調査自体に問題があるケースも存在する。第三者機関に調査を丸投げするのではなく、第三者機関の調査方法に対しても依頼者がチェックをしておくことも重要だ。
とはいえ素人ではどのような点をチェックすべきか判別が難しいだろう。次のポイントをチェックすることで、信頼できる第三者調査機関かどうかを判別できるだろう。
- 誘導質問になるような質問の仕方
- 対象者の住まいが東京都のみなどエリアが限定されているケース
- 回答者の属性に偏りがあるケース
- 調査団体・協会の自主規則に則って調査を行っているかどうか
上記のポイントをクリアしている団体であれば、信頼に値すると言える。上記以外に注意すべき点はないか、早乙女弁護士によると「例えばですが『貴社のためにNo.1を獲得します』と謳っている企業は注意が必要など、どういった広告宣伝をしているかという点は重要ですし、法令違反が生じないようどういった取り組みをしているのか、業界のガイドライン等を遵守しているのか、といった点も重要です。また、調査結果を踏まえて実際にどう表示するか、といった段階では弁護士に確認することが重要といえます」
調査結果は依頼主が責任を負うものであることと自覚し、依頼者が調査機関をコントロールすることも重要なのだ。
「No.1」表示のあり方(模範表示例・掲載基準)
今回は初めて第三者(調査機関)に「No.1」「国内No.1」などの「No.1調査」を依頼する企業にとって役立つ情報として、「No.1」表示のあり方について紹介する。尚、今回の記事は、法律事務所ZeLo・外国法共同事業の早乙女明弘弁護士のインタビューを元に作成した。
No.1表記の前提で最も重要なことは、「社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で調査を行っていたかどうか」という点だ。必ずしも専門家(第三者調査機関)に依頼をしていれば良いということではない。
例えば業界最大手のA社が販売しているαという商品の売上データおよびその主な競合となる企業の商品の売上データが公表されているとしよう。
これらの売上データを元にB社がβという商品とαや競合商品の売上を照らし合わせ、βが売上を上回っていることが判明した場合、「業界No.1」と表記しても問題ないと言えるだろう。
しかし、調査方法を客観的なデータを調査するのではなく、ネット検索のみに依存した場合はどうか。自社のホームページが上位表示され、良い口コミをいくつか確認できたとしても「検索結果No.1」と言い切ることはできない。SEO対策がなされた結果に過ぎないかもしれないからである。
では、具体的にどのような表示方法であれば問題ないのか。以下のポイントを押さえたものであれば、信頼できるデータと言えるだろう。
- 正確に評価できる調査方法
- 許容誤差を考慮したサンプル数の設定
- 対象者の選び方
ここで「許容誤差」とは一体何か?と疑問に思う方もいるかもしれない。許容誤差とは、アンケート結果をする際に生じる誤差のことだ。例えば400人にアンケートを採ったサンプルで、調査結果が、A社が90%、B社が80%、それ以下はC社、D社を支持していたとしよう。
一見このデータだけを見ればA社が支持されると評価できるが、許容誤差を仮に5%とした場合、母集団全体では、A社は85〜95%となり、85%まで下がる可能性があることを考慮しなければならない。
一方、B社の許容誤差は75~85%となり、B社が許容誤差により85%になる可能性も考慮もしなければならない。
その結果A社が許容誤差で85%、B社が85%となり、どちらも数値が同じになる可能性があり、アンケートの結果、「No.1」であるとは言い切れなくなってしまうのだ。A社がNo.1と表記するためには、許容誤差を考えてもA社の方が優れているというデータ結果を導く必要があり、400からさらにサンプル数を増やし、許容誤差を小さくする必要があるだろう。
客観的な調査結果を元に調査したことを示すために注意すべきことは何か、早乙女弁護士によると、アンケートの設計について、調査機関任せにするのではなく、調査対象や質問内容(質問の順番や構成を含む)、サンプル数の妥当性について批判的に検討し、バイアスが生じていないかという点を十分に検証する必要があるとのことである。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年03月18日
2024年03月18日


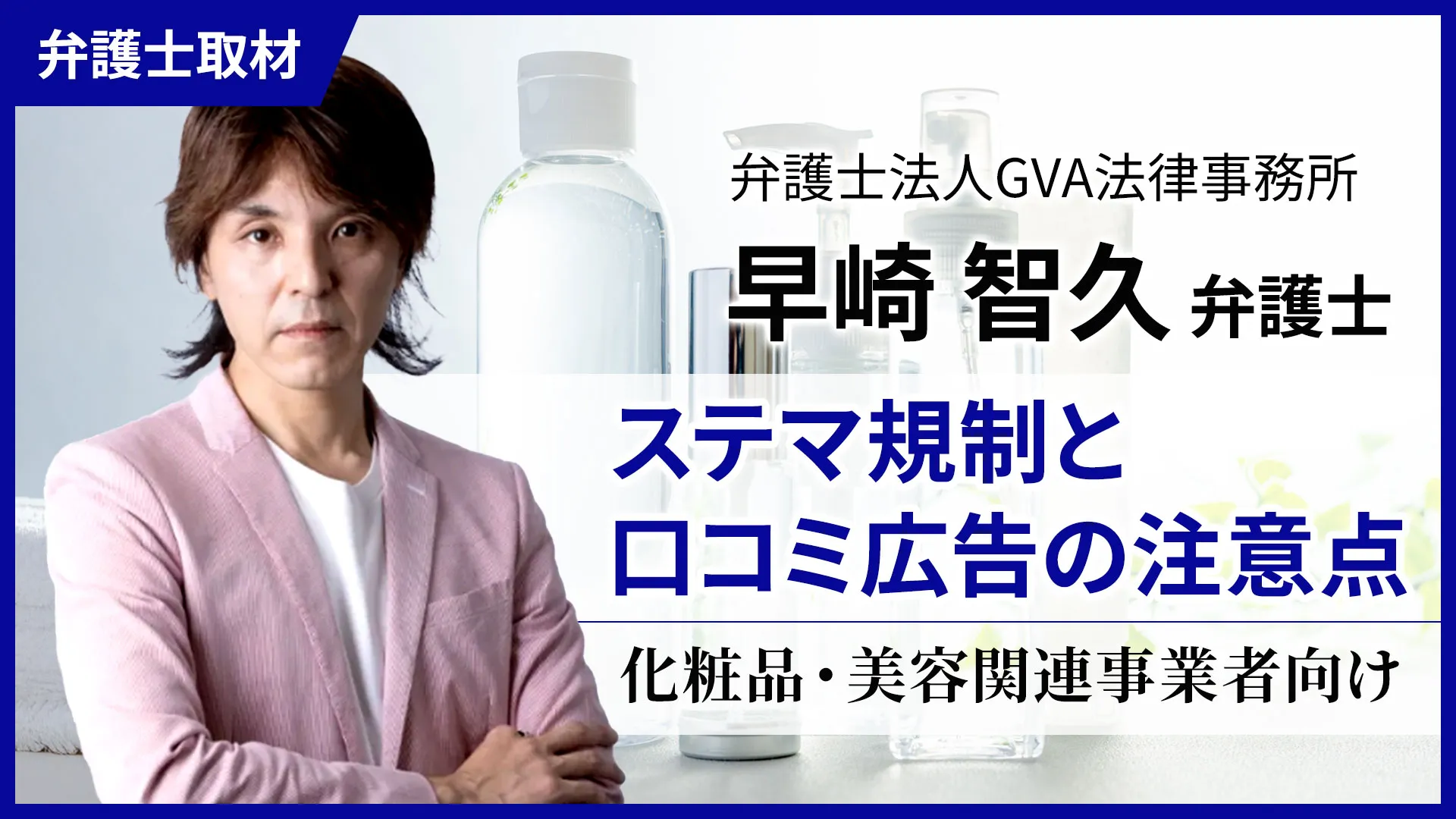
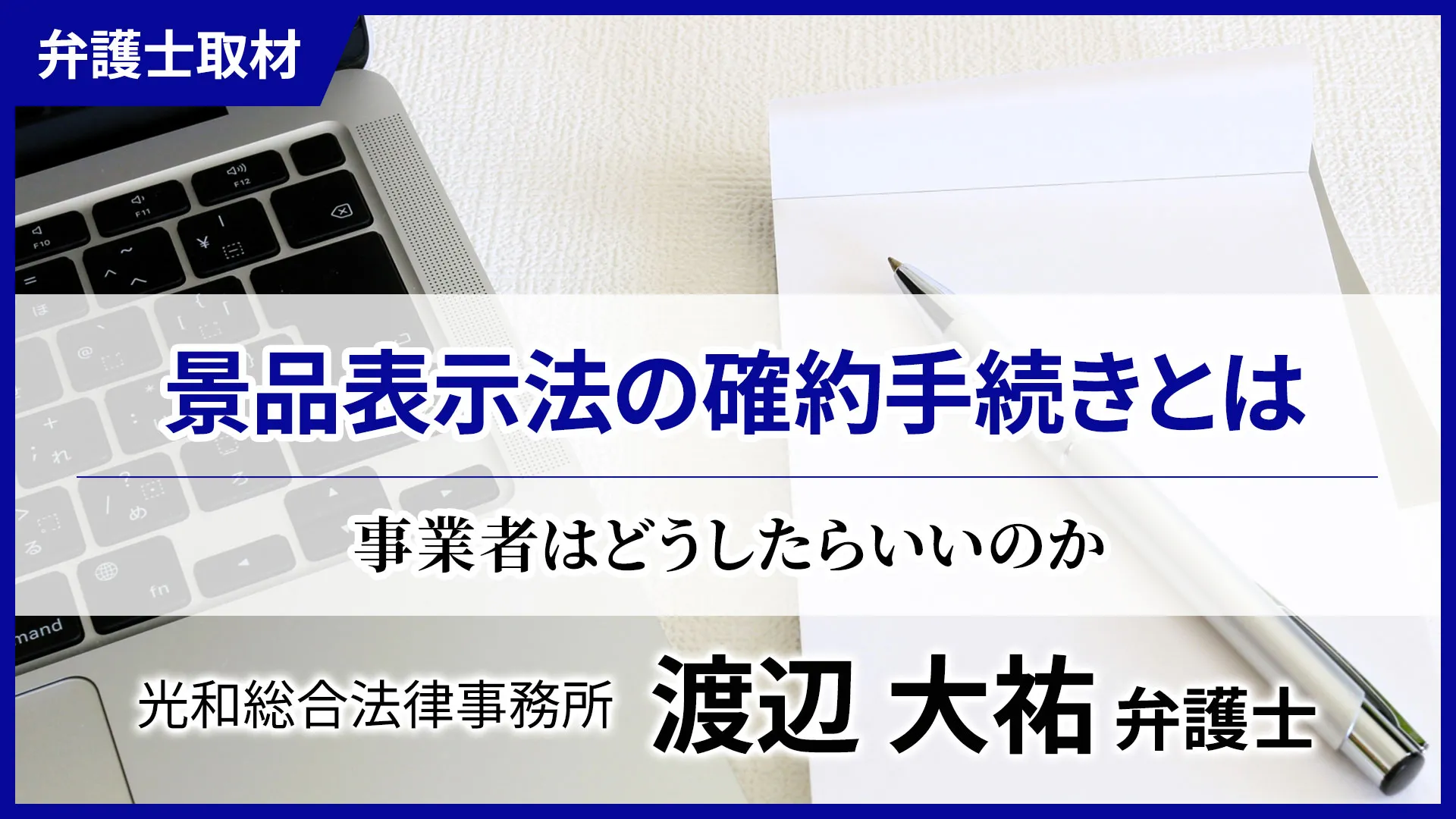




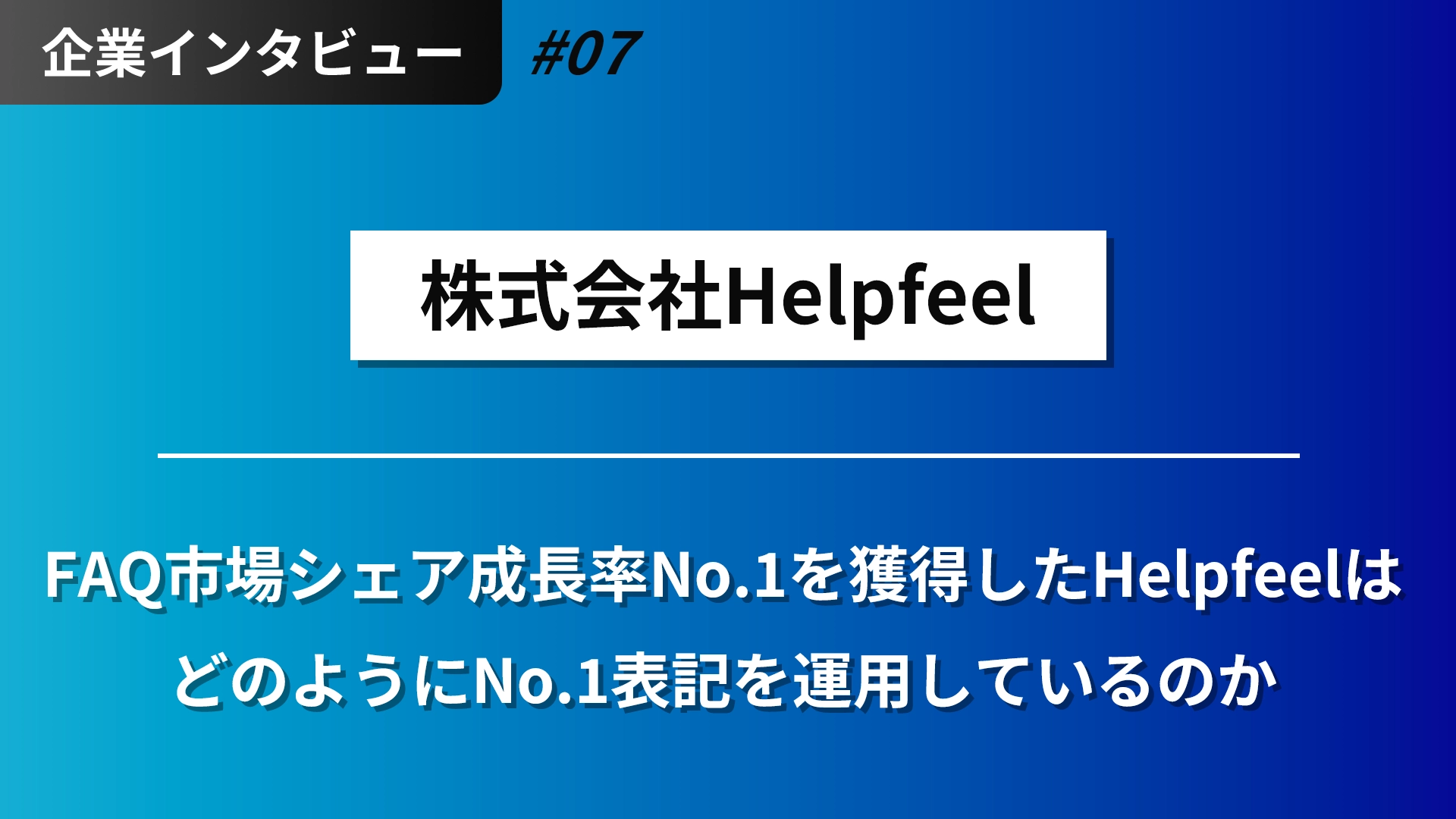

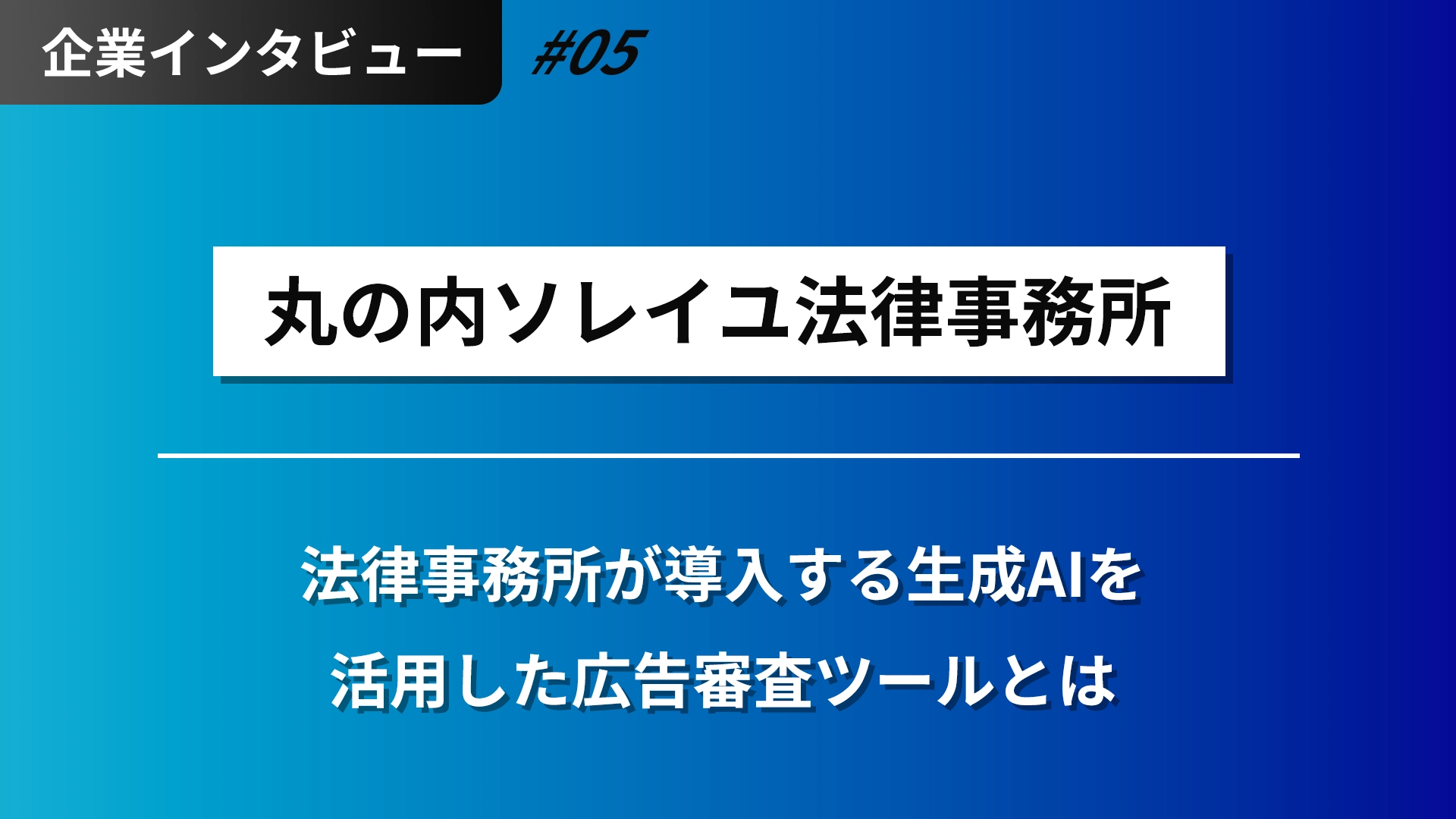
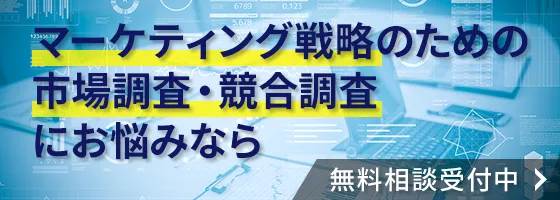
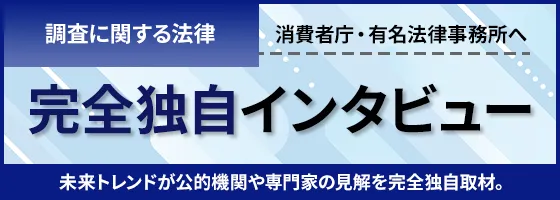
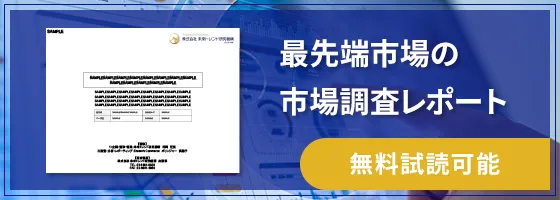


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com