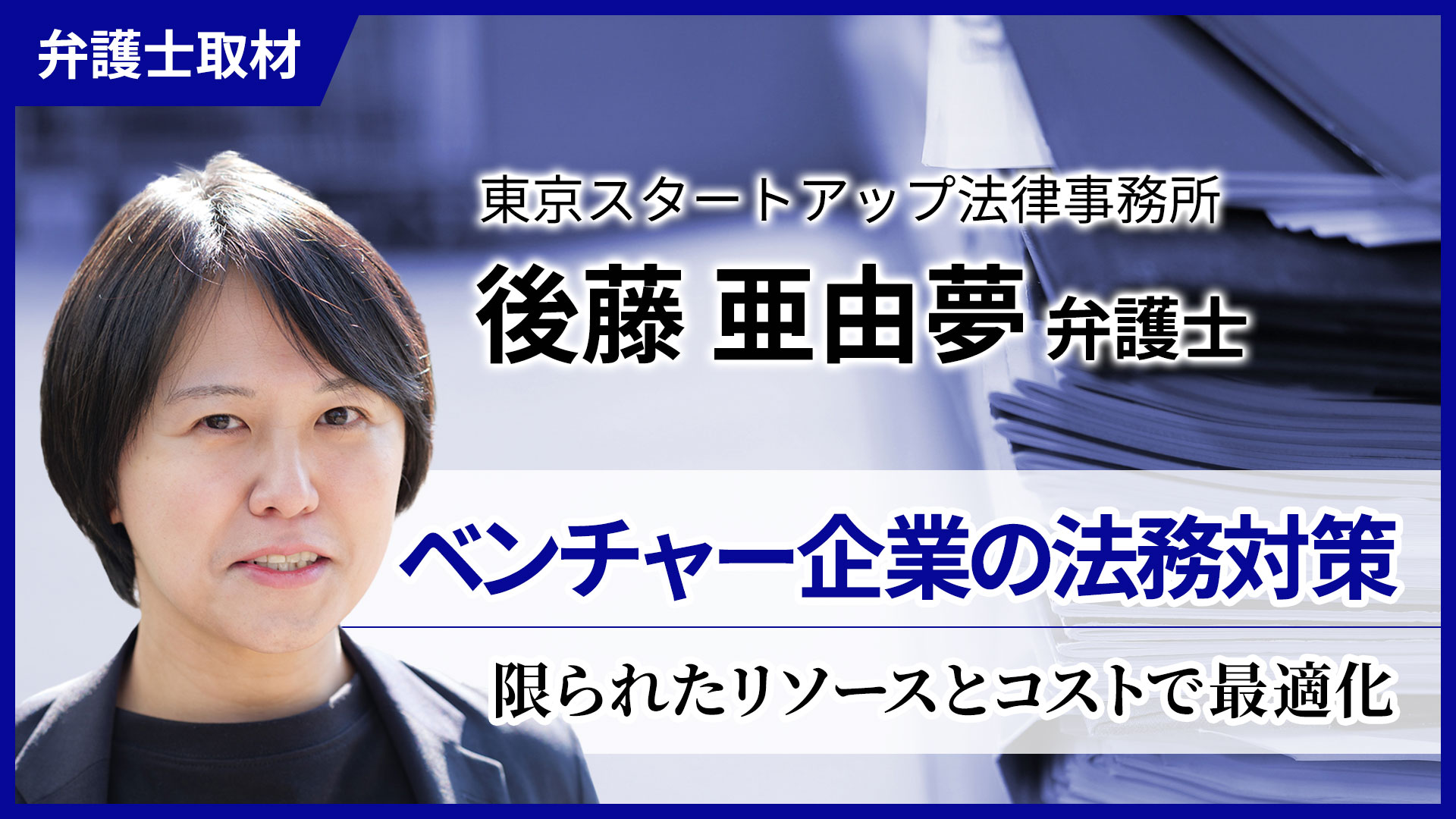
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
東京スタートアップ法律事務所
後藤亜由夢弁護士
ごとう あゆむ
東京スタートアップ法律事務所
https://tokyo-startup-law.or.jp/
在籍弁護士数30名以上、千件以上の実績を持ちお客様の依頼に合わせて、スキルがマッチする弁護士を配置しチームでサポートする。「UPDATE JAPAN」という企業理念を実現するため、各メンバーが「For Client」という価値観を持って対応する。相手を理解し、解決策を提示する「新しい時代の弁護士像」を目指す。
後藤亜由夢弁護士(東京弁護士会)
https://tokyo-startup-law.or.jp/member/goto/
公認会計士でもあり、監査法人勤務時代に培ったノウハウで、新たなサービスやプロダクトを生み出し、急速に成長していくスタートアップ・ベンチャー企業に寄り添う。
 本文
本文ベンチャー企業が考えるべき企業法務の段階
ベンチャー企業はリソースが限られている。事業規模が大きい事業者であれば、商品・サービスのNo.1や初の表記に対し客観的な視点でチェックを入れる事が出来るが、担当者が不在であるため、問題のある表記を見落としてしまうこともある。スタートアップ、ベンチャーの事業者は景品表示法(以下景表法)を正しく運用するために、どのようなことに注意すべきなのか。 全国規模でベンチャー企業・スタートアップ企業の支援を行う東京スタートアップ法律事務所の後藤亜由夢弁護士に話を伺った。
ベンチャー・スタートアップ企業が最低限行うべき対策
ベンチャー・スタートアップ企業の景表法に対する運用方針は事業者によって考え方が異なる。適切に景表法に則って表記の運用を心掛けている事業者もいれば、消費者庁の調査が入ってから対策を検討することを割り切って考える事業者も存在する。
景表法に則って運用を行うことが大前提であるが、スタートアップ企業・ベンチャー企業はどのように考えて企業法務を検討すべきだろうか。 「スタートアップ企業の場合、ほとんどの事業者は資金力等のリソースが限られています。この点、リソースをビジネスサイドと管理サイドどちらにコストを割くかと考えた時、まずはビジネスの収益化が優先されることから、ビジネスサイドに注力しようと考える経営者が多い傾向にあります。そうすると、経営者の考え方によって、強固な対策を行う事業者と、そうでない事業者で、管理サイドに割く資金力やリソースが異なります」(後藤弁護士)
管理サイドにコストをかけられるのであれば、フローチャートを用意してそれに沿って運用を実施したり、表記の最終チェックを行う担当者も配置できる。一方で事業規模が小さくリソースを割けられない場合は、そこまで手が回らない。景表法は、白黒はっきり表記を分けられることもあるが、グレーゾーンな表記も存在する。どこまで対策をしっかり実施すれば良いか、正解が存在せず判断が難しいものだ。 このような場合は「事業者の求めるレベルによって対策を変えるべきだ」と説明する。
「事業者自身が法務リスクをどのように受け止めているかによって対策が変わりますが、対策の判断基準の一つとしては、企業のビジョンによって運用方法を検討することが望ましいです。例えば上場準備企業や、M&Aを将来的に視野に入れている事業者であれば、1度でも措置命令の対象となれば、上場審査にひっかかることや、M&Aにおける自社の価値の低下、イメージダウン等のマイナスに繋がります。そのため、このような企業は、コンプライアンスをなるべく初期段階から意識して、景表法を遵守する必要が生じます。」(後藤弁護士) レベルに応じた対策が必要な景表法。比較的事業規模の小さい事業者は最低限どこまでの対策を実施すれば良いのだろうか。後藤弁護士によれば、「ランディングページのチェック」「チェックリストの作成」であれば、比較的簡単に対応できるとのことだ。
「例えば、自社の重要なサービスのランディングページのみをチェックするのであれば、そこまでコストがかからず低コストで対応出来ると思います。具体的には、掲載したいページの中身や、商品・サービス内容の実態と表示との対応等をレビューすることで、どこが問題のある表記かを、ある程度は指摘することが可能になります」(後藤弁護士)
No.1や初の表記を継続的に運用するのであれば、チェックリストを作成しておくことも良いアプローチだ。しかし、現場レベルで活用出来るものを作成するためには注意すべきポイントもある。チェックリストを作成する際は、消費者庁が発表しているガイドラインに沿って作成すると良いとのこと。
「No.1や初の表記を適切に行う際には、消費者庁の不実証広告規制に対する指針が、ガイドラインの中でも最も参考になります。これに沿ってチェックリストを作ることで、小規模の事業者でも管理しやすいのではないかと考えます。とはいえ、不実証広告の規制に記載されている内容は抽象的な表現があるため、例えば弁護士にチェックリストを評価してもらうと、なお良いかと思います」(後藤弁護士)
景表法にある程度詳しい有識者や担当者にチェックリストを作成しても良いが、誤ったチェックリストを作成すると、将来的に不利益を被るのは事業者だ。この点を考慮して作成するのであれば、ランディングページのチェックのように、ガイドラインをチェックしてもらうのも1つの手と言えるだろう。
後藤弁護士によれば、一定の業績を出し、事業規模が拡大したタイミングや、外部から資金調達を受けたタイミングで、顧問契約の打診を行うケースが多い。顧問契約をするタイミングが分からない時は、まずは弁護士に無料相談等で話を聞いてみるのも良い。あるいは、経営者において、ビジネスにおけるリターンと景表法違反の場合のリスクを加味し、その上でお金をかけてでもリスクを減らした方が良いという判断に至る場合は、顧問契約に踏み切るのも良いとのことだ。
今から出来る措置命令の確認方法
ベンチャー企業は企業法務を構築する際、景表法に関する知識を最低限学んでおくと、様々な面でリスクを回避できる。事業者がNo.1や初の表記に関する景表法の知識を身につけるためには、どのようなアプローチが適切なのか。後藤弁護士によれば、「措置命令をすべて分析するのではなく、まずは直感的に分かるものを確認しておくと良い」とのことだ。
「法的知識がない人が消費者庁の発表した資料をチェックしたとしても、何がどのように問題のある表記なのか、全てを理解出来ないと思います。この点、知見のない事業者の場合は、まずは消費者庁のHPの報道資料の中に添付されている「実際に問題があった広告」をチェックしておくことが重要です。処罰の対象になった表示がビジュアルで確認できるので、知識がない状態で確認しても、どのような表記が問題になったのかをある程度は知ることができます、従って、まずは消費者庁がどのような表記を措置命令・課徴金納付命令対象の事案として評価したのかについて、リサーチするのが良いと思います。」(後藤弁護士)
措置命令・課徴金納付命令を下しされた事業者は、消費者庁から報道発表資料として細かく発表される。その中で「別紙」と書かれているものを確認すれば、実際に問題となった広告を閲覧出来る。まだ一度も見たことがない担当者は一度読んでおくと良いだろう。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/036514/
景表法を学ぶ方法は措置命令を確認するだけでなく、セミナーを受講する、研修に参加すると様々なアクションがあるが、誤った広告を確認する作業は今すぐに出来るアクションだ。何から始めれば良いか分からない事業者は、まずはNo.1表記の失敗事例を確認しておくと良いだろう。
ベンチャー企業が最低限知っておくべきNo.1、初の評価基準
ベンチャー企業やスタートアップ企業の場合、「初」を謳うケースもあるが、後藤弁護士によっては失敗してしまうケースの方が多いとのこと。
「『初』はかなり難しい表記のため、対象をしっかり絞っても、既存の事例が見つかることもあります。事業者が自信満々に掲げたものが「初」ではないこともあるので、注意が必要です」(後藤弁護士)
「初」の表記は事業者の思い入れが強いこともある。しかし、初は表記の中でも調査がそれ相応のものが必要になるため、覚悟を持って調査をしなければならないと心得ておく必要がありそうだ。
事業者にとって魅力的なNo.1の表記はどうか。No.1の場合は「表記を見た一般消費者に誤解を与えないような表現を心掛ける」ことが最も重要とのこと。
「No.1の裏付けとなる客観的な資料を集めるために、専門家の学術文献や統計学に伴ったサンプル数をもとにアンケート調査を実施することもありますが、その結果の中身をしっかりチェックすることが重要です。また、知見のない事業者は調査会社の調査過程・結果をそのまま受け入れてしまう場合もありますが、措置命令・課徴金納付命令の対象となった事業者は、調査会社の調査結果をそのまま受け入れた結果、措置命令の対象になっている場合が多いです。従って、「この表記は一般消費者が見たらどんな風に受け止めるのか」という消費者の視点から表記をチェックして、事業者が見落としがちなミスを見つけましょう」(後藤弁護士)
いくらリソースが不足し、事業者内で客観的に評価できる仕組みがなくても、第三者の目線で最終的な広告をチェックすることはできる。事業者自身の偏りを防ぐのであれば、プロジェクトから一番遠い立場の人間に見てもらっても良いだろう。
ベンチャー企業やスタートアップ企業は大手企業に比べてリソースが限られている。
景表法対策に避けるリソースが限られているが、一般消費者から信頼関係が無くなればこれまで蓄積したビジネスも台無しとなってしまうかもしれない。だからこそ、売上重視とならないよう一般消費者の感覚に立って表記を冷静に評価できる姿勢を持つことが重要だ。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年07月04日
2024年07月04日


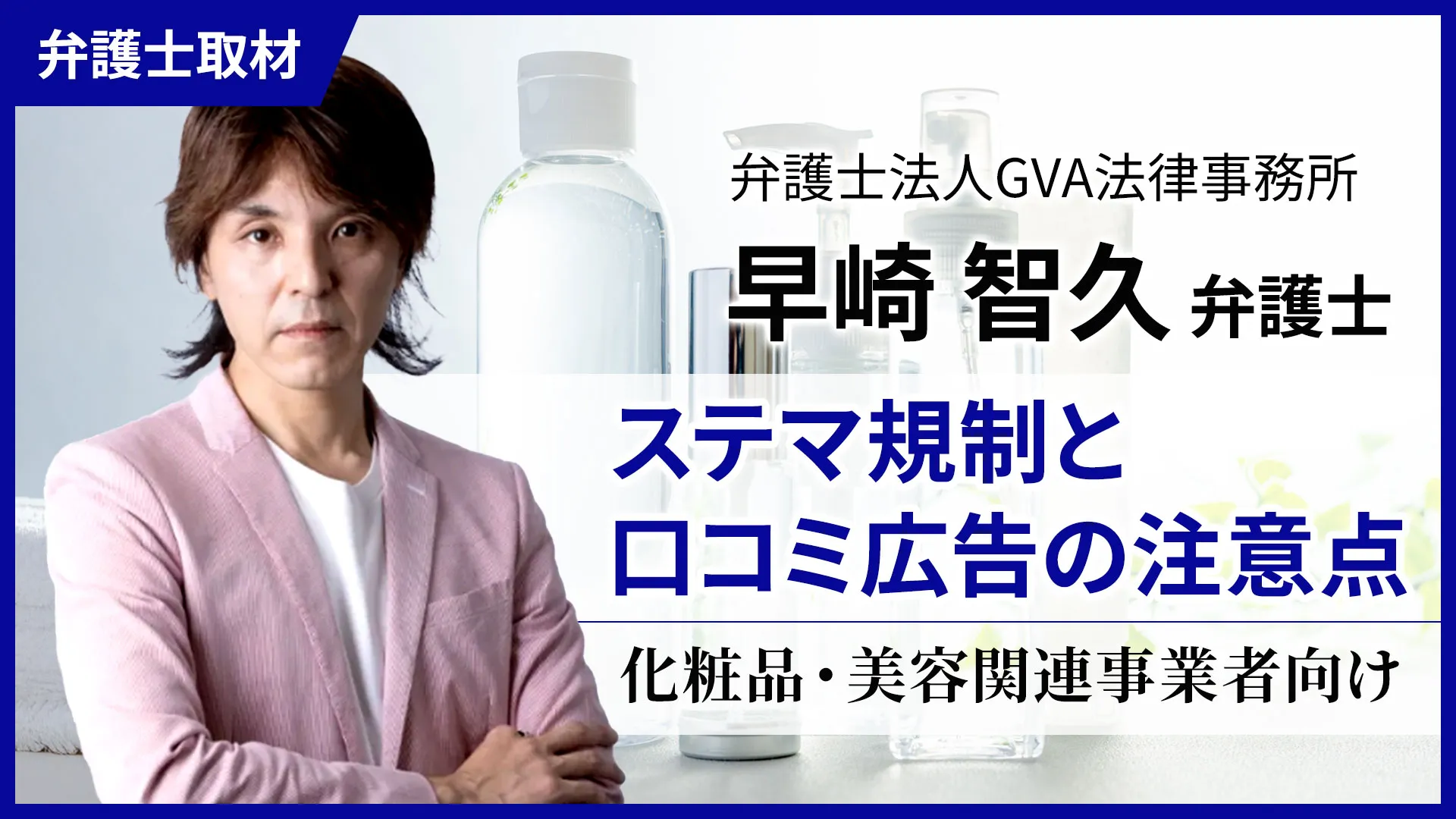
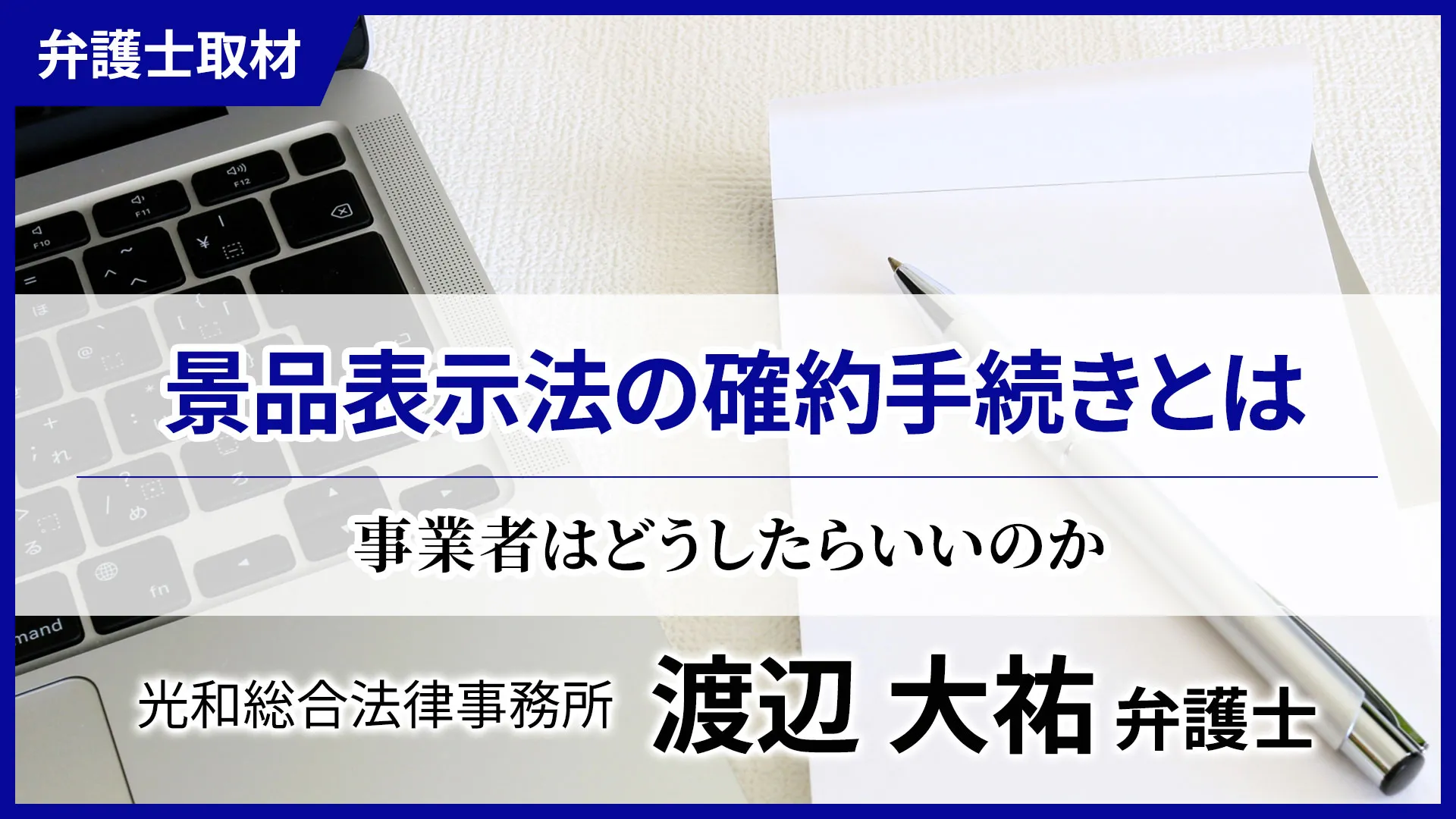




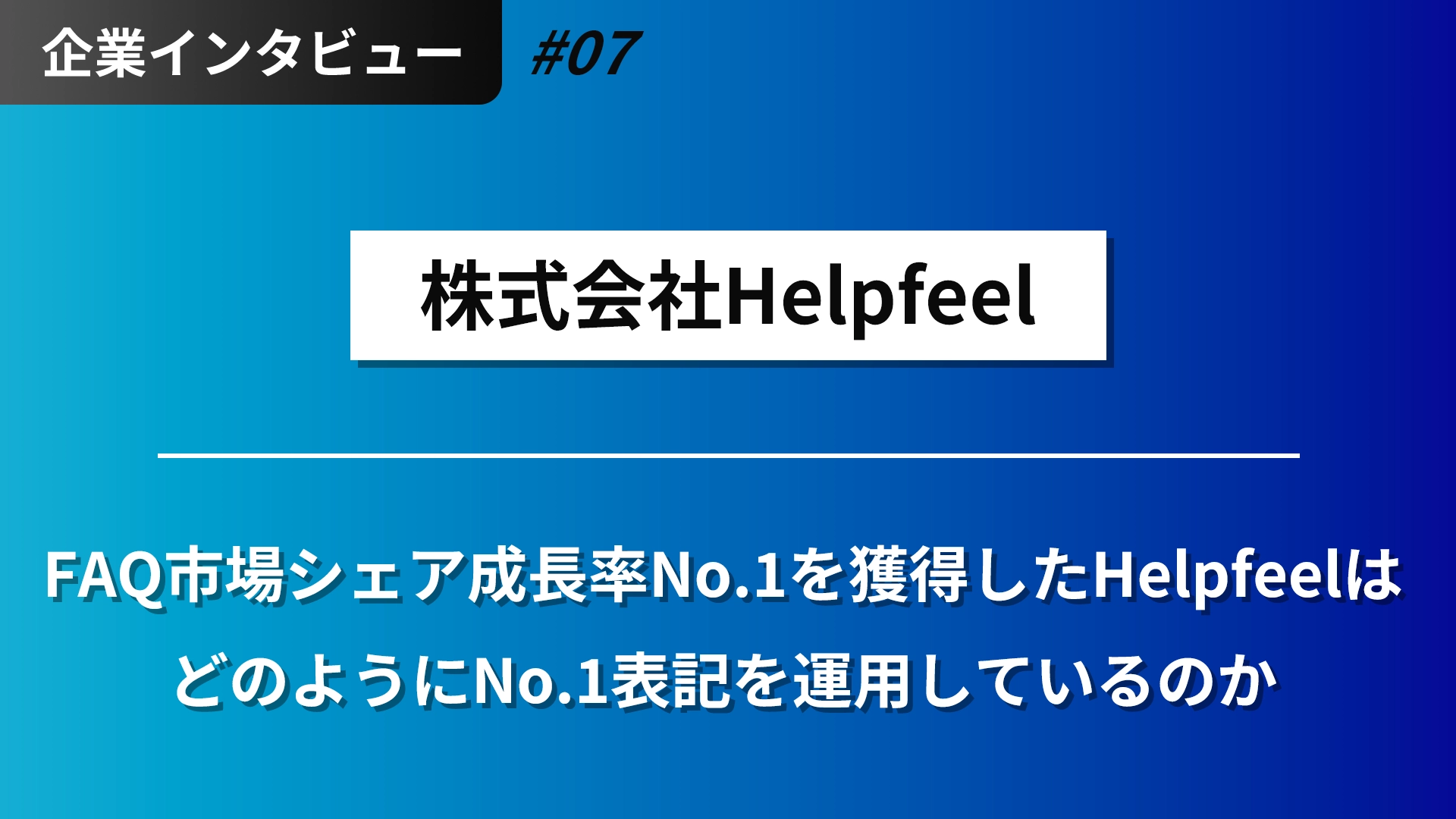

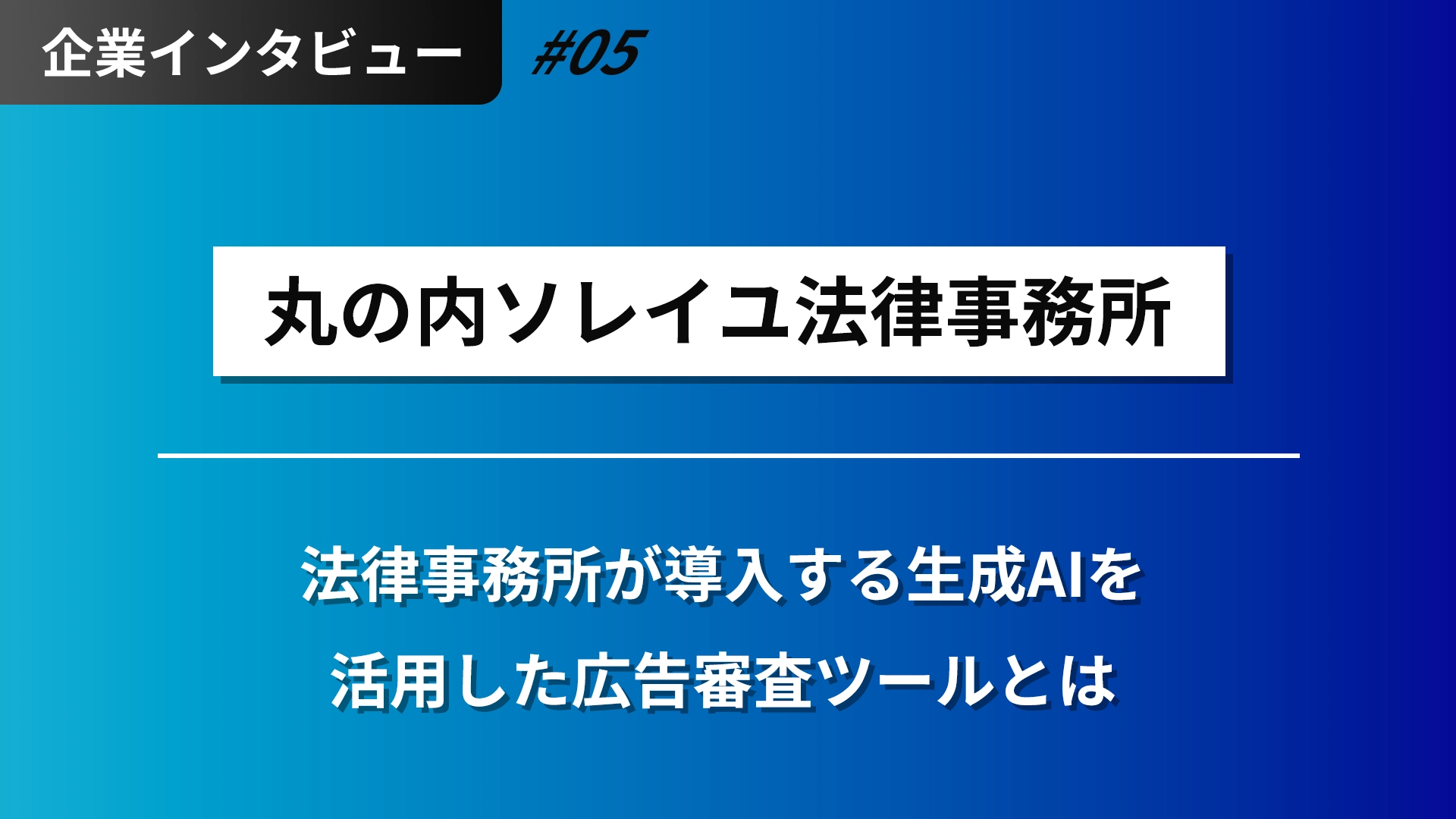
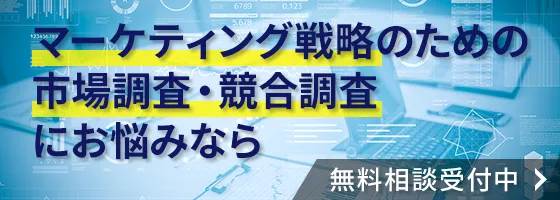
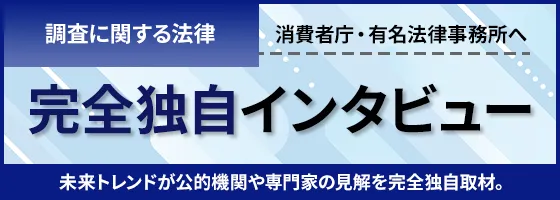
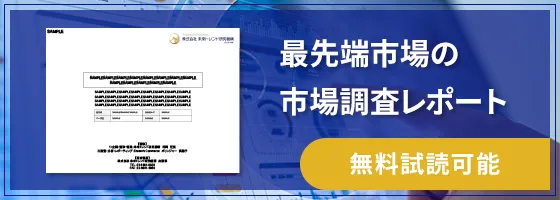


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com