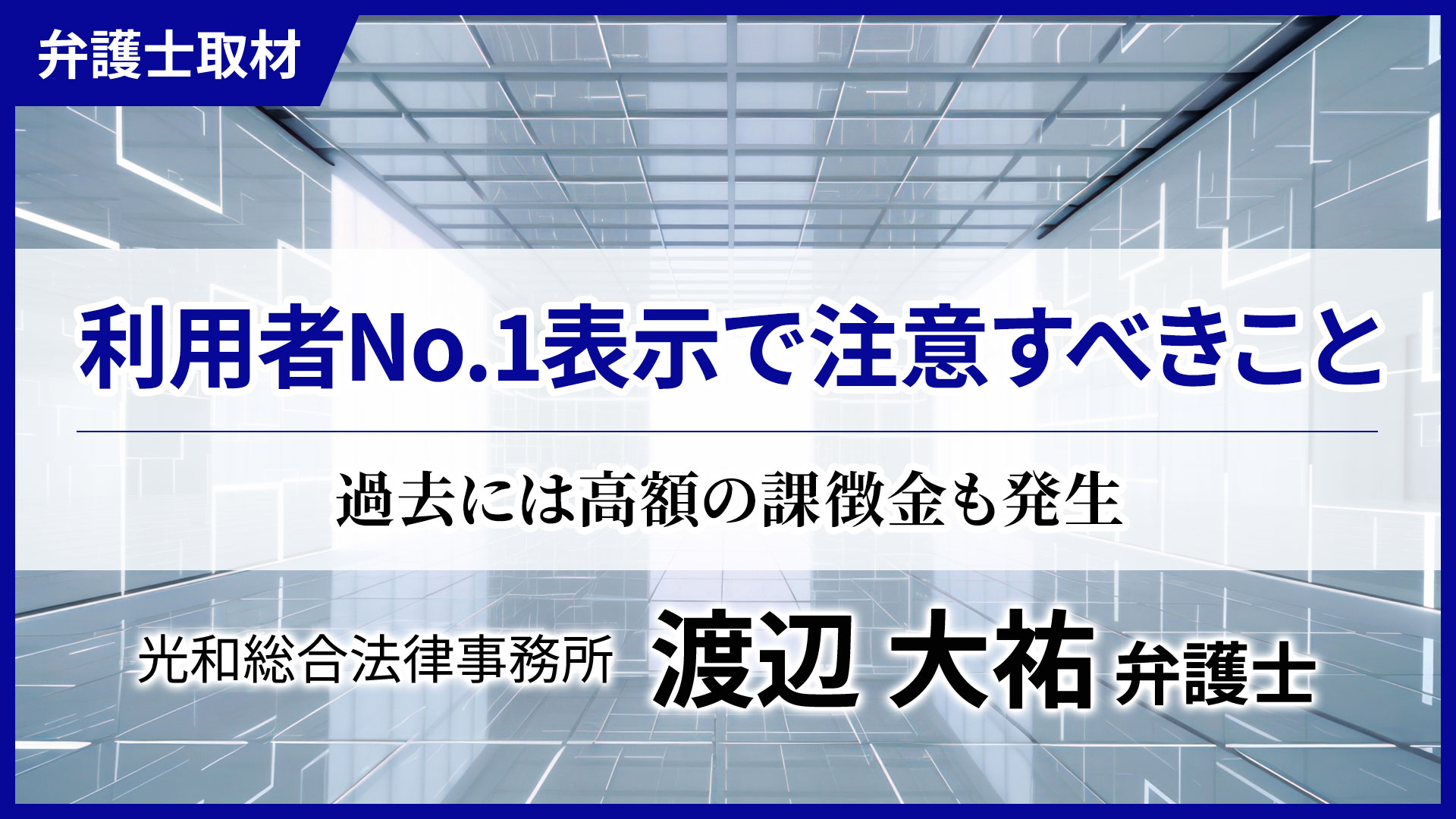
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール光和総合法律事務所
渡辺 大祐 弁護士
わたなべ だいすけ
渡辺大祐弁護士(第一東京弁護士会)
https://www.kohwa.or.jp/wp/members/2190/
景品表示法に関するセミナー・講演を精力的に行い、書籍を多数制作する景品表示法に精通している弁護士。公正取引委員会に審査専門官(主査)として出向後、消費者庁表示対策課において景品・表示調査官として実際の事件執行業務を行っただけでなく、令和5年改正景表法の立案業務を担当。これらの経験から、消費者庁の視点を踏まえて表示を評価し、クライアントにリーガルアドバイスを提供することも出来る。また上級食品表示診断士の資格もあり、食品業界の表示に対して特に精通している。
・「景品表示法における確約手続の実務的考察-第1号事案を踏まえて」『ジュリスト2025年5月号(No.1609)』
(有斐閣:2025年4月)
・『実務の勘所をおさえる 景品表示法重要判例・命令』(共著)
(中央経済社:2025年3月)
「時論 買取りサービスと景品表示法―運用基準改正を契機に」『ジュリスト2024年9月号(No.1601)』
(有斐閣:2024年8月)
「いま知りたい! 食品業界の法律 第1回 産地偽装問題と企業の対応」『ビジネス法務 2024年9月号』(共著)(連載)
(中央経済社:2024年7月~)
『法律要件から導く論点整理 景品表示法の実務』
(第一法規:2023年12月)
『逐条解説 令和5年改正景品表示法 確約手続の導入など』(共著)
(商事法務:2023年12月)
セミナー実績
・「広告法務基礎セミナーシリーズ1景品表示法 知っておきたい景品表示法の基礎知識-近時の実例も踏まえて-」
(公益社団法人日本広告審査機構(JARO):2025年4月)
・「事例で学ぶ『いまさら聞けない景品表示法の基礎と表示ルール』」
((一社)食品表示検定協会:2025年3月)
・「相次ぐステマ広告への行政処分と事業者がとるべき広告対策」
((株)ヘルスビジネスメディア:2025年1月)
・「不正調査の最新動向ー有事対応発生時における企業担当者の注意ポイントと平時の心構え」
(光和総合法律事務所/株式会社FRONTEO共催セミナー:2025年1月)
・「食品表示の法律実務とコンプライアンス解説講座」
((公財)公正取引協会:2024年11月)
等
メディア出演
「追跡“紅麹サプリ”〜健康ブームの死角に迫る〜」
(NHKスペシャル:2024年6月9日)
「その広告 本当?健康食品の表示 ここをチェック」
(NHKサタデーウォッチ9:2024年6月8日)
等
 本文
本文利用者No.1表示で注意すべきこと
2023年度以降、No.1表示は、消費者庁が特に注目している表示である。ここ数ヶ月間で新たな措置命令の対象となった事例は確認されていないが、事業者は引き続き注意しなくてはならない。今回は、事業者の参考になるよう「利用者No.1」の表示について、以前取材でお世話になった渡辺大祐弁護士の話を聞いて紹介する。
光和総合法律事務所
https://www.kohwa.or.jp/
事案の規模や複雑性に応じて、様々な法領域・業界に精通した弁護士の知識・ノウハウを結集してチームを編成し、専門的で複雑な案件にも対応。官公庁・民間企業での勤務経験者、留学経験者も多数所属し、弁護士がそれぞれの専門分野を有機的に結合して活動している。
No.1表示で最低限把握すべき事
No.1表示をこれから検討している事業者として、大前提として理解しておくことがある。それは、No.1表示は、それを行うことが直ちに違法となるような表示ではないということだ。
「No.1表示は、一般消費者が、同種の商品の内容や取引条件を比較するために有益な情報となり得るものです。No.1表示が合理的な根拠に基づくものであり、表示と実際が合致しているのであれば、問題となるものではありません」(渡辺弁護士)
では、表示と実際をどのように合わせるのか。消費者庁は、「事業者が講ずべき管理上の措置」に関して指針を定めており、7つの事項を提示している。
(1)景品表示法の考え方の周知啓発
(2)法令遵守の方針等の明確化
(3)表示等に関する情報の確認
(4)表示等の情報の共有
(5)表示等管理担当者担当者を定める
(6)根拠となる情報を事後的に確認するための措置を採る
(7)不当な表示が明らかになった場合は迅速かつ適切に対応する
この対策を事業者が実効的に行っていれば、不当表示を未然に防止することができるだろう。
さらに、消費者庁が注目をしているNo.1表示はどのようなものか、過去の事例を見ておくことも重要だ。
「2023年度の課徴金納付命令事例で、オンライン個別学習指導に関する役務のNo.1表示が対象となったケースは、課徴金が6346万円と高額であり、注目すべき事例の1つであると言えます」
「利用者No.1」の表示は、ユーザーにインパクトを与え、利用を後押しするものである。しかし、一般消費者に誤認されるような用い方をしてしまうと、上記のように高額な課徴金が課されることもあり得るため、その点について事業者は理解しておくべきである。
利用者No.1表示で注意すべきこと
利用者No.1表示をする際には、客観的な調査を元に、利用者No.1であるかを、適切な形で引用していることが重要だ。
「No.1表示をする際には、客観的な調査を実施した上で、商品の範囲、地理的範囲、調査期間などを明瞭に示しておくことが重要です」
渡辺弁護士は、No.1表示をする際の留意点として、次のとおり述べている。
「どのようなカテゴリーの商品で利用者No.1なのか、また、どの地理的範囲においてその商品はNo.1であったのか、調査期間や時点はいつなのかといった点を明瞭に表示することが望ましいとされます。それから、No.1の根拠となる調査の出典を明記しておくことも重要です」
裏付けとなる根拠がなく、「利用者No.1」と表示してしまうと、どのような調査をいつ実施してNo.1になったかが分からず、疑わしい表示となってしまうので、注意が必要だ。
「表示したいNo.1の種類によって異なりますが、定期的に表示のチェックを行うことも重要です。ある程度の期間が経過してしまうと、ランキングの変動等もあり得ますし、先述したNo.1表示に根拠があると言えなくなってしまう可能性もあるので、定期的な見直しをお薦めします」
ペナルティ対象となる人は
No.1表示で問題のある表示をしてしまった場合、責任を問われるのは事業者だ。仮にNo.1表示の調査を行う調査会社が提示した調査結果が実態と大きくかけ離れたものであったとしても、基本的には広告主の判断として表示したと判断され、措置命令の対象となる。
「No.1表示が不当表示に該当するものである場合、措置命令や課徴金納付命令といった行政処分があり得ます。また、直近の景品表示法の改正により、刑事罰(直罰)が課せられるリスクもあります」
調査会社の杜撰な調査を実施した場合でも、事業者が気づけなければペナルティを受けるのは広告主である。調査内容に信頼性の欠ける調査を実施する調査会社かどうかを見分けるために、調査前の打ち合わせはもちろんのこと、裏付けとなる根拠資料の提示を要求した上で、その内容を確認しておくと良いだろう。
まとめ
利用者No.1表示は、他のNo.1表示と同様に注意が必要だ。景品表示法は利用者にとって誤認を与えるような表示をした広告主を厳しく取り締まる法律だ。
適切な運用を心がけていたと思っていたとしても、消費者庁の調査が入ることもある。万が一調査が入ってしまった場合でも、客観的にNo.1であることを示すことができれば、最悪の事態を回避することができる。とはいえ、どのような点に注意すべきか分からない時は、一般消費者の視点に立って、誤解を生むような表示となっていないかを確認しておくと良いだろう。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年04月15日
2024年04月15日





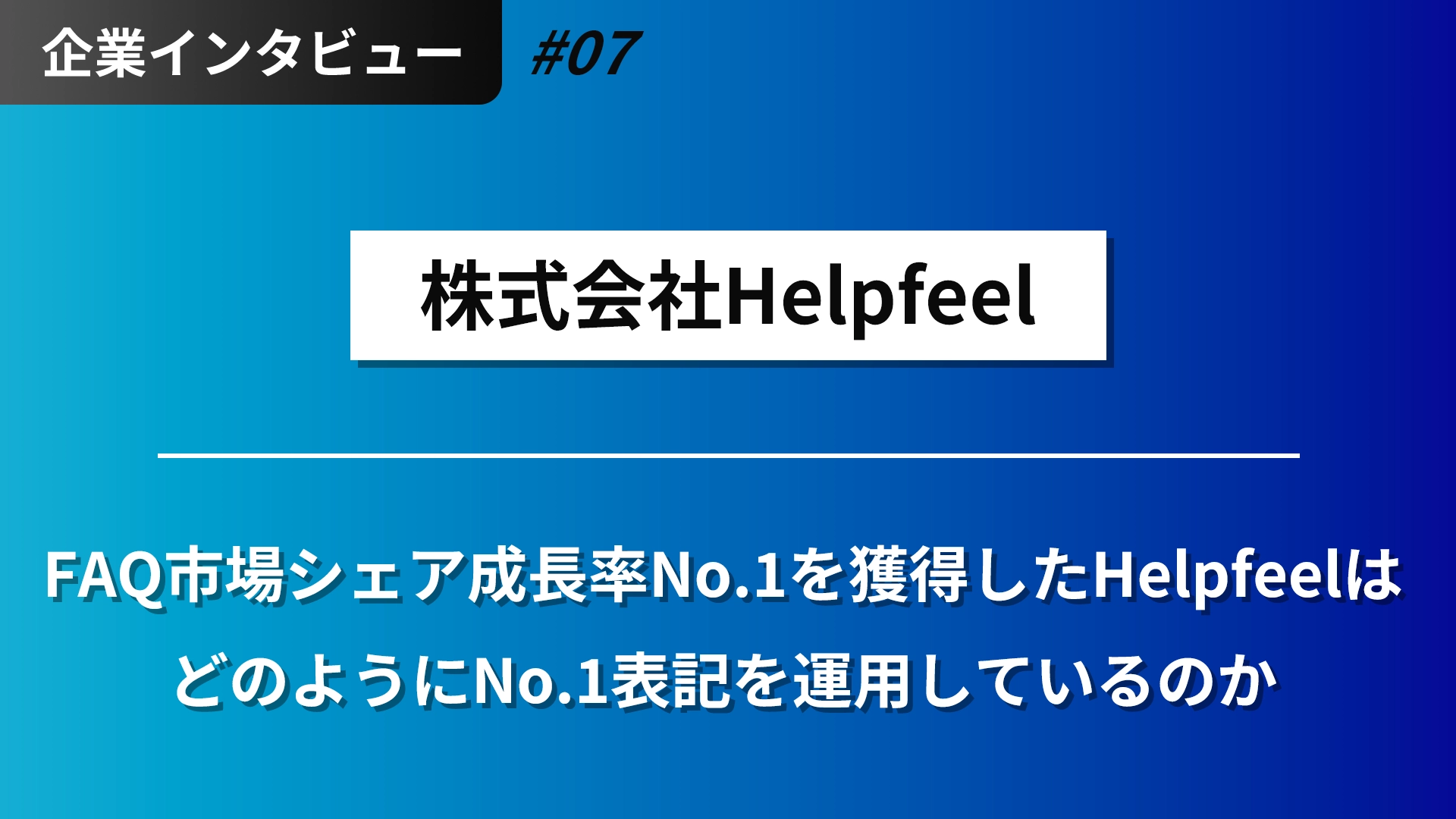

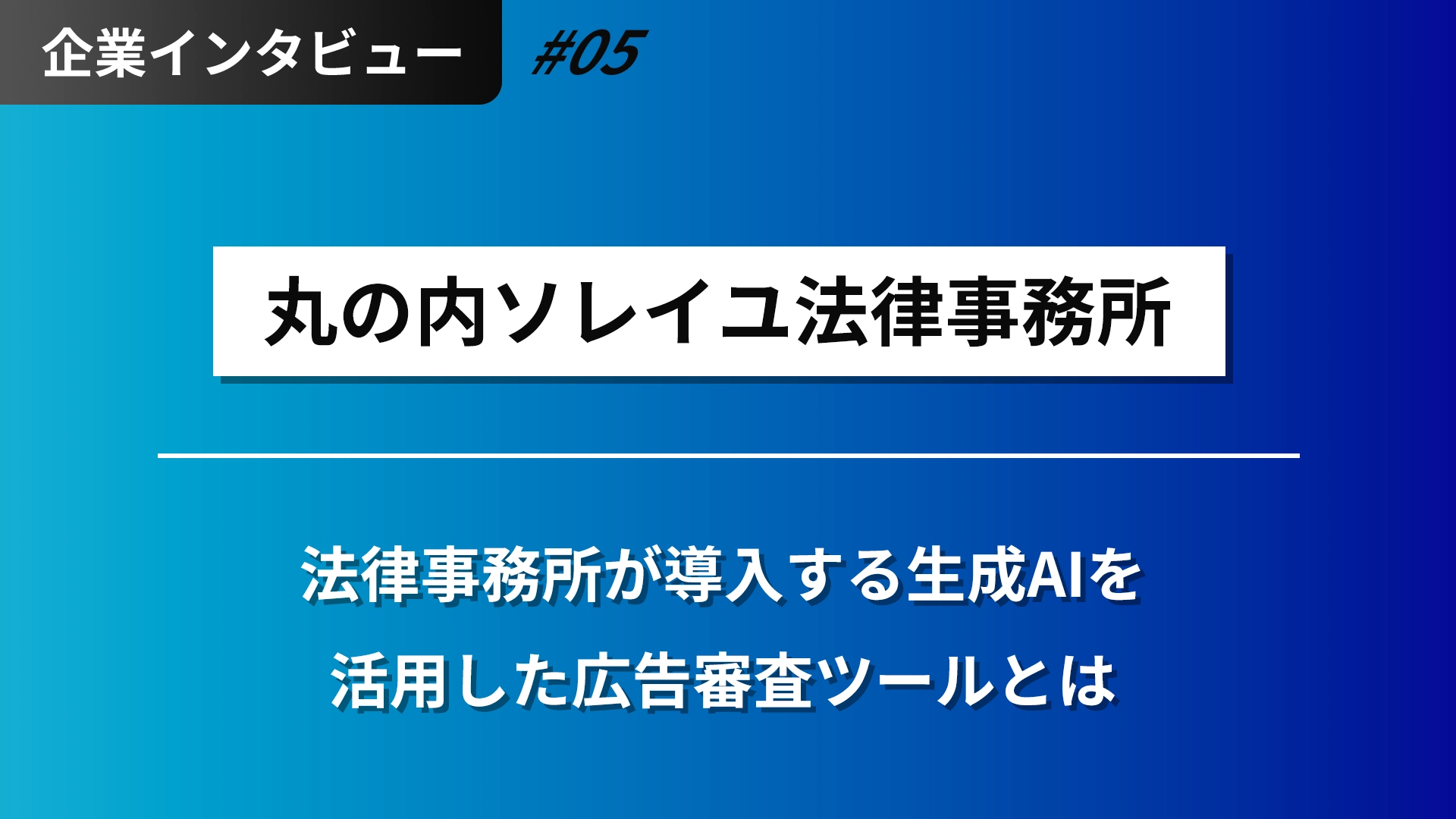
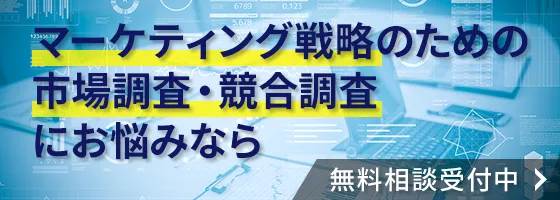
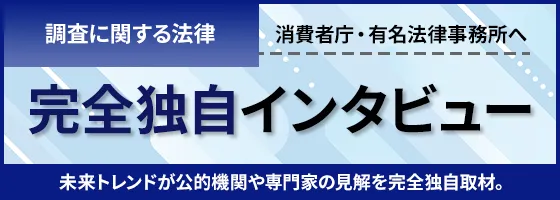
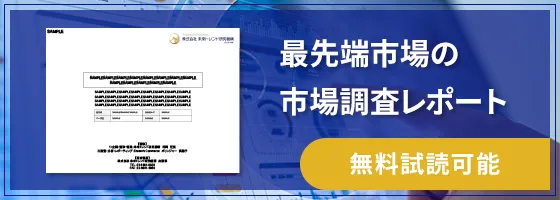


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com