
 本文
本文課徴金納付命令の基準
消費者庁が景品表示法違反と判断すると、行政措置命令発出という形で発表される。その後、一定の期間を空けて課徴金納付命令となる。しかし、行政措置の中には課徴金納付命令に至らない事例もある。どのような基準を持って課徴金納付命令か否かを決定しているのかについて、消費者庁 景品表示対策課に問い合わせをした。
原則課徴金納付命令が関係
消費者庁の担当者によれば、課徴金納付命令について誤った解釈をしている事業者も少なくないと言う。
「課徴金納付命令は売上が少なければ対象外と考えている事業者さんもいらっしゃいますが、対象外ではありません」
仮に問題のあるNo.1表示を掲載した期間が1日のみの場合、課徴金納付命令の対象となるものは1日のみのため、金額がそこまで大きくかからないので大丈夫だという認識をしている事業者もいる。措置命令と課徴金納付はセットで考えると良いだろう。
「措置事例の発表後に課徴金納付命令を行う際は、景品表示法に基づいて課徴金を算定しております。金額の算定基準に基づいて課徴金を算出します。景品表示法違反が疑われる表示を掲載した期間に売り上げた金額に対し加算されます」
問題のある表示と判断された場合は、どのような事情があるにせよ、課徴金納付の可能性が高いと考えておくと良いだろう。
なぜ課徴金納付命令までに期間を要するのか
では、行政措置が出されてから一定の期間を経て課徴金納付命令となるのか。その理由は措置事例後に行う調査が理由とのこと。
「課徴金納付命令の際は、調査期間が一定期間必要なこともあります。そのため、1年程の期間が必要になってしまう事例が多く、措置事例から1年後に時間差で課徴金納付命令が出されます」
措置事例と課徴金納付命令が時間差で発出されることで、2度メディアで取り上げられる可能性がある。その度に事業者は信頼回復に向けた行動が求められるため、注意が必要だ。
事業者へのペナルティ
事業者の中には「課徴金納付命令を免れることが出来れば、行政措置は発表に過ぎない。刑事罰のような重いペナルティではないため、リスクを承知で強い表現をしても構わない」そう考える事業者も存在する。
しかし、措置命令が発出された場合でも事業者にとってマイナスな面があると担当者は説明する。
「事業者の方が金額的な面で考えれば問題ないかもしれません。しかし、過去に行政措置を受けたという事実は一定期間記録として残り、その後もネットで簡単に検索出来ます。事業者さんが展開しているビジネスによってはお客様の信頼を失う可能性があると考えています」
過去に行政措置を受けた事業者をネットで検索すると、予測キーワードにネガティブな情報が提示されるケースが多い。インターネットでは一度悪い情報が拡散されてしまうと、その情報を正しい状態に戻すためにはそれ相応の期間が必要になる。
開業して間もない事業者であれば、行政措置を受けた場合でも被害は少ないかもしれない。しかし、他の事業で成功をして認知度もある一定の事業者は行政措置事例だけでも、影響があると考えておくのが良いだろう。
事業者に求められること
今後もNo.1表示に関する課徴金納付命令を避けるために、どのようなことをすべきか。改めて確認すると、「調査会社との付き合い方」を意識する必要があると担当者は説明する。
「表示の最終的な責任を負うのは事業者であり、調査会社ではありません。いくら杜撰な調査を実施しても、その表示を掲載するかを判断したのは事業者だと受け止めるため、その点への認識が必要かと思います」
担当者によれば、仮にグレーゾーンと呼ばれる問題のある表示が調査対象となった場合でも、適切な裏付けとなる調査資料等があれば、行政措置を免れる可能性もゼロではないとのこと。もちろんケースバイケースであるが、調査時に提示された資料を精査した結果、お咎めなしというケースもあるという。
だからこそ、事業者は日頃から表示に対して適切な運用を心がけることが重要だ。自身で対策をどうすべきか不安を感じている場合は、弁護士など専門家に企業法務体制を確認してもらうだけでなく、平時から適切な運用を心がけておくことが重要だ。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の消費者庁インタビュー
関連コンテンツ
弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2025年06月19日
2025年06月19日





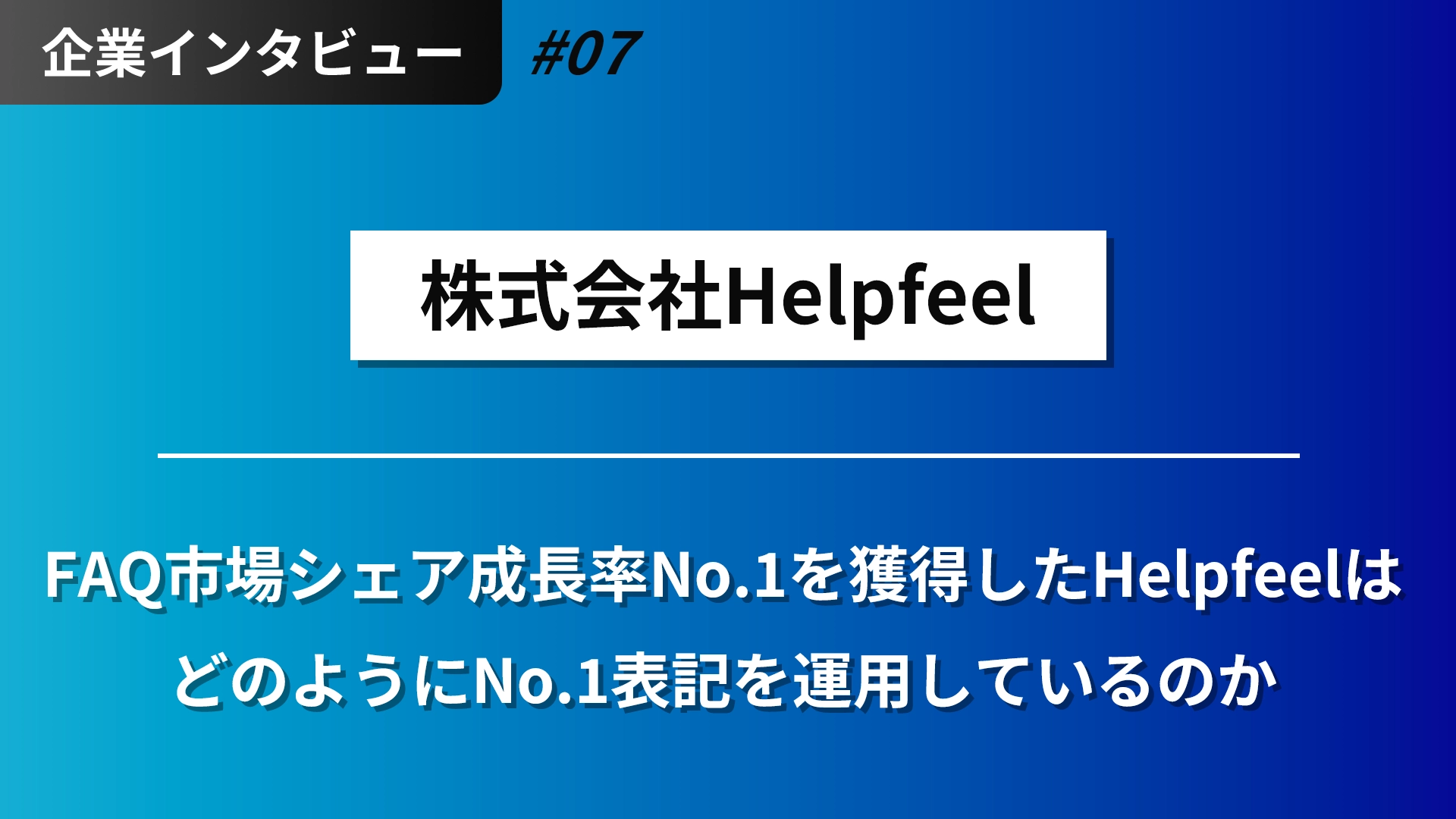

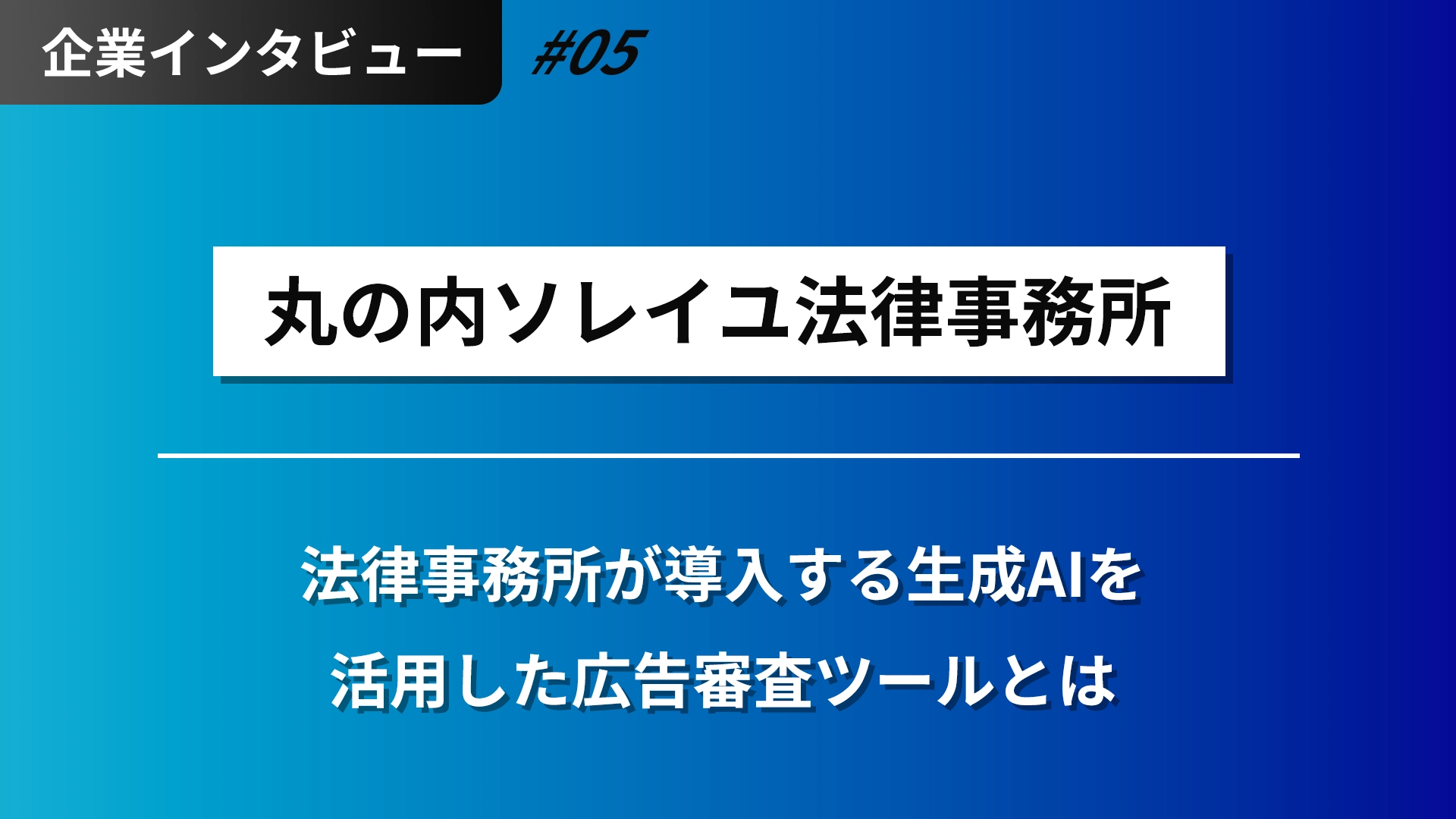
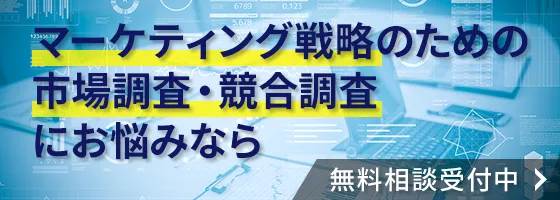
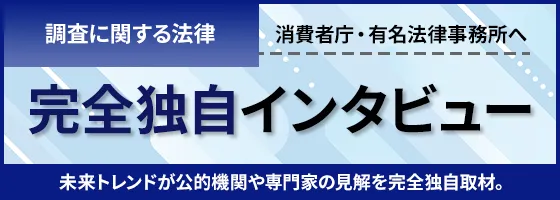
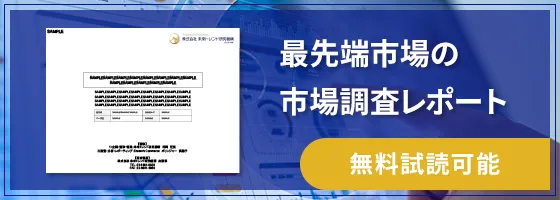


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com