
 本文
本文動画に関する注意すべき表示事例
2025年6月16日に、株式会社フォレストウィルに対して課徴金納付命令が発出された。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/042622/
この表記は「日本初」や「No.1」といった表示ではないが、消費者庁が「問題のある表示を調査したところ、事業者から提示された資料が裏付けとなる資料とは言えなかった」とした事例である。
この事例を熟知しておくことで、表示を運用する際のヒントになると思い、消費者庁表示対策課に問い合わせを行った。
根拠のない資料かどうかを精査する
フォレストウェルに対する課徴金納付命令では、「空気清浄機があたかも室内に設置すれば、マイナスイオン及びオゾンの作用により、25畳までの空間室内に浮遊する地理やアレルギー物質を除去する」という働きを紹介していた。しかし、客観的な資料はいずれも該当せず却下されたというものであった。
当然のことではあるが、消費者庁の調査時に消費者庁が納得出来るような資料を提出出来なければ、行政措置の対象となる。
「今回の措置事例では、事業者側に裏付けとなる資料を求めた際に動画に掲載したグラフの裏付け資料にも及びました。事業者は動画に掲載したグラフが裏付けの根拠となると主張していましたが、資料は有効的なものであるとは言えず、その結果、消費者庁の課徴金納付命令の対象になってしまいました」
消費者庁が特定の表示に対し調査を行い、資料を提出するまでの期間は約2週間程度と言われている。その期間内に事業者が適切な資料を用意することが出来なければ、措置事例に移行するケースもある。管理措置指針に則って運用していれば、適切な資料を即座に提出出来るため、この点は懸念する必要は無いだろう。
動画内表示をする際に注意すべきこと
今回の事例では、動画内の表示に対しても言及されたケースであり、消費者庁はチラシやHPだけでなく、動画に関しても把握していると理解しておいた方が良い。
動画の表示で注意すべきポイントを改めて整理しておこう
視認性を意識する
動画内でNo.1をはじめとした表示の注釈を記載する際は、視認性を意識して配置を検討しておく必要がある。正しい情報を記載していたとしても、表示時間が極端に短かったり、フォントがあまりにも小さい場合は消費者の目に入らなかったと見られる可能性もある。第三者がその動画を初めて見た時でも、正しく視認できるかどうか、という視点で確認しておくと良いだろう。
概要欄や文章でも補足する
動画本編に注釈を見える位置に配置をしていると、表現の阻害をしてしまう恐れもある。そのような時は、概要欄等を活用して説明するアプローチも1つの手だ。しかし、注意すべきポイントがあるという。
「注釈を概要欄等に記載するアプローチは良いと思いますが、視聴者が必ずしも情報をチェックするとは限りません。注釈の情報が概要欄に記載されている、画面上に表示されたQRコードを読み取ると解説が表示される、といった消費者に対して誤解を与えない仕組みが必要になります」
広告を掲載する際は視聴者に誤解を与えないよう、表示を適切に配置することを心がけて動画を作成することを推奨する。
打ち消し表示は効果がない
動画の中でよく多用されている表示が「個人差があります」「個人の感想です」といった注釈だ。仮に化粧品のような製品に対し、このような注釈を記載しているからといってもお咎めなしという訳では無い。打ち消し表示は、根拠がない表示として、景品表示法への意識を持っている人であれば理解しているものの、まだまだ認知度が足りないとのこと。
「注釈を記載すれば、消費者を勘違いさせないようにしているという見解を持っている事業者さんもいます。しかし、このような注釈は効果の根拠にはなりません。最近では専門家が評価したという表示もNo.1表示と同様に注目をしている表示のため事業者はそれ相応の注意が必要です」
視聴者にとって理解しやすい位置に配置する
注釈や説明を行う際は、必ず視聴者が理解できるような位置に配置しておくことも重要だ。
「適切な説明をしていたとしても、別の動画で詳しく解説をしていたり、注釈の説明を動画の終盤に行っていると、視聴者に誤解を与えてしまう可能性があります。動画でグラフを使用するのであれば、どのような実験を実施したのか、消費者でも理解出来る記載方法をしないといけません」
適切な裏付け資料を準備している場合でも、視聴者がその表示に対してどのように捉えるのか、という視点が欠けていると視聴者に誤解を与えてしまう恐れがある。この視点で動画全体を見直し改めて表示を見直しておくことをおススメする。
まとめ
今回は動画の表示に対して、消費者庁がどのように見ているかについて紹介した。動画は今や情報発信をする際には欠かせないアプローチであるが、一歩間違えてしまうと景品表示法違反の疑いのある表示として厳しくチェックされてしまうこともある。このような視点に注意しておくと良いだろう。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2025年06月19日
2025年06月19日





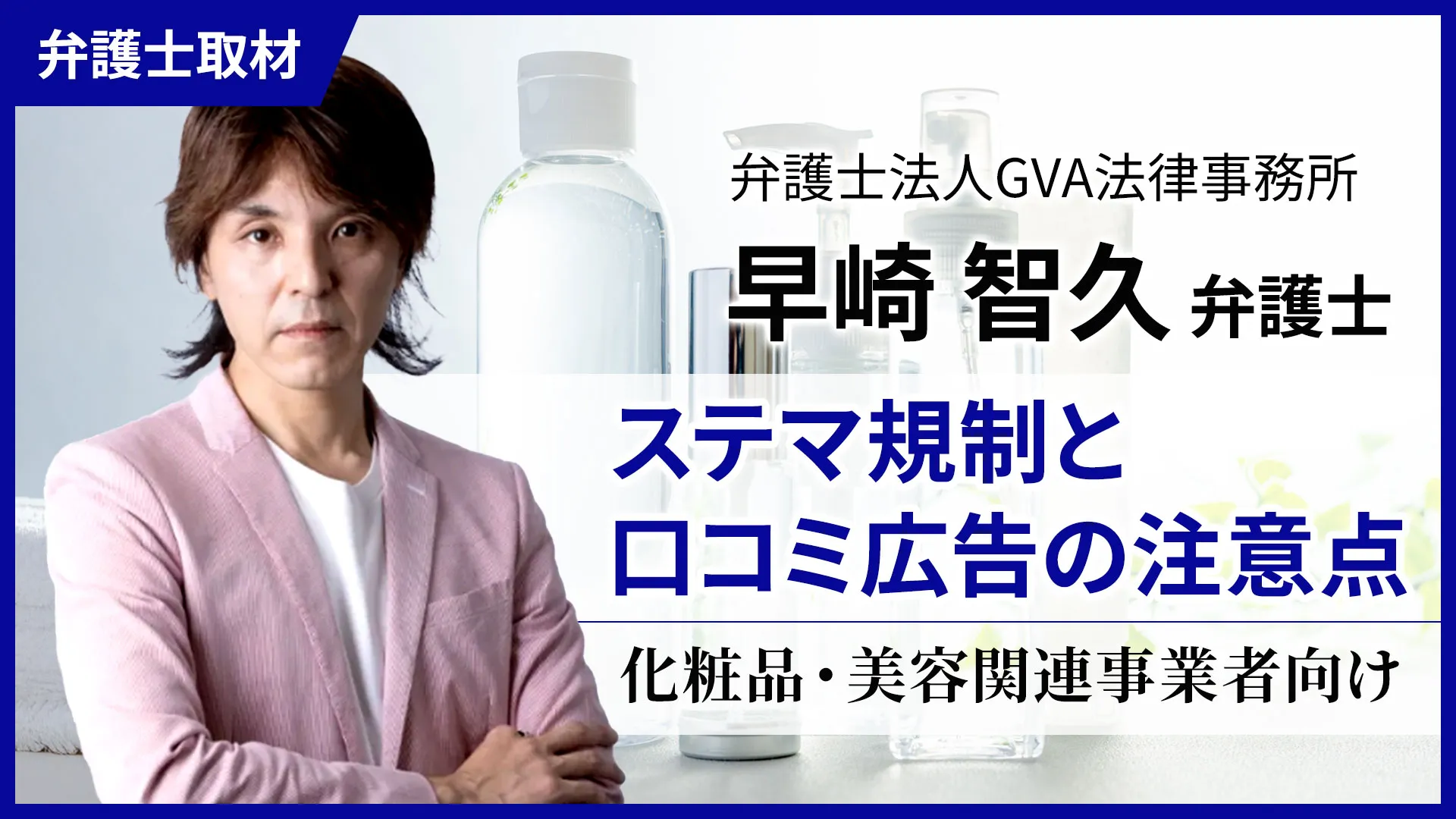
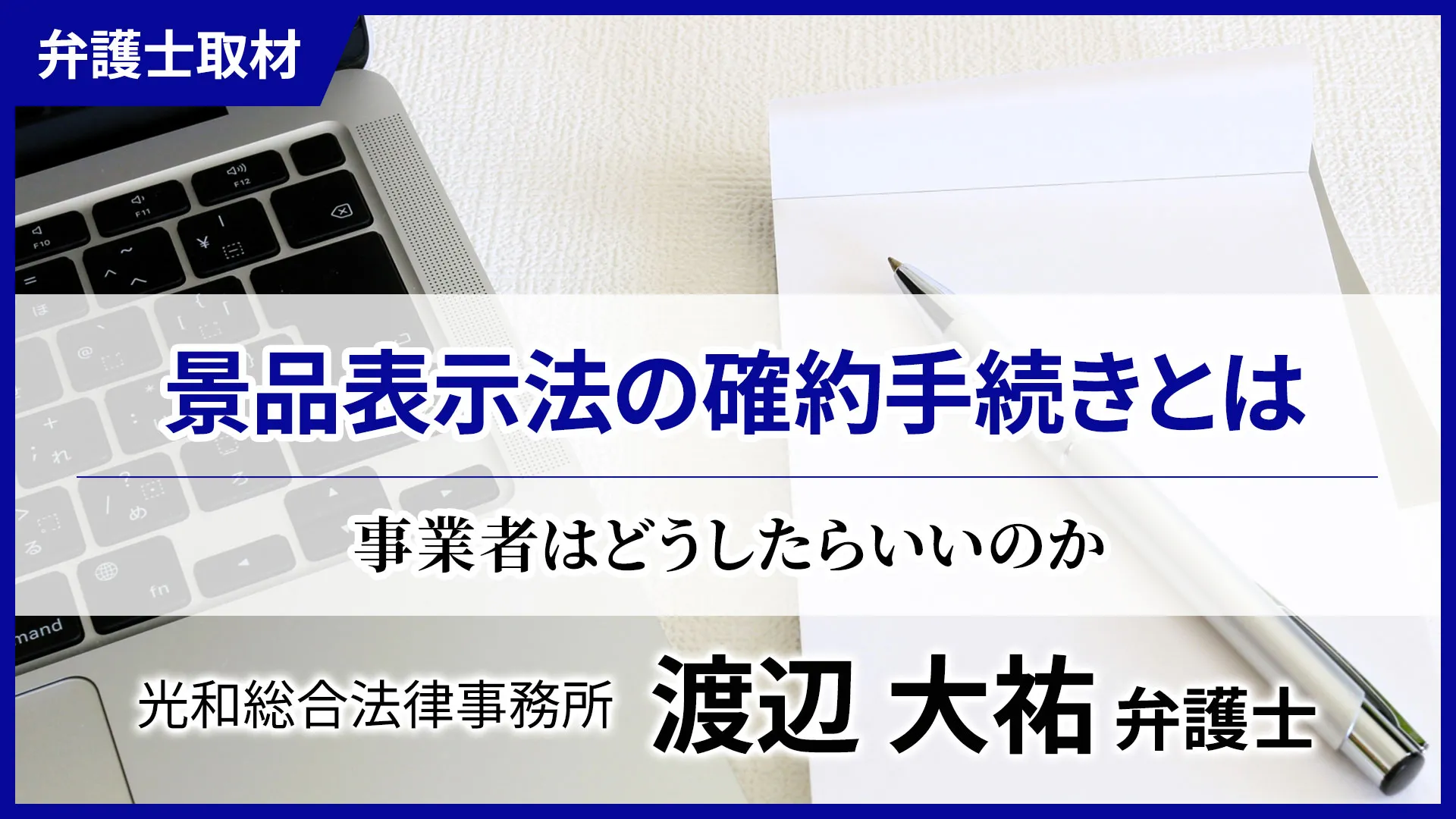

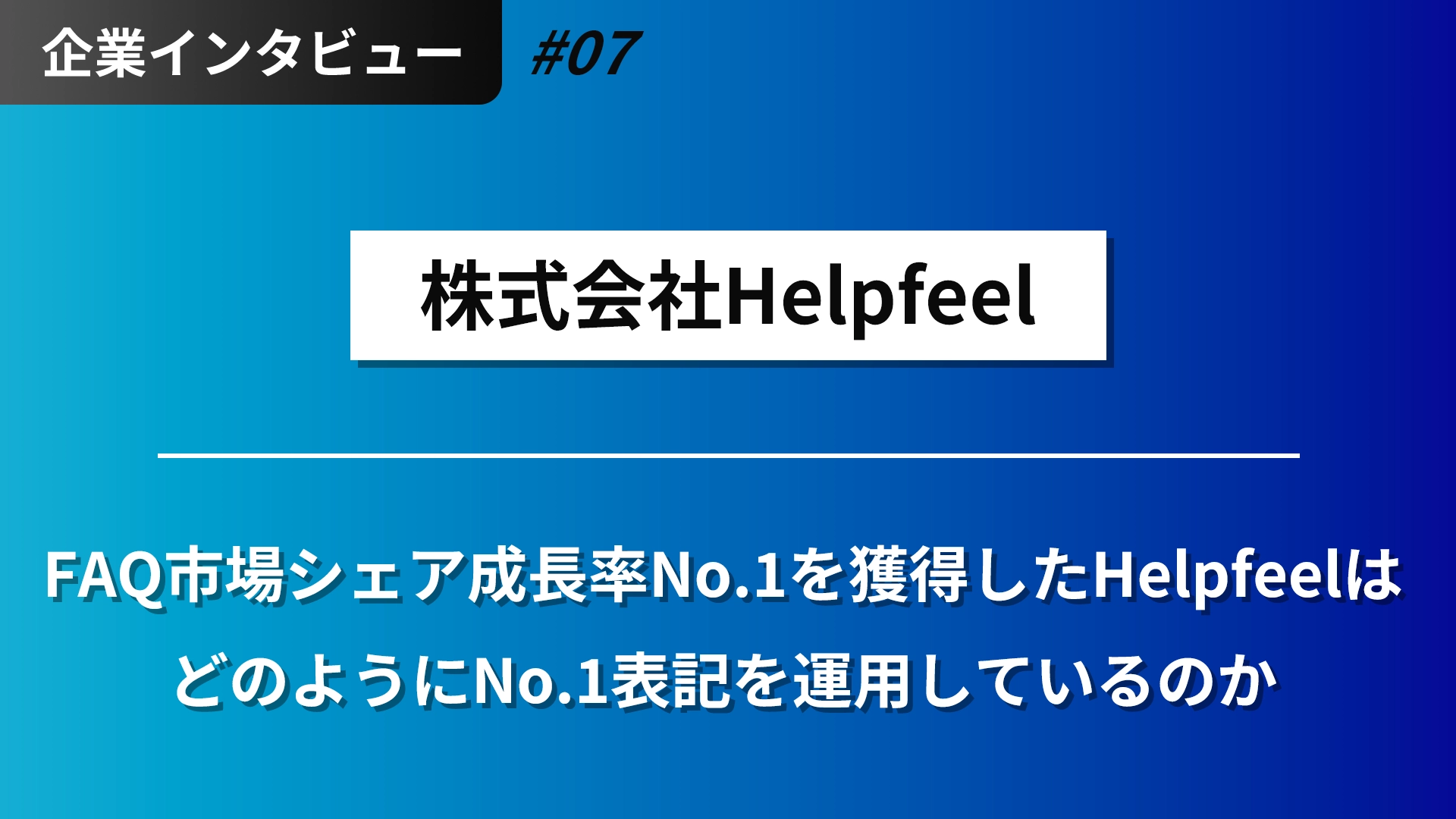

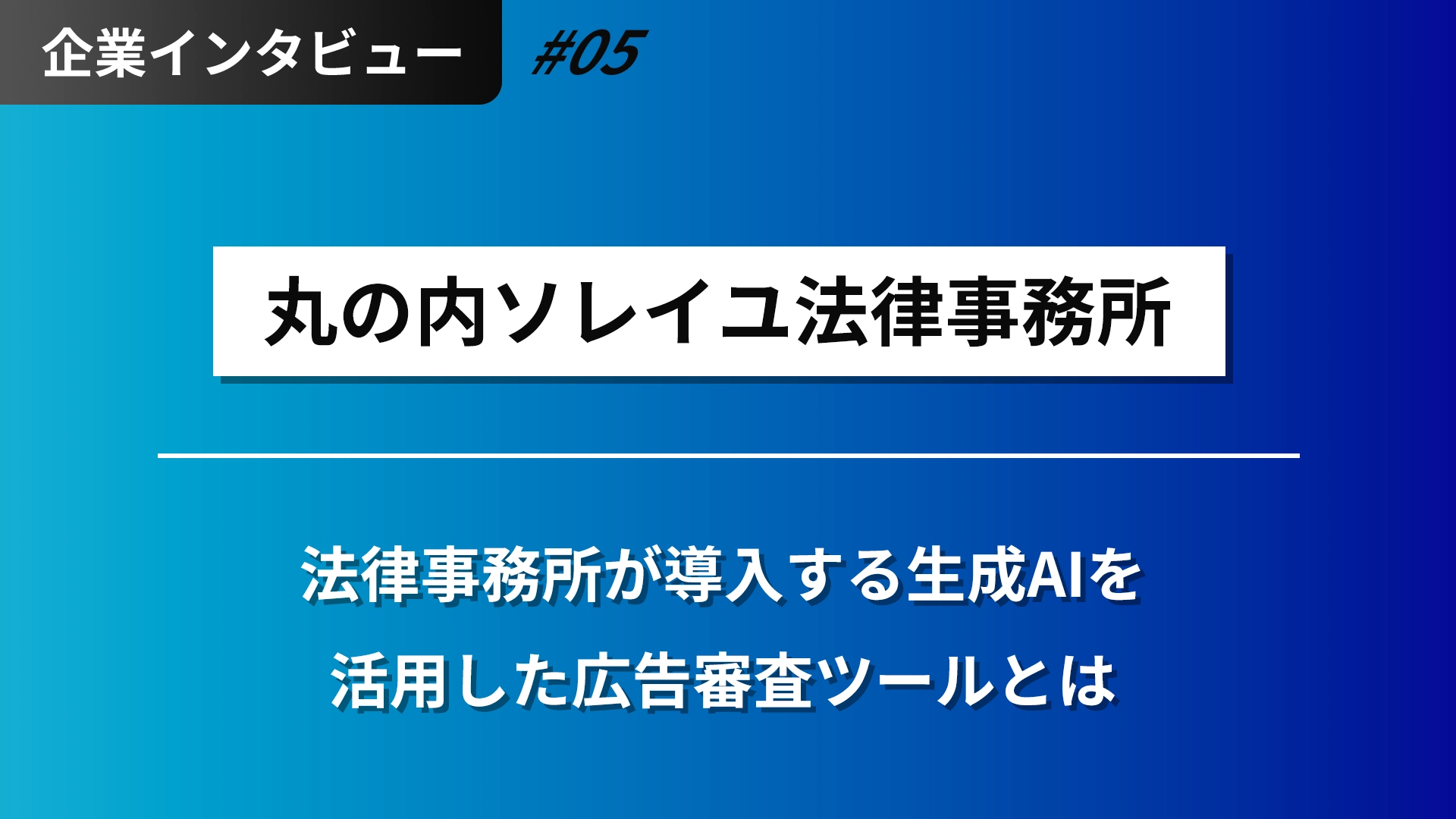
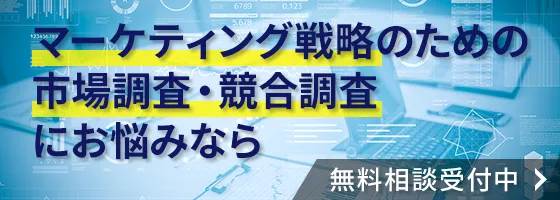
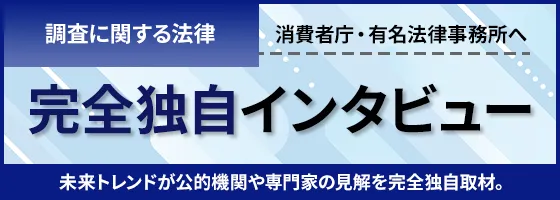
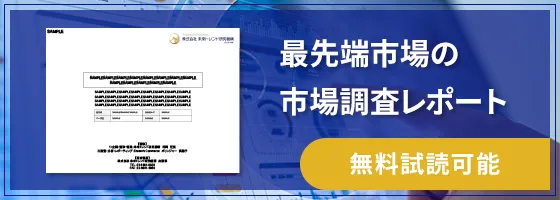


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com