
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
牛島総合法律事務所
石川 拓哉 弁護士
いしかわ たくや
石川拓哉弁護士(第二東京弁護士会所属)
https://www.ushijima-law.gr.jp/attorney/takuya-ishikawa/
企業(上場・非上場)のガバナンス・コンプライアンスに関する対応や、海外関連の事案など、幅広い企業法務を担当する。相談者に対し、きめ細かいヒアリングを実施するだけでなく、難しい案件を分かりやすく説明する。
一般企業法務
企業(上場・非上場)における法律問題に関するアドバイス
企業のガバナンス・コンプライアンスに関するアドバイス
M&A・組織再編(会社分割・株式交換・事業譲渡等)に関するアドバイス
医薬品・医療機器の法規制に関するアドバイス
セミナー実績
【法改正ステーション#31】No.1表示に関する実態調査報告書の企業への影響(LegalOn Technologies)
 本文
本文自社調べの限界〜No.1調査を自社調べで実施するためには〜
No.1表示を行う際に、事業者は調査会社に依頼して表示の裏付けとなる客観的な調査を行い、調査結果についての客観的資料を作成することが望ましいと言われている。しかし、絶対に調査会社に依頼しなければならない訳ではない。
景品表示法が定めている要件や、当局が示す考え方を満たす調査を行い、合理的な根拠に基づく表示であることを証明できる客観的資料を作成出来れば、自社調べでも可能である。今回は自社調べを実施する際に注意すべきことは何かについて、牛島総合法律事務所石川拓哉弁護士に話を聞いた。
牛島総合法律事務所
https://www.ushijima-law.gr.jp/
会社法、M&A、不動産取引、建築、環境法、IT、情報管理、労働法等の各領域で専門性を有する弁護士が数多く在籍。企業の社会的責任(CSR)を見据え、企業の事業の特性によるリスクに応じ、適切なコンプライアンス体制の構築の支援、様々なリスクに対応したコンプライアンス社内研修・セミナーの実施、内部統制システムの構築に関する提案、コンプライアンスマニュアル・内部通報マニュアルその他各種内部組織の規則等の作成などを行う。
現在、Multilaw、ELAおよびLAW の日本における唯一のメンバーファームとなり、クロスボーダー案件を扱うにあたって、これらグローバルネットワークも駆使して、現地の法律実務に精通した、トップレベルの現地法律事務所と連携して、グローバル内部通報制度の設計・運用を進めていくなど、グローバル企業のコンプライアンス体制の構築にも対応。
最高のクオリティのリーガル・サービスを、適正な価格で速やかに、ワンストップで提供できる体制を整えている。
自社調べを成立させるために行う事
石川弁護士によれば、自社調べのリスクは2008年に公正取引委員会が発表した報告書で既にリスクとして紹介されているとの事。
「当時景品表示法の所管だった公正取引委員会の報告書内で、No.1表示を自社調べで実施するリスクが指摘されています。自社調べは独自の基準で、恣意的な調査を実施してしまう恐れがあり、客観的な調査であることを証明出来るような資料を準備しておかなければなりません」(石川弁護士)
客観的な調査とは具体的にはどのような調査か。
「客観的な調査とは、No.1表示を行う場合は、社会通念や経験則に照らして妥当と判断されるかどうかという視点で、表示の内容、商品等の特性、それから関連分野の専門家が妥当と判断するか否かなどを総合的に勘案して判断されます。No.1表示の場合は、実務上、大きく分けて「売上」「安さ」「顧客満足度」の3つの類型がよく見られますが、それぞれに適した資料が必要になります」(石川弁護士)
No.1表示を自社調べで実施する際に、客観的な調査であることを証明するためには、以下のポイントで調査を進める事が重要だ。
- 比較対象となる競合商品・サービスを適切に選定する
- 調査対象者を適切に選定する
- 調査を公平な方法で実施する
「No.1と表示出来るかを客観的に提示する調査とするためには、事業者が表示の対象となる商品に関する競合商品を適切に選び、データを示す事です。競合商品に漏れがないことを客観的に評価出来るようにするため、売上、販売数量、出荷量、ダウンロード数など、客観的なデータを収集しておきましょう。
主要な競合商品を意図的に除外して調査を実施してしまうと、客観的な調査と言えなくなってしまいます。また、仮に意図的でなくても、インターネットの検索結果で上位表示された商品のみを選定し、主要な競合商品の一部が抜けたまま調査を実施するのも問題です。
次に、調査対象者の選定については、アンケートの回答者を恣意的に選んだとみられないよう、自社の社員や関係者、自社商品を継続的に購入している顧客だけを回答者とすることは避け、回答者を無作為に抽出する必要があります。
また、顧客満足度の調査をする場合は、実際に対象の商品やサービスを利用したことがある者を対象とする必要があります。調査の実施方法については、アンケートの設問に対しても注意する必要があります」(石川弁護士)
顧客満足度の調査を実施する際に、自社の商品をアンケートの解答欄の最上位に固定して表示させた場合、恣意的な調査項目を設定したと受け止められる恐れがある。事業者の都合の良い調査結果とみられないよう、担当者だけではなくそれ以外の部署の目でアンケートの方法が適切かどうかを検証しておくと良いだろう。
「顧客満足度の調査では、No.1を取れた時点で調査を終えてしまうこともあります。No.1表示が取れたら、終わりという結論ありきの調査ではなく、客観的・網羅的な調査を元にNo.1と言えると証明しておくことも重要です。自社調べを実施する事業者は主観的に調査を進めてしまうと当局から疑われる傾向があり、いかに恣意的な調査でないかを証明する事も重要です」
万が一自社調べで消費者庁から注目された場合、指摘を受けてから客観的資料集めをすれば問題ないと考える事業者もいるかもしれない。しかし、指摘後に資料集めをするようでは遅いと石川弁護士は言う。
「消費者庁は事業者に15日以内で調査の根拠資料を提出するように通達します。表示を行う事業者は、表示の裏付けとなる合理的な根拠資料をあらかじめ有しているべきであり、すぐに提出できるだろうという事です。実際、客観的な資料を15日間で集めることはハードルが高く、不可能に近いと言えるでしょう」
上記以外にも調査の根拠を提示する際に、表示と共に直接記載するのが難しければQRコードを配置したり、直近の調査結果といえるために適切な期限を設けてNo.1表示を行うなど気を付けるポイントは多い。
調査結果の引用がNo.1表示の要件を満たすために言われている「商品・サービスの範囲」「地理的範囲」「調査時点」「調査の出典」以外にも気をつけなければならないことが多いと理解しておくと良いだろう。
自社調べの限界
今回紹介した自社調べのポイントをまとめると
- 客観的かつ適切な調査を実施していると証明できるかどうか
- 事業者の主観で調査を実施し、恣意性が排除されていないか
上記2点が自社調べにおいて最も重要であるが、第三者が見ても適切な調査かどうかを証明するためにはかなりの労力が求められる。企業内の法務部や顧問弁護士も、組織内の距離が近すぎると恣意的な調査結果に気づかずに表示してしまう可能性も高い。
「No.1表示で重要な視点は一般消費者の感覚です。これなら大丈夫と事業者が感じていても、商品について十分な知識がなく、距離の遠い消費者は違う形でその表示を捉える可能性があります。自社調べを行う場合でも、第三者の立場にいる人間の視点でチェックすることが重要かもしれません」(石川弁護士)
自社調べでも理論上No.1表示を証明することは可能であるが、改めてどのようなリスクがあるのかを見直し、それでも事業者自身で調査を実施するか、あるいは調査会社に依頼するか、専門家にも相談しながら検討しておく事を推奨する。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2025年05月23日
2025年05月23日





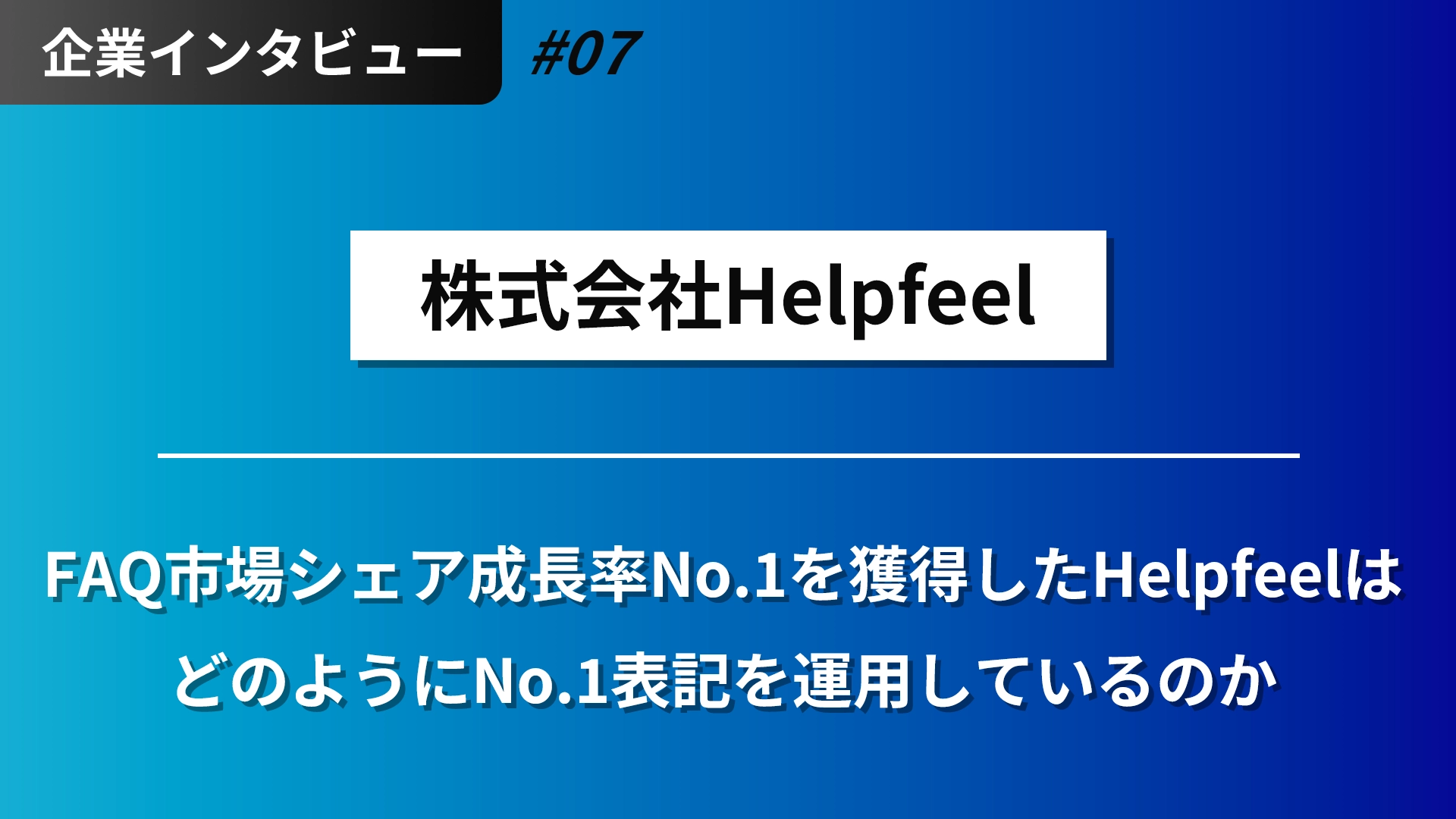

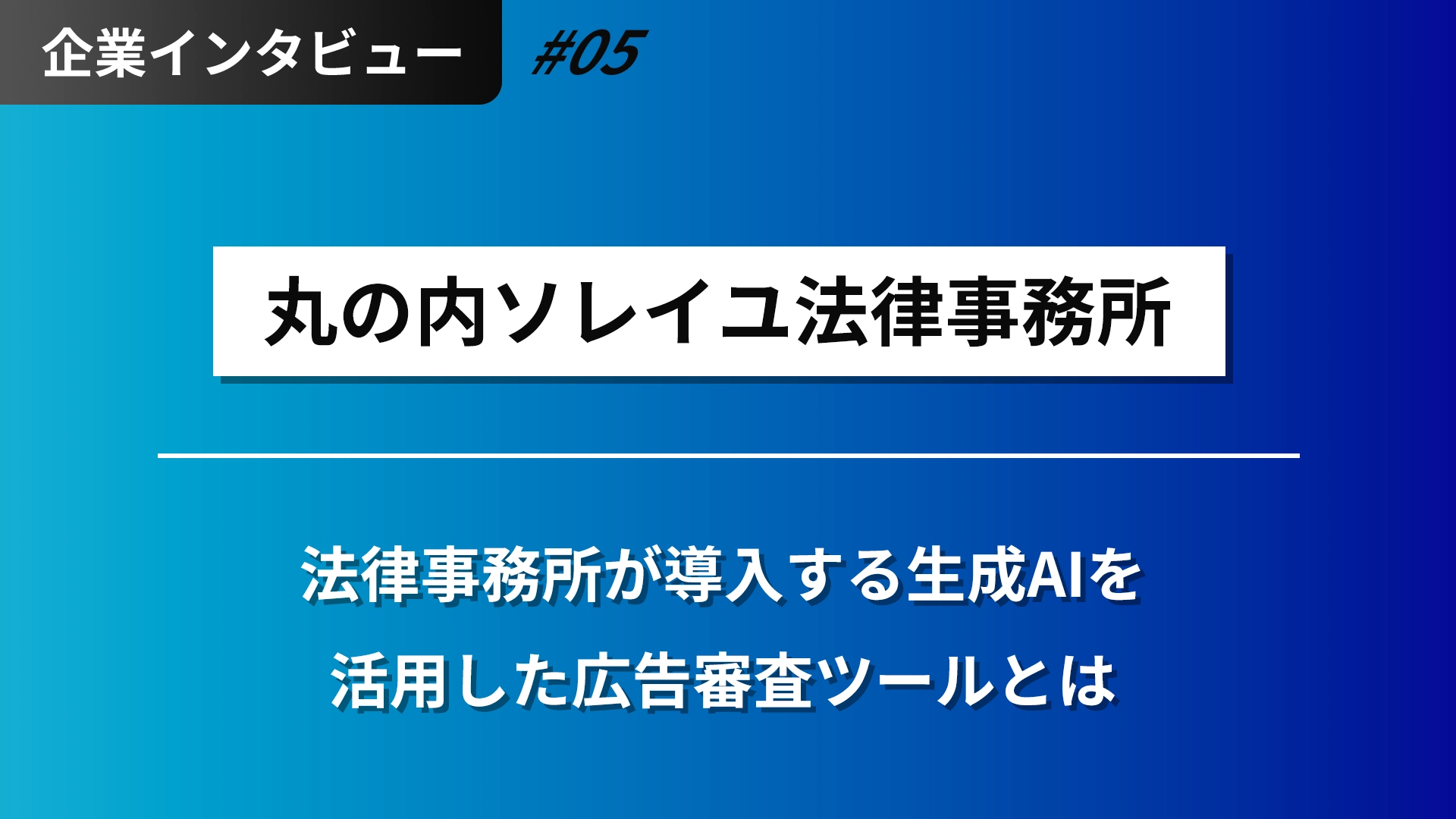
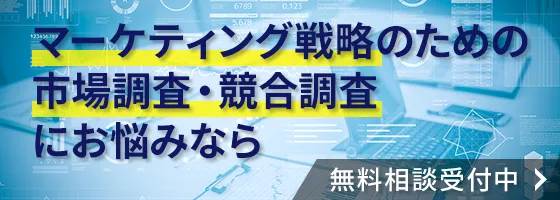
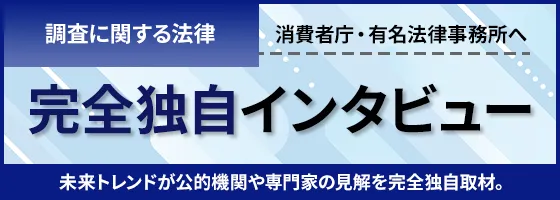
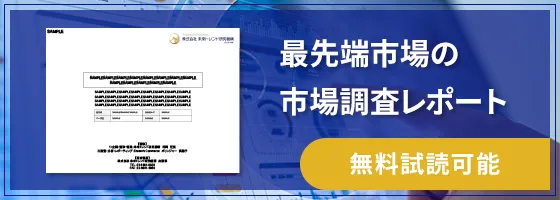


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com