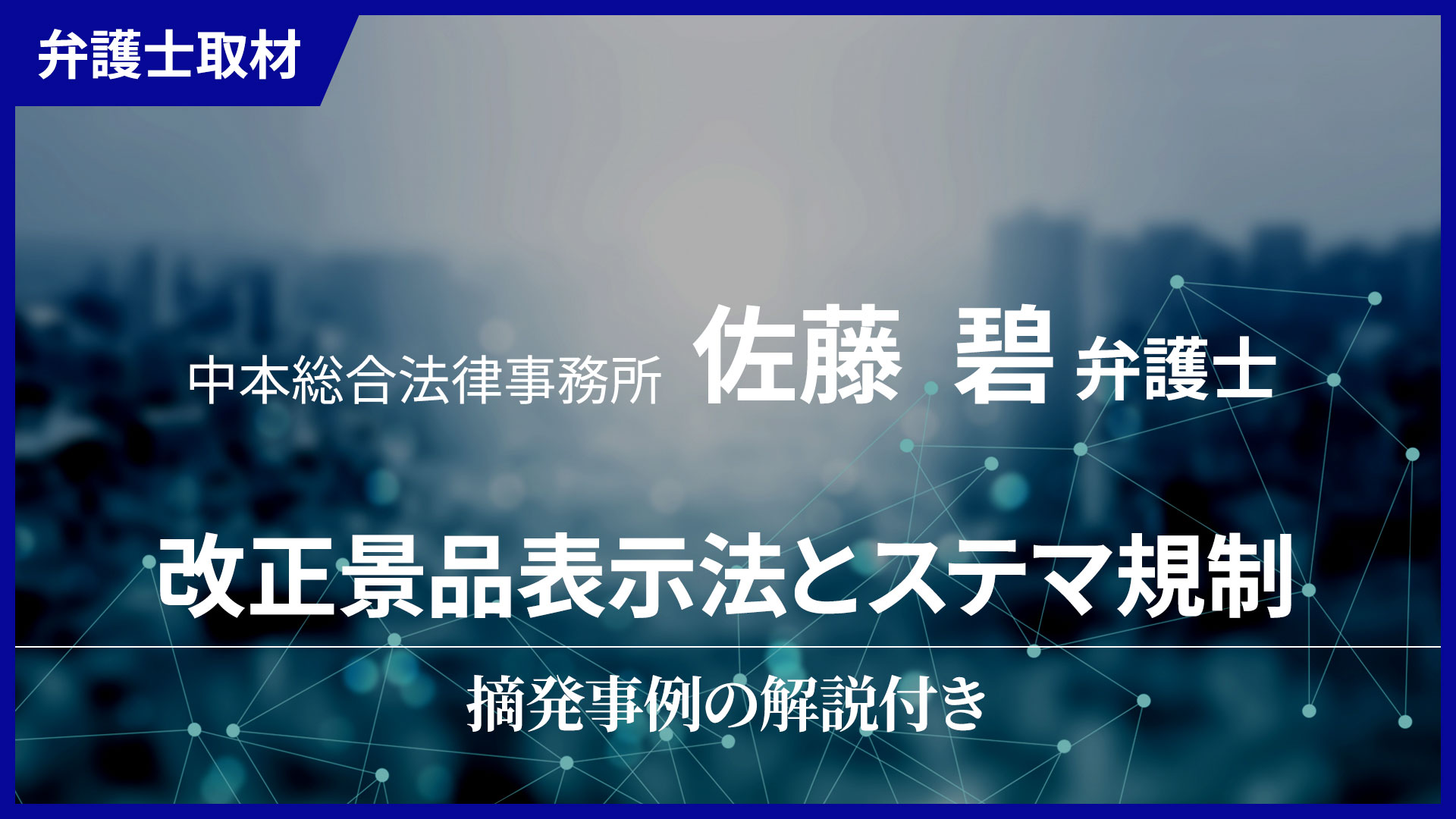
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール中本総合法律事務所
佐藤 碧 弁護士
さとう あおい
まっすぐ。をモットーに、景品・表示規制をはじめとする消費者法全般、民事、商事一般、少年事件、労働事件を取り扱う。2011年〜2014年には、消費者庁に出向し、消費者制度課において消費者の財産被害に係る行政手法の検討等、表示対策課において景品表示法違反事件の調査等を行う。
 本文
本文ステマ規制の基礎知識と事業者がやるべきこと
改正景品表示法(以下 景表法という。)が2024年10月1日から施行され、新たに確約手続の制度が始まった。
事業者はこれまで通りの対策が求められるが、新たな規制などの情報は最新情報にアップデートしておく必要がある。
その中で、消費者庁が注目しているものがステマ規制だ。2024年11月13日には大正製薬が販売するサプリメントについてのSNS投稿引用が景表法違反に該当するとして措置命令の対象となった。
https://x.com/caa_shohishacho/status/1856586315221148106
SNSを用いた広告戦略が当たり前となった今だからこそ、事業者が改めて知っておくべき情報について、別記事で取材協力をいただいた佐藤碧弁護士に話をお伺いした。
措置事例から学ぶ事業者が注意すべきポイント
ステマ規制とは、広告であるにも関わらず、広告であることを隠して宣伝する「ステルスマーケティング」を規制するものだ。
2024年11月20日時点でステマ規制違反を理由とする措置命令はこれまで3件あった。ステマ規制に対し事業者の知見がない場合は、まずどのような表示が消費者庁は注目しているのか、一度目を通しておくと良いだろう。
(1)医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令
Google マップの口コミを高評価したユーザーに対して割引サービスを実施した
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms204_240607_01.pdf
(2) RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
インフルエンサーに依頼したPR投稿を、自社のホームページで「一般ユーザーの声」として反映した。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038980/
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240809_02.pdf
(3)大正製薬株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
インフルエンサーに依頼したPR投稿を、自社のホームページで引用した
https://www.caa.go.jp/notice/entry/039990/
https://x.com/caa_shohishacho/status/1856586315221148106
上記⑵⑶において、事業者が過去にインフルエンサーにPR投稿を依頼したものをホームページで掲載する事例が立て続けに行政処分の対象となっている。この点について、佐藤弁護士は次のように解説する
「大正製薬とRIZAPに共通する問題点等、措置命令に対する見解を解説してください」
両社の共通点は、自社の商品、サービスについて、インフルエンサーに対しインスタグラムで投稿してもらうように依頼し、「PR」を付して投稿してもらった上で、その投稿内容を自社ウェブサイトに引用し(その際には「PR」を外していた)、第三者が自由に書いたものであるかのように表示をしてしまっていた、という点です。事業者としては自社ウェブサイトに引用していたことから、インフルエンサーの投稿部分についても広告表示として判別できると考えがちであり、2社とも同様の認識から上記のように表示してしまっていたようですが、消費者の目線からしますと第三者が自由に投稿していたものと誤認してしまう表示となっています。この消費者目線に立つことができていなかったことが本件の原因と思われますので、今回のケースを踏まえ、事業者において改めてステマ規制の周知徹底を行う必要があります。
特にPR投稿を自社のコンテンツとして扱っている事業者は、早急に対策を行う必要がありそうだ。
ステマ規制の基礎知識と対策すべきこと
そもそもどのようなポイントに気をつければ良いのだろうか。
「ステマ規制のポイントは、事業者が広告ではないように表示をしていないかを確認することです。例えば、自社の口コミで悪い情報が掲載されている場合、従業員に対し「悪い評価が多いので良い口コミを書いてくださいね」と指示して投稿させることも、ステマ規制に該当します。事業者はまず、ステマ規制がどのような事例に当てはまるか、上記の行政処分例やガイドラインなどを整理しておくと良いでしょう」
ステマ規制のことがよく分からない場合は、次の項目で事業者自身のこれまでの表示をチェックしておくと良いだろう。
- 広告を「PR」等付けずに通常の投稿のように発信していないか
- インフルエンサーのみならず…第三者(従業員、知人、ユーザー)に口コミ内容を指示していないか、内容の指示を実際にしていなくとも、投稿して欲しい内容が伝わるような依頼をしてしまっていないか
- インターネットだけでなく、テレビ、新聞、雑誌等も該当することを忘れていないか
この3つのポイントを元に表示を確認することがまず有用といえる。
「広告代理店経由で依頼する事業者さんは、広告代理店が指示する表示に対してのチェックも必要です。広告代理店の指示に沿って広告を掲載したら、知らないうちにステマ規制に該当しているというケースもあります。景表法は広告を出稿した事業者が責任を負う法律です。中間業者を介しても、事業者自身で表示の適法性を確認することが重要です」
事業者はステマ規制に対応するため、どのようなことに注意すべきなのか。佐藤弁護士によれば、「表示等の情報の確認」と「表示等に関する情報の共有」が特に重要とのこと。
「法令遵守の方針の明確化と周知徹底がステマ規制では最も重要な対策になると思います。事業者の内部でどのような投稿がステマ規制に該当するかの確認はその都度必要です。またステマ規制で措置命令を受けた事例を確認しておくことも重要です。その都度情報をアップデートしていけば、ステマ規制に該当するリスクを減らすことが出来るでしょう」
勝手PR投稿で気を付けるべきこと
最近ではステマ規制を恐れ、インフルエンサーやユーザーが「#PR」をつけて投稿するケースも散見される。このような投稿に対して事業者はどのような対応をすれば良いのだろうか。
「PRと付記して投稿されているだけで、ただちに景表法上の問題とはならないと思います。但し、行き過ぎた表現になっていて、事業者が表示に関与していることが疑われるような場合には、優良誤認表示として指摘される可能性はあります」
全ての投稿が事業者にとってマイナスな要因になる訳ではないが、行き過ぎた表記をしている投稿は事業者自身でチェックをすることが推奨される。
「事業者の中には勝手に広告が掲載されていないか等の観点から、定期的にSNS等をチェックする担当者もいます。1週間に1度など期限を決めて、問題のある表示が掲載されていないかを確認しておくことも重要です」
チェックする際に、過去に取引のあるインフルエンサーがいる場合は注意が必要とのこと。
「全く関係ないインフルエンサーが行き過ぎた表示をした結果、消費者庁の調査対象となっていても、全く関わりがないことを証明できれば事業者の表示と認定されないと思います。しかし、過去に当該インフルエンサーに広告を依頼したことがあるような場合には、関係性が全く無いことを証明出来ない可能性があるので注意が必要です」
パトロールをすることはもちろんのこと、インフルエンサーに依頼をする際は勝手PR投稿について、控えてもらうことを説明しておく必要がありそうだ。
まとめ
ステマ規制でSNS投稿を巡り不安を抱える事業者も多いが、適切な表示対策を講じれば、過度に心配する必要はない。とはいえ、プロモーションの方法によっては事業者が意図せずうちにステマ規制に該当してしまうこともある。トラブルなく表示が出来るよう、佐藤弁護士のような精通している専門家に表示を定期的にチェックしてもらうと良いだろう。
中本総合法律事務所
https://nakamotopartners.com/
大阪で70年以上開業する老舗法律事務所。渉外案件を含む企業法務を中心に、離婚・相続問題や交通事故・労働問題など様々な事案を取り扱う。「迅速に価値ある法的サービスを提供する」という考えの基、クライアントの悩み事をスピーディーに解決する。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年11月08日
2024年11月08日





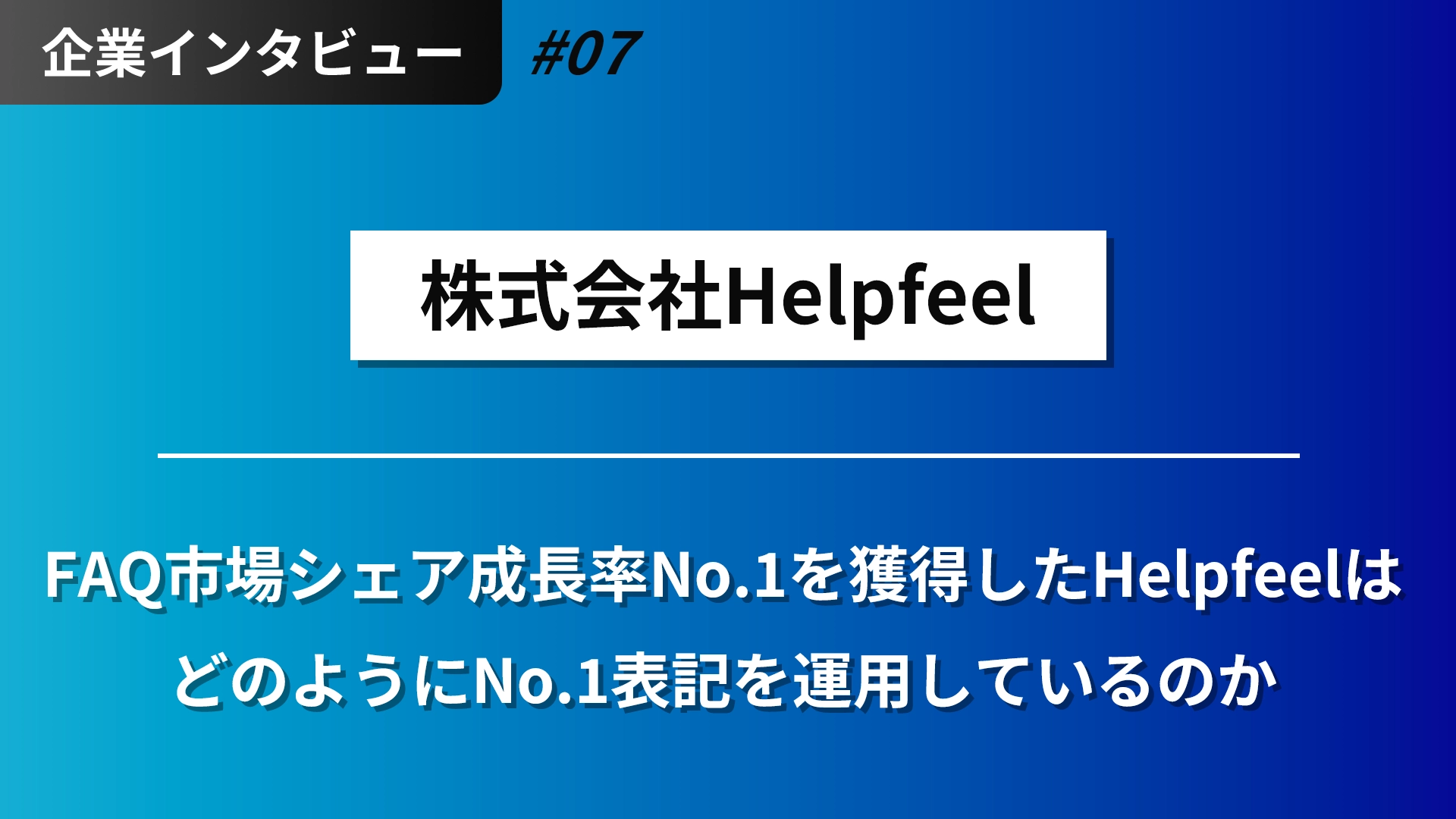

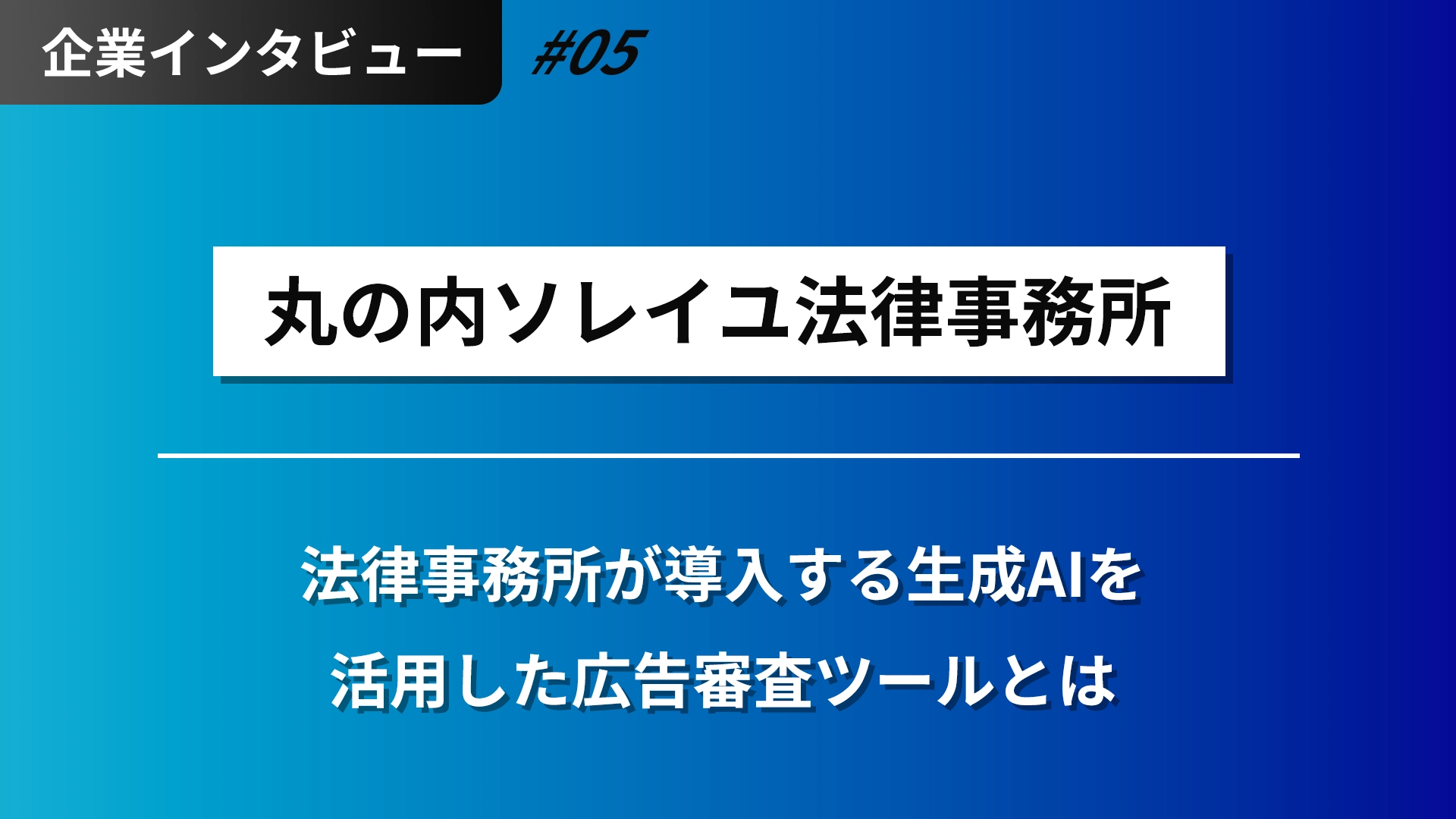
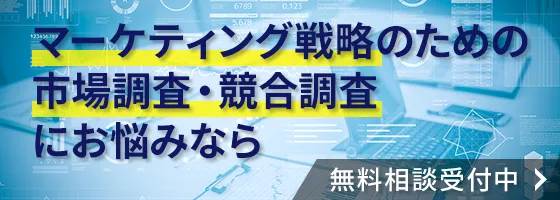
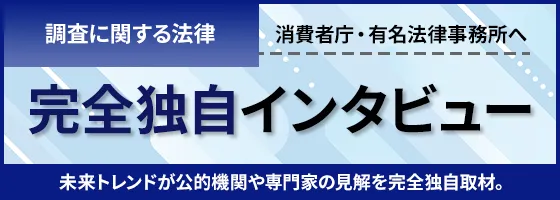
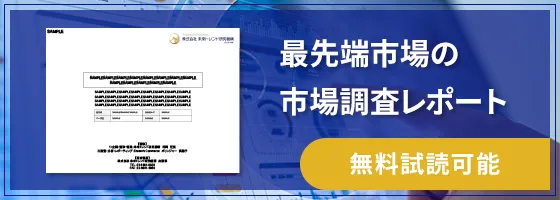


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com