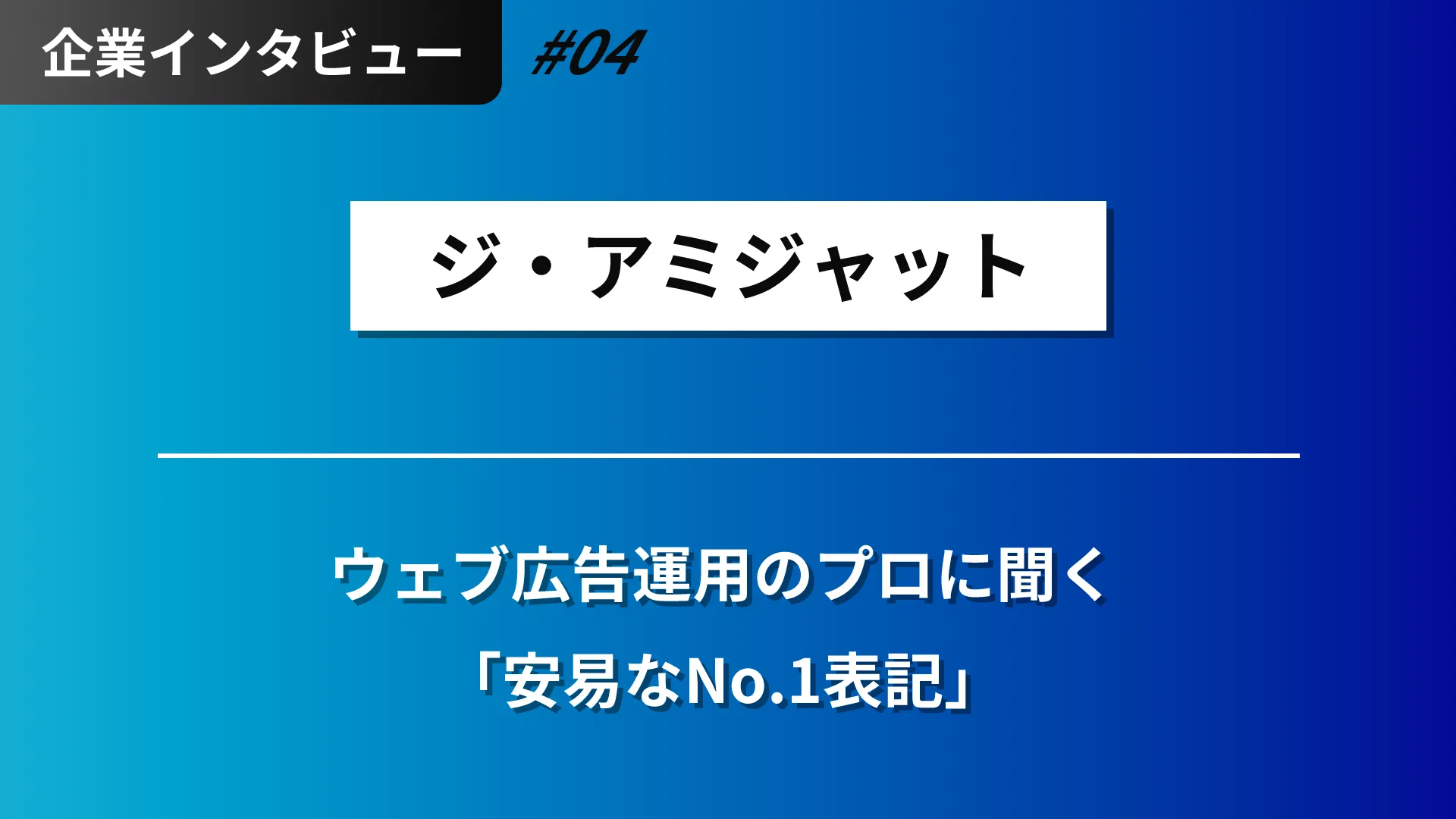
本インタビューは、No.1調査や世界初調査などで多くの実績を誇る未来トレンド研究機構が監修・実施しております。
新たなプロモーションを検討されている皆様のお力になれればと思い、各企業へNo.1表記などのPRに対する考え方や実際の効果など、ここにしかない情報をインタビュー形式でご紹介しております。
 2024年09月12日
2024年09月12日
 本文
本文事業者が作成したNo.1や初の表記を一般消費者の目に留まるようにする為には、インターネットの検索結果の上位にホームページを表示させる必要がある。SEOの専門業者やコンサルに依頼する、リスティング広告(検索連動型広告)を掲載するなど、様々なウェブ施策があるが、事業者にとって効果的な選択肢を精査しなければならない。その際、競合他社を真似て裏付けとなる根拠のないNo.1表記をすると、消費者庁の調査対象となる可能性も大いに懸念される。2024年9月26日に新たなNo.1表示に関する実態調査報告書が発表されたが、事業者への対策が従来よりも求められるようになった。
今回はリスティング広告などのウェブ広告運用に詳しいアミジャットの田島佑哉氏に「ウェブ広告の安易なNo.1表記のリスク」についてお話を伺った。

2013年よりウェブ広告運用に従事。
ウェブ広告代理店や弁護士事務所でのマーケター経験を経て、2017年にリスティング広告に特化したフリーランス「アミジャット」として活動を開始した。
Google 広告の正規代理店(Google Partners)、上級ウェブ解析士などの資格を持ち、リスティング広告の運用やインハウス支援と共に、アクセス解析やサイト改善のアドバイスも行う。
幅広い業種のウェブ広告運用を手掛け、特に士業(弁護士、税理士、司法書士)の案件を得意としている。
ウェブ広告業界でのNo.1や初表記の現状
消費者庁が「No.1」表記を措置命令の対象としたのは、消費者に誤解を与える根拠が不十分な表記が増えてしまった点にある。田島氏によれば「消費者も「No.1」や「初」の訴求を使ったウェブ広告に見慣れてしまっている」とのこと。ウェブ動画広告、ホームページなど、至るところで「No.1」という表記が目立つ。その中には何におけるNo.1なのかが理解出来ない表記も多い。
「Yahoo!広告では景品表示法に従った媒体審査が行われ、No.1表記についてはそもそも使用できない、または一定の基準を満たさないと掲載はできないというルールがあります。広告にNo.1のような最上表現を掲載した場合には広告審査が入り、審査に落ちれば広告は掲載停止となります。しかし、GoogleやFacebookなどのグローバルな広告媒体は、日本の景品表示法に合わせた広告審査になっていません。景品表示法に触れてしまう表現の広告でも、媒体の審査をすり抜けて表示できてしまうこともあります。」(田島氏)
事業者がNo.1の表記を掲載する際は、事前に「この表現に問題はないか?」を確認する必要があるだろう。
措置命令対象となってしまった事業者の失敗ケース
立て続けに措置命令対象となった事業者は、企業法務体制に問題があることをこれまで紹介してきた。ウェブ広告運用の従事者はこのような問題ある事業者をどのように見ているのか。田島氏は、次の2つの点で失敗をしてしまうケースが多いのではないかと推察する。
- ウェブ広告やホームページに安易なNo.1表現を使用してしまう
- 法令順守の意識が低いウェブ広告代理店やフリーランスに依頼してしまう。
事業者が陥りやすい失敗事例について、それぞれ具体的に解説頂いた。
安易なNo.1の危険性
安易なNo.1とは、根拠の無い調査結果を基に掲載している表記だ。田島氏はこの数ヶ月で問題あるNo.1のトレンドも少しずつ変化していると推察する。
「先日、消費者庁が「No.1表示に関する実態調査報告書(https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/survey)」を公開しました。私も景品表示法への意識が低い事業者ほど、自社のホームページやLPサイトに「No.1」という表記を謳い文句のように掲載しているケースが多いと感じます。以前はホームページやウェブ広告に「顧客満足度No.1」の表記が目立ちましたが、最近では「シェアNo.1」を表記する事業者が増えていると感じます。同じ業界なのに「シェアNo.1」を使う事業者が複数存在することも見かけます。」(田島氏)
実際にプレスリリースサイトで「シェアNo.1」で検索をすると、事業者が記事タイトルに「業界シェアNo.1の〇〇が」と掲載するケースが増えている。
「業界の売上データなど客観的な根拠となる資料の裏付けがあれば問題ない表記ですが、データや注釈も無く「シェアNo.1の〇〇」といった形で掲載する場合は注意が必要です。安易にNo.1表記を掲載する事業者が増加すれば、顧客満足度No.1の措置命令対象が増えたように、厳しい目でチェックされる表記になると考えています。」(田島氏)
消費者庁もNo.1実態調査報告書で警告しているように、安易なNo.1表記は措置命令対象となる可能性が高い。プレスリリース文に競合他社が「No.1」を表記しているので、類似表記を掲載しようと考えるのではなく、表記予定のNo.1が本当に問題ない表記かを精査するよう心がけるべきだ。
外部パートナーへ丸投げするリスク
No.1表記を適切に調査した場合でも、ウェブ広告運用を広告代理店やフリーランスなどの外部パートナーに委託する場合、事業者自身が適切に運用されているかセルフチェックをすべきとのこと。特に法令順守の意識が低い外部パートナーに運用を任せてしまうと、No.1表記の問題を知っていながら広告表現に使用しているケースもあるという。
「広告媒体によって審査基準が異なるため、審査基準がゆるい広告媒体を狙って景品表示法に触れるような広告を、利益重視で掲載してしまう外部パートナーも存在します。後から第三者指摘や媒体の再審査が入ると、広告は掲載できなくなることもありますが、それまでには広告掲載から数日間のタイムラグがあるため、この期間を狙う悪質な手法も出回っています。」(田島氏)
措置命令の対象期間は問題とされる表記が一般消費者の目に触れた時点から1日目として計算される。例え掲載期間が2、3日と短い期間であったとしても、調査対象としてチェックされることを認識しておく必要がある。
「アフィリエイト広告を利用する場合にも注意が必要です。GoogleやFacebookなどの広告は、個人でも広告を掲載することが可能です。もし、No.1表記に対する知識や問題意識がないアフィリエイターが利益を優先したら、景品表示法に触れてしまう広告を事業者の表記として掲載してしまうリスクが出てきます。」(田島氏)
No.1の表記の責任を負うのは事業者だ。アフィリエイターが独自の判断で景品表示法に触れる広告を掲載していたとしても、事業者が表記の問題を改善しなかったと判断される可能性がある。アフィリエイターが勝手に広告掲載をしたので我々も被害者であるといった言い訳は通用しないと覚えておくべきだ。
「適切なウェブ広告代理店であれば、お客様の知見に合わせて丁寧な説明を行います。お客様が最上級の表現を掲載したいと申し出ている場合は、最上級表記の取り扱ルールや、表記するために必要なことを説明します。何も説明しない状態で「No.1」を使った広告の掲載を勧めるウェブ広告代理店やフリーランスには注意が必要です。事業主が「この外部パートナーで問題ないか?」を判断して依頼することも重要です。」(田島氏)
広告法務が全く分からないので外部に全て丸投げするのではなく、事業者自身も広告法務に知見を得る必要がある。適切な運用を心掛ければ、適切な事業者の見極めも可能になるだろう。
最上級表現に頼らない表記も必要
No.1や初の表記は訴求力のある表記だが、適切な調査を実施しなければ措置命令対象となってしまい、事業者の信用度を下げるリスクもある。田島氏は選択肢の1つとして「No.1に頼らない広告」の選択肢も重要と説明する。
「そもそも広告とは、「魅力の無い商品やサービス(売れないモノ)を売る魔法」ではなく、「商品やサービスの魅力を、必要とする消費者に伝える手段」です。安易に作り上げた「No.1」や「初」の訴求に頼るのではなく、自社の商品やサービス自体の魅力や特徴を深掘り、ウェブ広告の訴求に活用していくことを推奨します。手法は「3C分析」や「SWOT分析」といった基本的なフレームワークを活用することから始めてください。また、既存顧客にインタビューを実施し、自社の商材やサービスを選んだ理由などをヒアリングして、広告の訴求に活用することも有効です。」(田島氏)
No.1や初が取れそうかを安易に判断するのではなく、自社の商品やサービスはどのような点において魅力があるのかを見つめ直すことも重要だ。No.1が見慣れている表現だからこそ、自社製品の魅力を伝える方法が別に無いかを探って見ると良いだろう。
まとめ
ウェブ広告運用を外部パートナーに依頼する場合、成果を出すことは前提条件として、景品表示法の視点から事業者にとってどのようなリスクが考えられるかを語れることも重要な選択基準だ。
景品表示法に精通していない外部パートナーにウェブ広告運用を依頼してしまうと、検索広告の上位表示の実現や、コンバージョンを多く獲得できたとしても、いずれ何らかのトラブルに発展することも考えられる。万が一の事態を回避するために出来ることは、事業者自身が知見を蓄積しておくことだ。幸いにもNo.1や初の表記は様々なガイドラインが適用されるため、理解を深めるだけで景品表示法の知識も蓄積できる。ウェブ広告の全てを外部パートナーに丸投げするのではなく、この機会に景品表示法について学び、外部パートナーと対等に話せる姿を目指しては如何だろうか。

アミジャット
https://amijat.work/service
「アミジャット」はGoogle認定(Google Partner)のリスティング広告代理店。リスティング広告運用に特化したフリーランスの田島佑哉が、Google広告やYahoo!広告の「リスティング広告・ディスプレイ広告・動画広告」などの運用、Google タグマネジャーの導入、Google アナリティクスによるアクセス解析を専任で対応。
他社では「少額案件」と雑に扱われてしまう広告予算でも、丁寧かつ成果を出すウェブ広告運用を行う。
 会社概要
会社概要| 社名 | アミジャット |
|---|---|
| 代表者氏名 | 田島佑哉 |
| インタビュー | 田島佑哉 |
| 事業概要 | ウェブ広告運用 |
| W E B サ イ ト | https://amijat.work/ |
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
その他の企業インタビュー
-
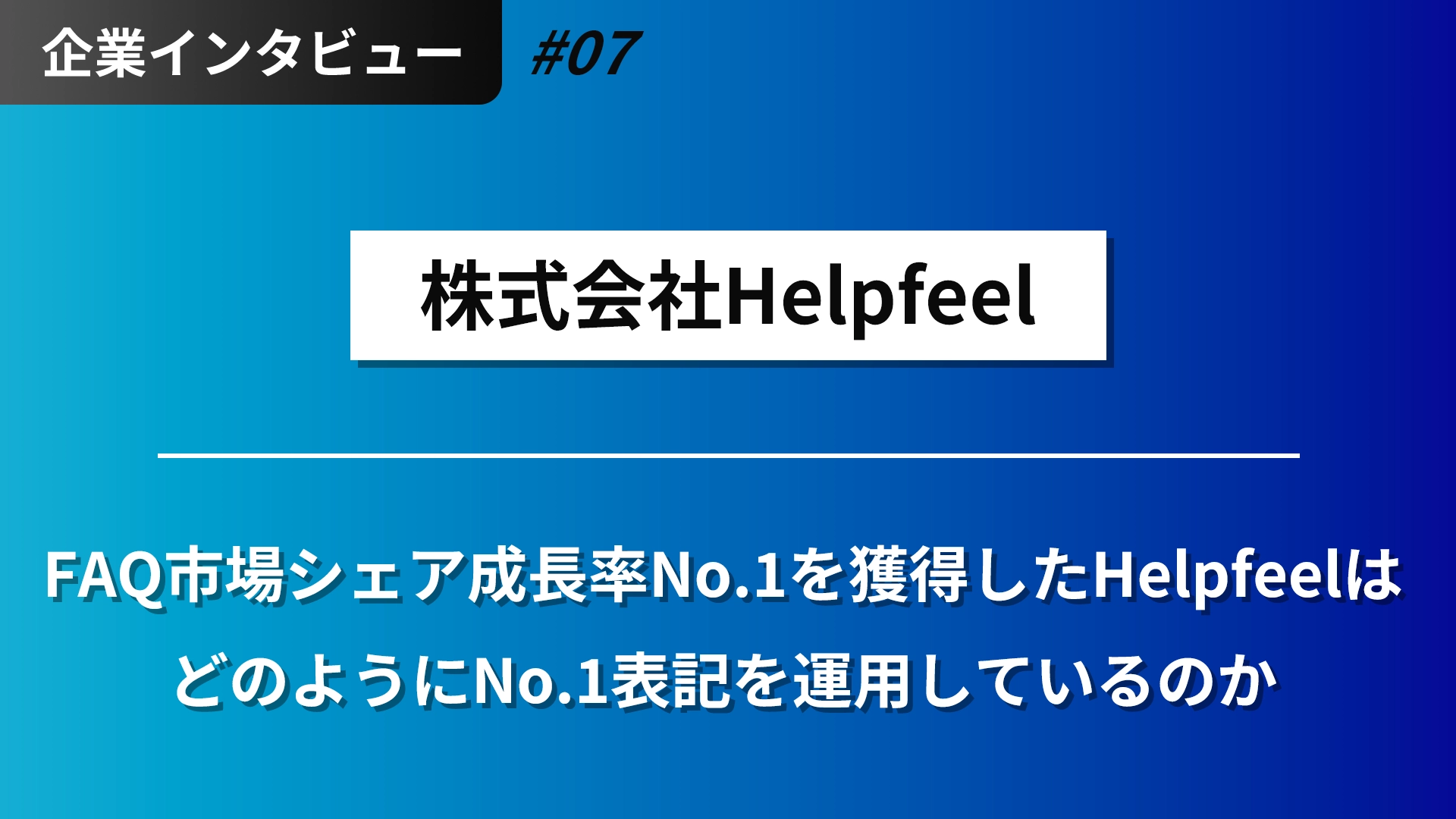 【株式会社Helpfeel】最新AI検索で最先端を走る企業のNo.1表記への考え方
【株式会社Helpfeel】最新AI検索で最先端を走る企業のNo.1表記への考え方 -
 【株式会社REGAL CORE】景表法対策 管理措置指針のヒント
【株式会社REGAL CORE】景表法対策 管理措置指針のヒント -
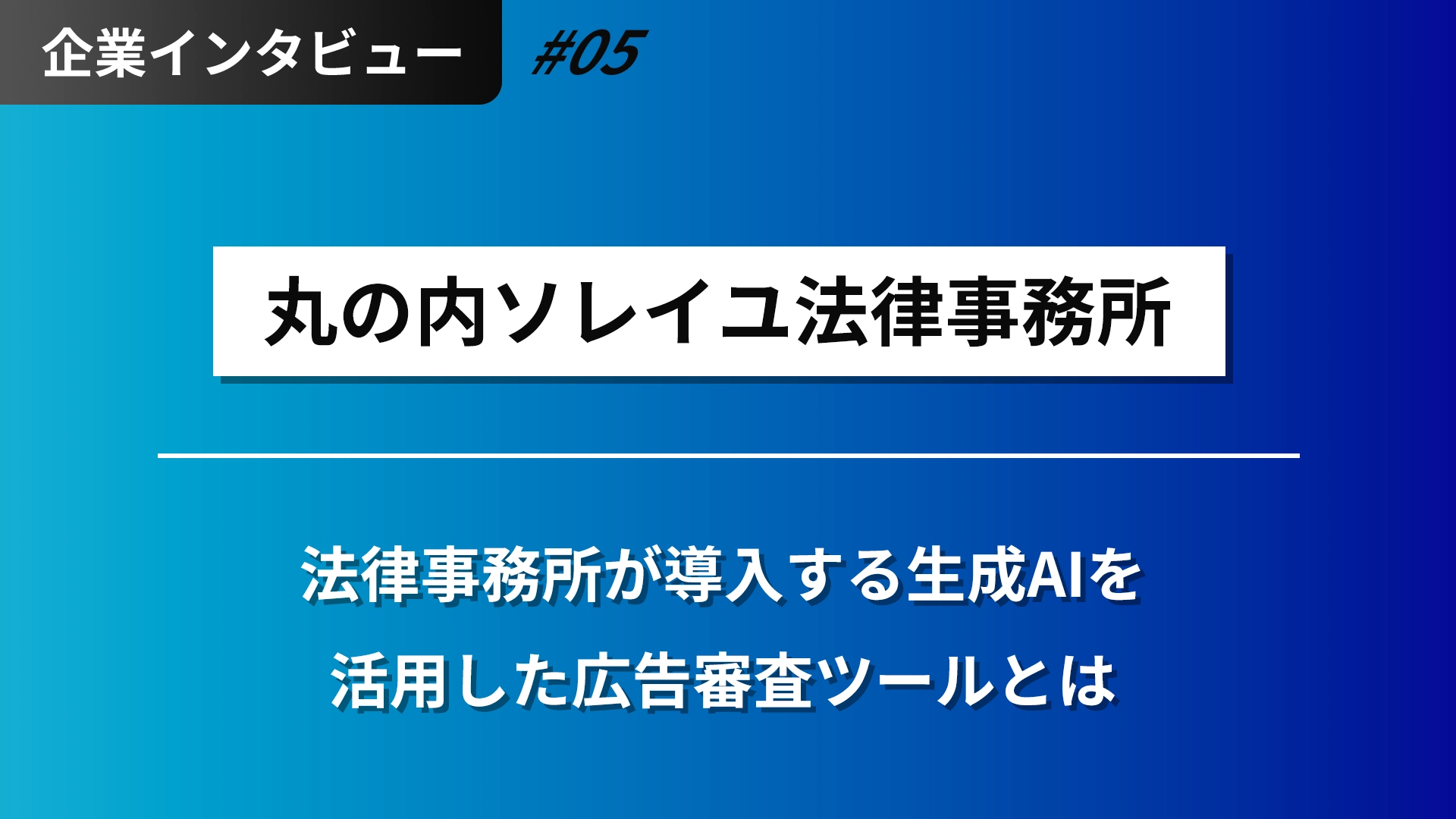 【丸の内ソレイユ法律事務所】広告審査AIツールの将来性と課題
【丸の内ソレイユ法律事務所】広告審査AIツールの将来性と課題

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com












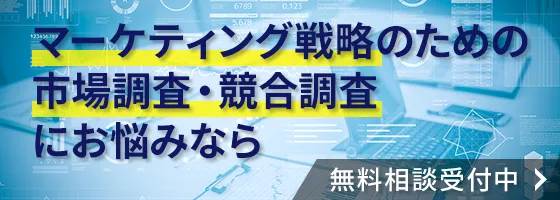
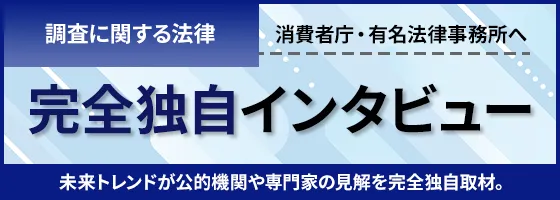
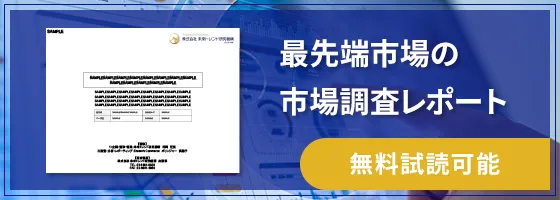


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com