
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
丸の内五番街法律事務所
辻󠄀本 奈保弁護士
つじもと なお
辻󠄀本奈保法律事務所
https://tsujimoto-nao-law.jp/
大手飲食事業会社と中央官庁で活躍した経験を活かし、クライアントのニーズに合わせたサポートが可能。
広告・表示(景品表示法、薬機法、食品表示法等)、飲食・食品事業関連に強みを持ち、事業者が抱えている問題に対し寄り添ったアドバイスを行う。
辻󠄀本奈保弁護士(東京弁護士会)
https://tsujimoto-nao-law.jp/
消費者庁調査官や大手企業での組織内弁護士の経験を活かし、辻󠄀本奈保法律事務所を開設。「クライアントのニーズに応え、期待を上回ること」をモットーに、事業者が納得する解決策を提案。
関連書籍
- 『景品表示法(第6版)』(共著、商事法務)(2021年6月)
- Thomson Reuters Practical Law Global “Employees: Cross-Border Private Acquisitions (Japan)” (共著)(2022年3月)
- 『労務管理のエキスパートガイド-事例でみる職場環境における配慮と問題行動への対処-』(共著、新日本法規出版)(2023年10月)
- 『遺言だけじゃない!?弁護士だからできる 生前の相続対策のすべて』(共著、第一法規)(2024年2月)
 本文
本文食品事業者のためのNo.1,初表記
事業者が掲載した広告やWEBサイトの表記が景品表示法(以下景表法)違反として措置命令の判断が下ると、課徴金納付命令が下る。参入ハードルが低い業種の中でも特に注意すべき業界が食品業界だ。食品に関係する事業者の表示したNo.1や初の表記を見た一般消費者が購入後に健康被害を起こしてしまった場合、事業者が問われる責任は大きい。
そこで食品業界でNo.1や初の表記を検討している事業者は、どのようなことに注意すべきか、消費者庁表示対策課食品表示対策室の調査官として活躍経験もある辻󠄀本弁護士に話を聞いた。
景表法を軽視してはいけない理由
No.1や初の表記は、一般消費者の購買行動に影響を与える魅力的な表記だ。消費者庁もNo.1表記の調査を重視するようになり、事業者が調査を実施したアンケート内容と表記内容が大きくかけ離れた場合措置命令対象として厳しくチェックするようになっている。
「これまでのNo.1表記の措置命令を見ていると、事業者のイメージダウンや課徴金納付命令など、事業者が被るペナルティは想定できました。しかし、食品の場合は別のリスクも考えなければなりません。健康食品に含まれた成分が原因で健康被害を引き起こすことがあります。その際には事業者が負うべきリスクは計り知れません」(辻󠄀本弁護士)
実際に今年の3月頃に大手製薬メーカーが開発したサプリメントの成分が健康被害を引き起こし、死亡との因果関係が疑われるという事例があった。この商品はNo.1表記とは関係ない商品だったが、仮に「No.1」と表記した食品で調査方法に問題があれば、事業者としての責任も大きくなってしまう。
「私のこれまでの経験では、措置命令や調査の対象となった事業者の多くが景表法や食品表示法に関する法律を軽視しているように感じました。特に食品の場合、健康被害を引き起こす可能性も考えられるので、事業者は関連の法律をきちんと知らなければなりません」(辻󠄀本弁護士)
ネット検索をしている事業者が「競合他社もこの表記をしているから大丈夫だ」と考えて掲載している場合、景表法違反等に該当してしまう恐れがある。適切な運用を実施するために事業者自身が独自にガイドラインを設ける必要がありそうだ。
表記で悩んだ時は業界団体へ意見を聞く
事業者が独自のガイドラインを作成する場合、業界ではどのような表記ルールが存在するのか、公正競争規約がある場合はそこに定められた内容をもとにガイドラインを作成すると良いだろう。業界団体が発表している公正競争規約には、表記してはいけない表示等が具体的に記載されている。公正競争規約はWEBからも確認出来る。
事業者が作成したガイドラインに沿って運用をしても、白か黒か判断できない表記も出てくるだろう。このような場合は有識者の意見が必要だ。
消費者庁には事前相談窓口があるので、ある程度意見を聞くことが出来るが、具体的な表示について白か黒かはっきりと解釈を教えてもらうことは難しい。
「消費者庁に問い合わせをする時は、事前にある程度知識がある方が具体的に質問できると思います。何も知らない状態で「このNo.1表記は適切ですか」と聞いても、意図した答えが返ってこない可能性があるため、事業者は具体的な情報をもとに問い合わせをした方が良いと思います」(辻󠄀本弁護士)
消費者庁に問い合わせをして解決出来れば良いが、聞き方と消費者庁の担当者次第なところもあるため、確実な方法と言えない。そこで推奨する方法が業界団体への問い合わせだ。
「公正競争規約を作成した業界団体であれば、具体的な表記のアドバイスを細かくしてもらえる可能性が高いと思います。通常は会員になる必要がありますが、事業者は安心して表記の相談が出来ると思います」(辻󠄀本弁護士)
業界団体は会費が発生するが、日頃から商品を開発し広告を出稿するような事業者であれば、担当者が知りたい情報を得ることが出来るだろう。
No.1ガイドラインの作り方
食品事業者がNo.1や初の表記に関するガイドラインを作成する際は、どのような手順で設定すべきか、辻󠄀本弁護士によれば、以下の3つのポイントが重要とのこと。
- 企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業等の各部門で連携を取る
- 原材料の資料を精査する
- 広告戦略をイメージしてNo.1表記を検討する
企画・設計・調達・生産・製造・加工・営業等の各部門で連携を取る
広告を客観的に評価する体制を構築する際に、社内全体で連携を取れるような体制を構築しておく必要がある。特に調達・生産・製造・加工部門は景品表示法に関する知識がないことも多く、事業者として重大なミスに気づかないケースもあると辻󠄀本弁護士は指摘する。
「事業者がやりがちなよくあるミスとして、原材料が調達や製造過程の都合で変わってしまうという事例があります。例えば、No.1調査を実施した際に使用した原材料が別の原材料に変わったことを営業部門に伝えないと、誤った表記を自然としてしまうことになってしまいます」
調達部門に景表法違反のリスクを説明していれば、原材料が変わったタイミングで広告担当者に伝え表記の改善が出来る。このようなうっかりミスを防ぐため、万が一表記と異なる製造が実施された時に、すぐに対応出来る仕組みをガイドラインに組み込んでおくと良いだろう。
そのためには、定期的に連携を取り掲載されている表記が正しいか、定期的にチェックをしておくことが良さそうだ。
原材料の資料を精査する
例えば、海外の原材料を使用している場合は、資料をより一層精査しておく必要もある。特に英語等外国語で作成された資料は解釈を誤るリスクがあるため注意が必要だ。
「外国語で書かれている資料は解釈を誤って捉えてしまうと、結果的に誤表記に繋がるようなケースも考えられます。原材料について外国語で記載された資料の場合は、外国語に精通している担当者を配置したり、外部の意見を確認するなど精査する仕組みを構築しておきましょう」
食品の場合、No.1の調査以外にも確認しておくべき項目が多い。事業者の製造予定の商品の場合、どの項目にチェックをすべきか考えておくと良いだろう。
広告戦略をイメージしてNo.1表記を検討する
No.1を表記する際は、調査を実施する前に広告戦略をイメージしておくことも重要と辻󠄀本弁護士は考える。
「広告戦略を最初からある程度イメージしていれば、どのようなNo.1や初であれば効果的であるかをある程度イメージできます。もちろん広告担当者が全てを知る必要はありませんが、やりすぎた広告は罰則の対象となることくらいの認識は持っておくと良いと思います」(辻󠄀本弁護士)
一定の知識があれば、商品開発の段階でNo.1表記や初表記が実現できる商品かどうかを精査することも可能だ。
消費者がどう見るかで判断を
適切なガイドラインを作り、No.1表記に必要な調査を適切に実施したとしても、消費者庁からの調査が入ってしまうこともある。
「景品表示法は過去の最高裁まで争った措置命令のように、広告を見た印象で判断されるものです。いくらNo.1が正しい調査過程でそう言えるとしても、消費者の目にどう映るかが重要です。その点も表記をする際にチェックする必要があることを覚えておきましょう」(辻󠄀本弁護士)
No.1や初の表記を消費者が目にしたら、事業者が意図しない方向で「この商品はきっと優れている商品に違いない」と判断してしまう可能性がある。事業者がホームページや広告を作成した際に少しでも違和感を感じた表記は「消費者はどう感じるか」という視点が重要となりそうだ。もちろん法律的な視点での意見が必要な場合は、辻󠄀本弁護士をはじめとする食品関連に精通した弁護士と連携しておく事を推奨する。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年07月23日
2024年07月23日


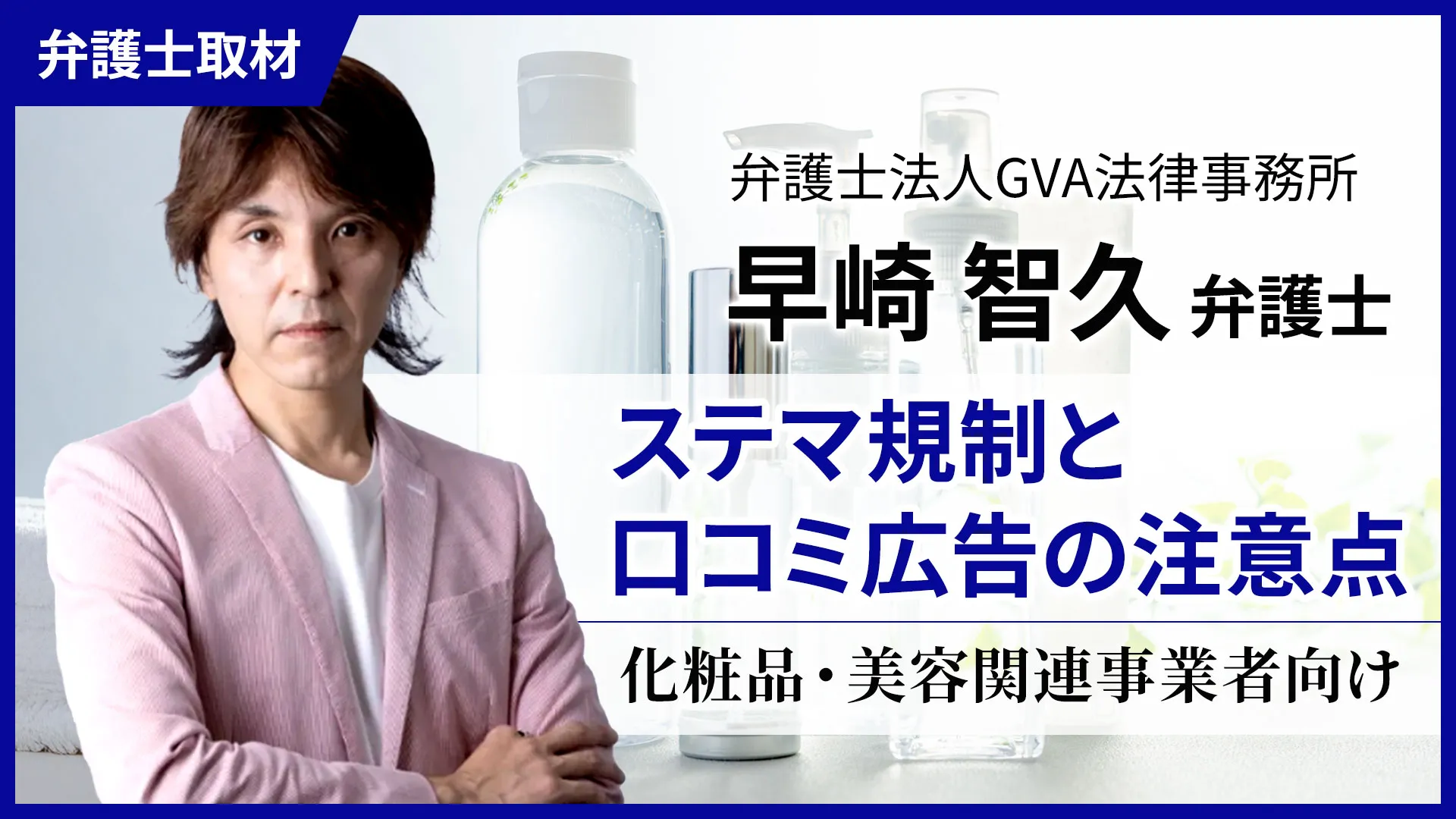
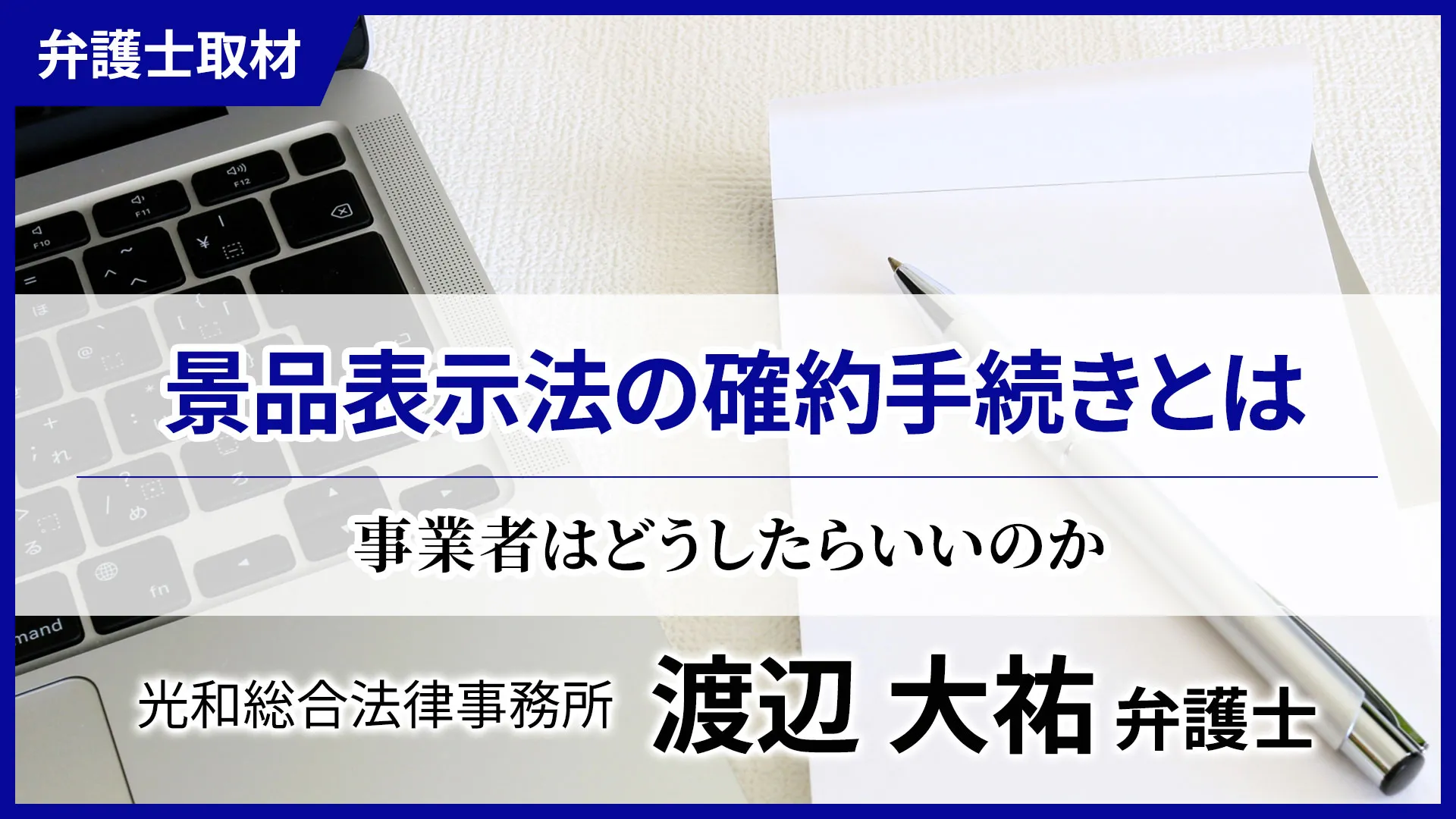




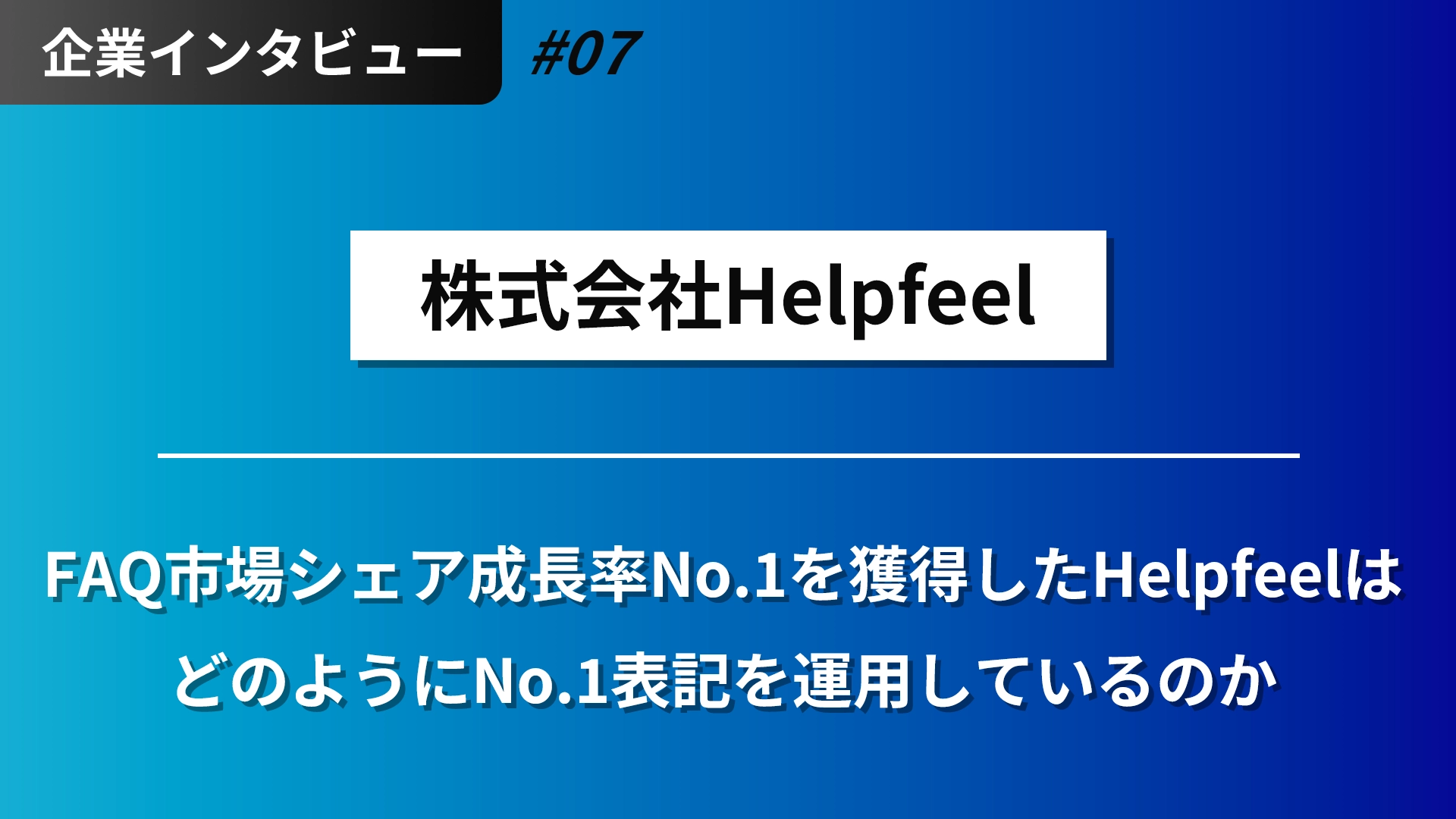

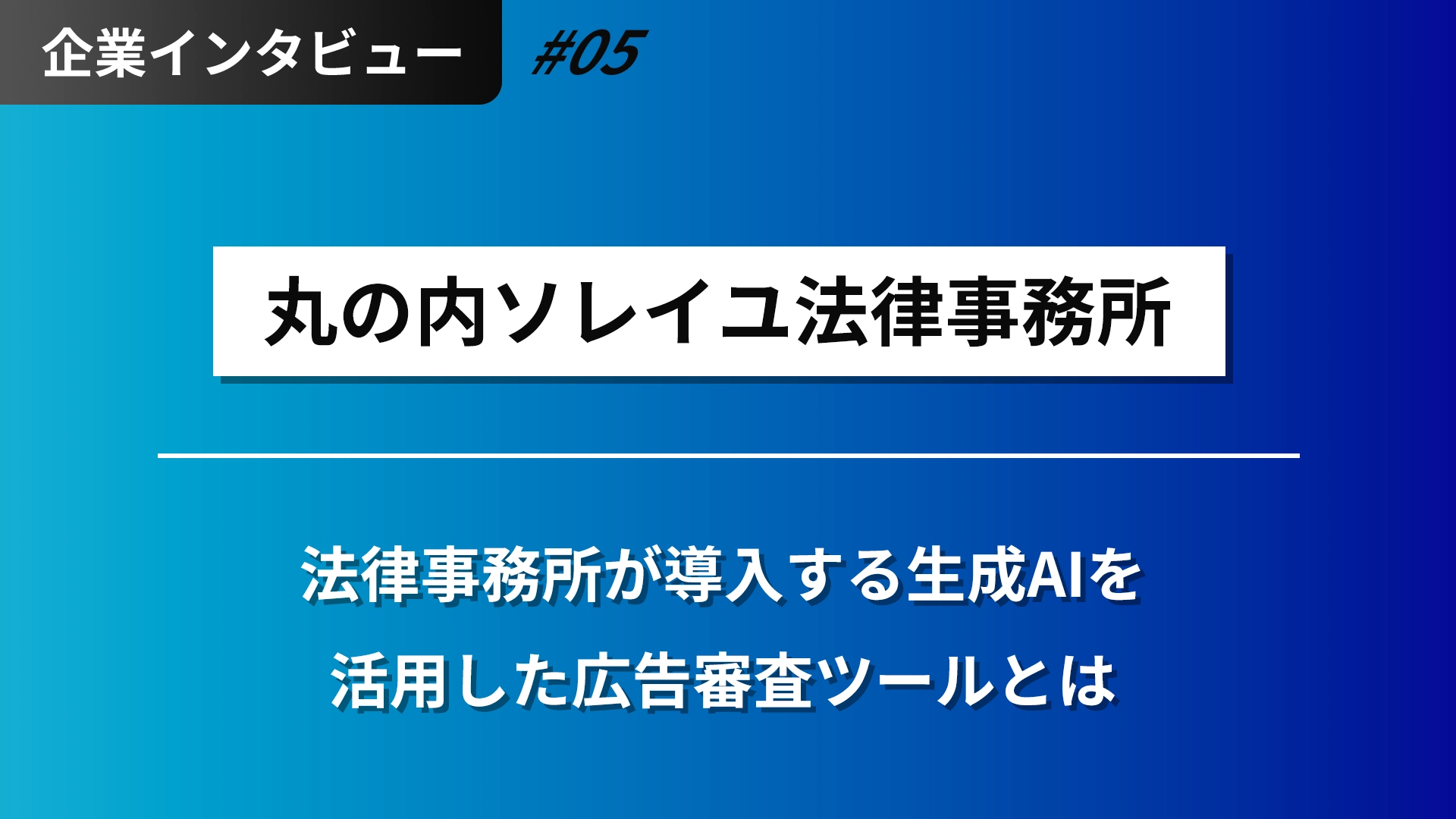
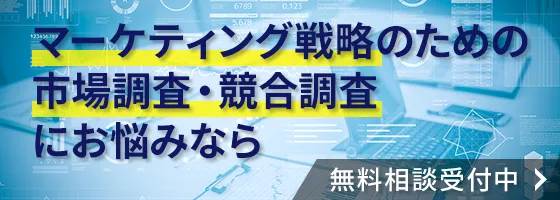
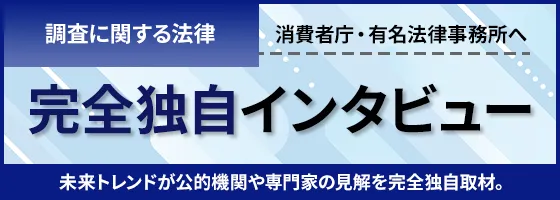
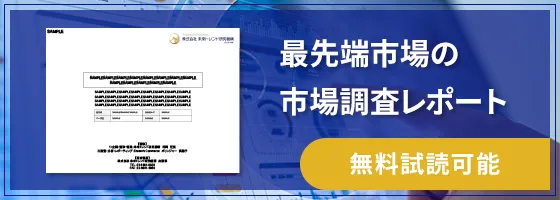


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com