
2023年6月14日に発表された株式会社バウムクーヘンの景品表示法(以下景表法)に基づく措置命令をきっかけに、事業者に対するNo.1表記へのチェックが厳しくなった。No.1調査時に事業者が最低限持つべき視点について、続けて吉原綜合法律事務所の吉原弁護士にお話を伺った。
No.1調査時に注意すべきこと
No.1表記を検討している事業者は、No.1調査前と調査後に注意すべきことがある。それぞれの注意点を意識して対策を実施することで、競合他社の事業者から指摘を受けにくくなる可能性が高い。具体的にどのような対策をすべきか、それぞれ紹介する。
競合他社から指摘を受けないようにするためにできること
No.1表記では公平な調査結果が裏付け資料の根拠となる。裏付け資料が実際に掲載されている表示と大きなずれが生じていると、問題ある表記として他の事業者から指摘される可能性が高い。
「No.1調査を実施する際、公平性のある調査が求められます。調査を行う過程で公平に行われているかどうか分からない場合は、調査前に、その調査が公平と言えるかを弁護士に尋ねてみても良いかと思います」(吉原弁護士)
No.1の調査を実施する際に注意すべきポイントは、一般消費者ではなく、事業者が消費者庁へ通報をして調査を開始する可能性があると捉えるべきだと吉原弁護士は言う。
「一般にNo.1表記は競争関係にある他社と業界内比較をして、自社の製品やサービスが優れていることを訴求するものです。その表記で顧客満足度、相談しやすさといったことをNo.1として表記するとすれば、そのような事実があることを証明しなければなりません。
そのためには自社のサービスだけでなく、他社の類似したサービスをすべて利用したことのある対象者にアンケートを実施しなければ、その業界においてNo.1であると証明する資料としては不十分です。その点を注意して調査を行う必要があります」(吉原弁護士)
消費者庁が2023年度に立て続けに行なってきたNo.1表記の措置命令を確認していくと、客観的な事実と異なる調査結果をあたかも「No.1」として表記したものが措置命令対象となっている。注意すべきは、明らかな虚偽というよりも「客観的な調査」というには不十分と判断された結果、客観的な調査結果に基づかないと消費者庁が判断しているという点である。適切なNo.1表記を目指すために出来ることは、競合他社から指摘が入らないよう対象者を慎重に選定しておくことが重要だ。
調査後に意識すべきこと
適切な調査方法を実施し、No.1表記が掲載可能となった場合でも、その後の広告で指摘を受けることもある。具体的にどのような注意点が必要かについて解説する。
掲載した広告はいつ指摘が入るか分からないと捉えておく
調査結果を元に作成した表記が、いき過ぎた表現になってしまい一般消費者へ誤解を与えてしまうケースもある。広告を掲載する前の最終チェックの段階で問題となる表現を発見出来れば良いが、見落としてしまうこともある。掲載後に問題のある表記を掲載してしまった場合は、たとえ1日のみだとしても指摘を受けるかもしれないと考えておくと良い。
「過去の事例を見ると、たった3日間掲載した表記が問題のある表記として指摘を受けたものがありました。掲載期間がたった3日間だけなのですが、掲載した表記自体が不当表示に該当する表記をしていたので、措置命令対象となっていました。掲載期間がたった1日だけだとしても、消費者庁へ指摘をする事業者や一般消費者がいれば調査対象になることは十分考えられます」(吉原弁護士)
今掲載している表記の全てに対し消費者庁がお墨付きを与えた表記ではないことも認識しておくことが重要だ。特に、吉原弁護士は、実務では「他の会社もやっている」ということで、他社表記を真似た表記をしようとする事業者がいるが、それも注意が必要だと指摘する。
「例えば事業者が競合他社の表記を真似して掲載をしてから、他社の表記に措置命令対象となった場合、その後真似していた事業者も措置命令対象となる可能性が十分考えられます。調査対象となり消費者庁に説明をする際「他社がやっていたので問題なかった」という言い訳は通用しません。措置命令になる可能性が高くなってしまうので注意が必要です」(吉原弁護士)
事業者は自社で制作した広告を掲載されたタイミングから、いつ指摘が入ってもおかしくないということを念頭に入れて、自社の対策を検討しておくとよさそうだ。
打ち消し表示の記載方法に注意
広告に打ち消し表記を用いる場合もある。No.1の表記が問題ない場合でも「これは個人の感想です」といった打ち消し表示の方法に問題があれば、指摘が入る可能性も考えられると吉原弁護士は指摘する。
「打ち消し表示については事業者の中でも「この表記していれば問題ないでしょ」という誤った認識がまだまだあると思います。一般消費者が誤認しないように書くのが打ち消し表示であって、「個人の感想です」を書いても通常気付かなければ打消し表示になりません。更には何を表記しても許される訳ではありません」(吉原弁護士)
健康食品をはじめとした薬機法関連の商品では、打ち消し表示を用いて訴求をすることが多い。No.1が適切な場合でも、他の表記が問題と捉え徹底的に調査を行われてしまうことも考えられるため注意が必要だ。
調査資料の保管方法
マーケティングにおいては、保守的過ぎると消費者は退屈であり、他方で景表法では法律遵守の壁も低くない。そこで、表記を適切に運用するだけでなく、No.1を調査した際の資料をどのような形で保管するかも重要だ。
「表記の時点で客観的資料があることは制度上も前提とされています。消費者に対する訴求力が強い表記ほど、目立つので、消費者庁による調査対象にも挙がりやすいです。万が一に調査が入ったときに備えて、予め広告表記と資料を紐付けして保管しておくことで、調査が入った時にどのような過程でこの表記に至ったのかをスムーズに示すことが出来ますし、事業上の不安を軽減できます。そのための社内での取扱いを定めるガイドラインを作る際は、表記に至るまでの過程(資料に基づく根拠)をただ示すのではなく措置命令の公表例をもとに合理的な説明内容を事前に準備し、更には万が一調査が入った時に事業者がどのような形で動くのかも決めておくと安心でしょう」(吉原弁護士)
万が一調査が入った時に誠実に対応できるよう、裏付けとなる根拠を保管しておくと良いだろう。
まとめ
No.1表記を運用する事業者は調査前、調査過程、調査後の3段階で対策を検討しなければならないことが理解できた。調査過程をガイドラインに沿って問題なく行ったとしても、広告として掲載する表記に問題があれば、指摘が入ることも十分考えられる。
専門家から見て、事業者の表記を実現するためにどのような対策が必要そうか、ガイドラインを作成する際に専門家の意見を聞いてみると、事業者毎に適切な対策とは何かが見えてくるだろう。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年07月31日
2024年07月31日





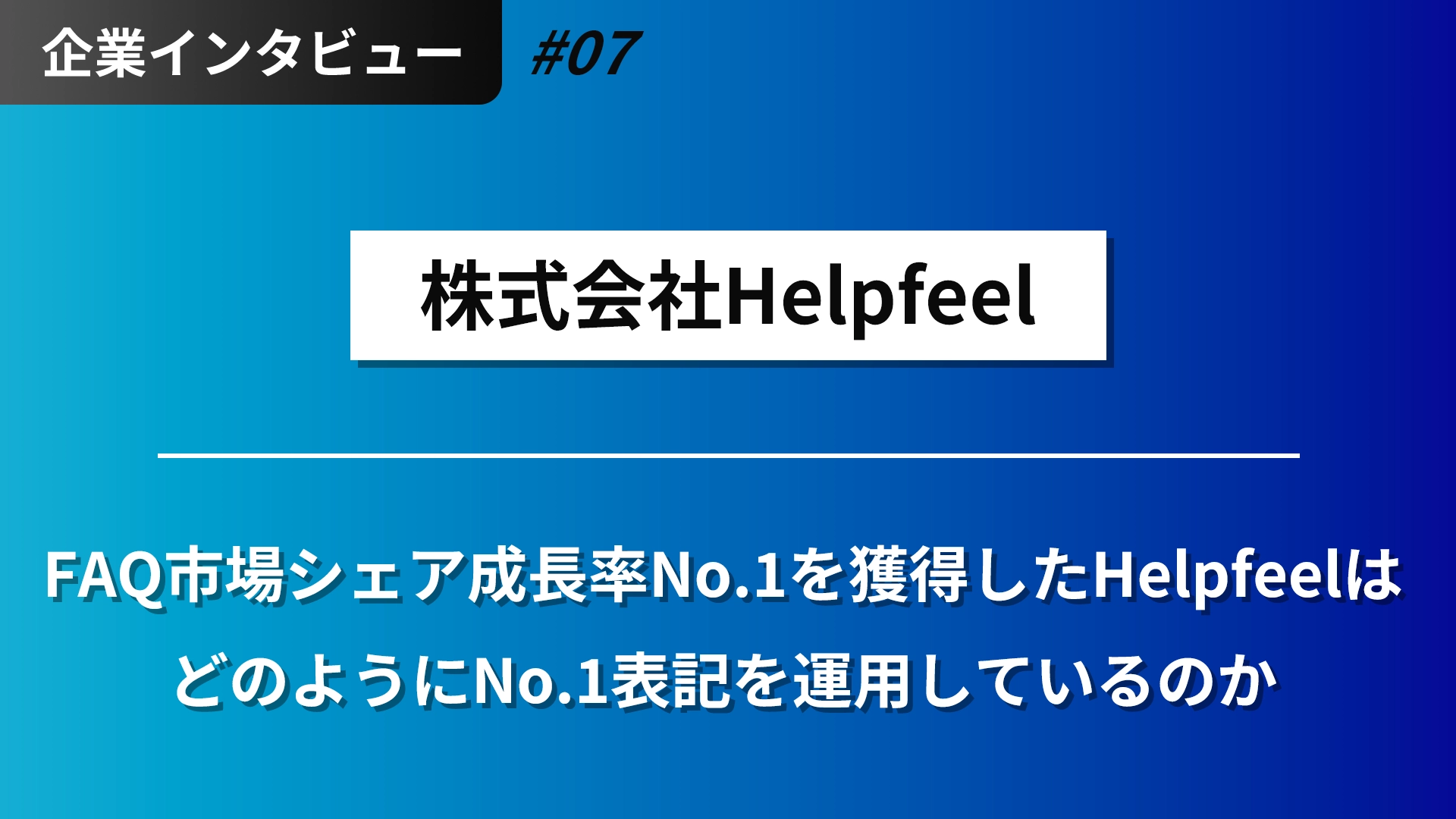

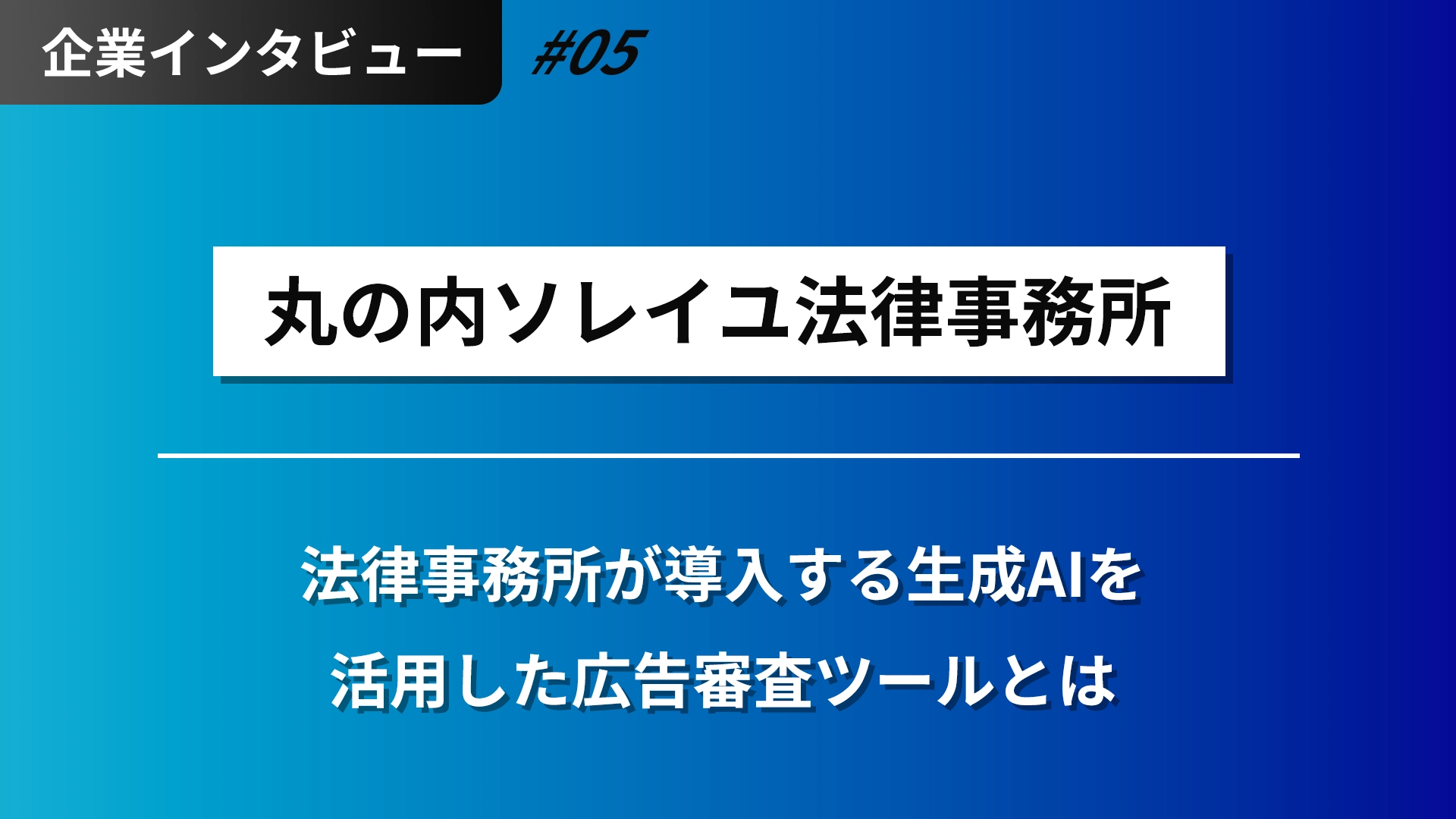
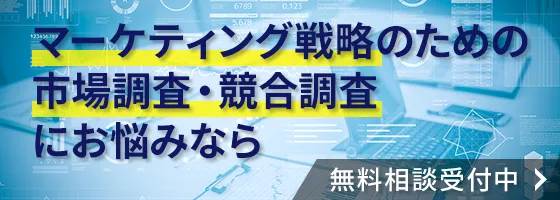
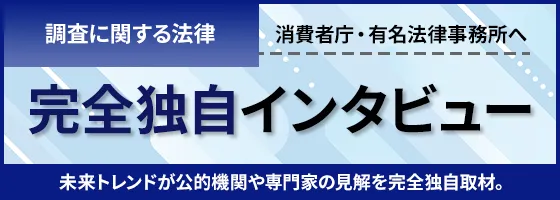
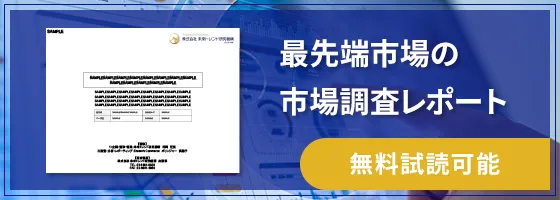


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com