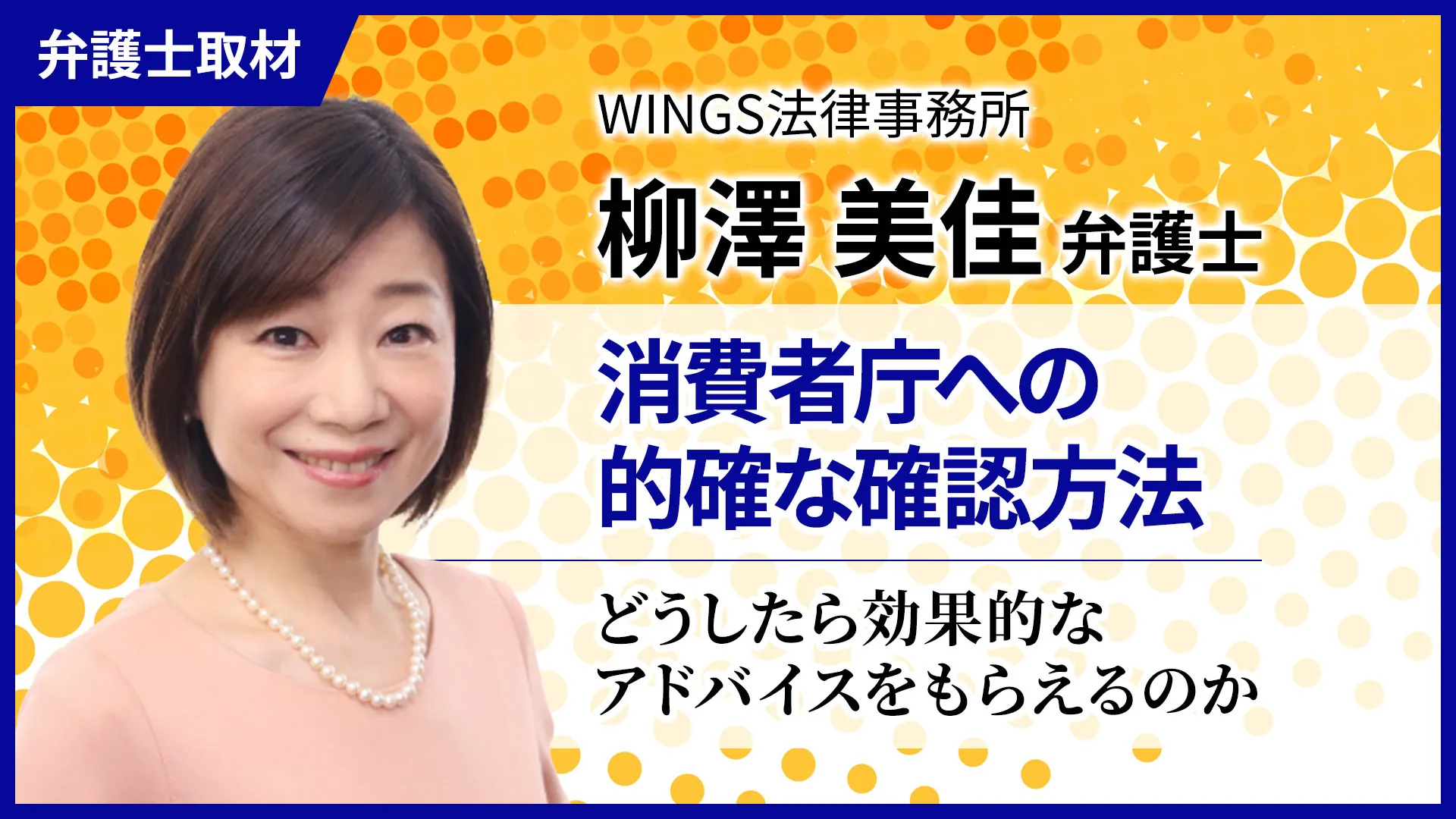
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
WINGS 法律事務所
柳澤 美佳 弁護士
やなぎさわ みか
WINGS 法律事務所
https://wings-law.net/message/
柳澤弁護士が「正義の実現」を目指してWINGS法律事務所を設立。
ビジネス法務の現場で培った経験を活かし、様々な事業者の問題を解決する。
「景品表示法の基礎を踏まえた委縮しない広告制作と広告チェック体制構築のポイント」や、「女子中高生向けキャリア講座『弁護士という生き方』など、多岐に渡るセミナー講師を担当する。
2月末にも景品表示法セミナーを開催予定(セミナー概要はこちら)。
柳澤美佳弁護士
https://wings-law.net/message/
10年の商社勤務を経て2006年より弁護士として活動。
2社でのインハウス弁護士として活躍した経験を持つ。
「正義の実現の一翼を担う」をモットーに、ビジネス法務の現場で培った経験を活かし、事業者に寄り添った最適なアドバイスを提供する。
2月末にも景品表示法セミナーを開催予定(セミナー概要はこちら)。
 本文
本文「消費者庁の問い合わせは「質問力」で決まる〜おすすめの質問方法」
No.1表記や初表記として掲載して問題ないかどうか、迷った時は消費者庁へ問い合わせをすると良い。
これは、景品表示法(以下 景表法)に精通している有識者でも判断が難しい場合に提案される解決策だ。消費者庁 景品表示対策課へ問い合わせをしても、「景表法をはじめとした表記の解釈を伝える場であり、具体的な表記についての回答は出来ません」と説明されるケースがある。回答が得られなかったため、諦めてそのまま表記を決断する事業者がいるかもしれないが、根気よく問い合わせをすれば回答やヒントを得られることもある。
今回は消費者庁への効果的なアドバイスを求めるアプローチを知るため、インハウス弁護士として広告法務の最前線で活躍した経験を活かし、景表法や消費者庁への対応を得意としているWINGS法律事務所代表柳澤美佳弁護士にお話を伺った。
消費者庁の温度感に敏感になる!公正競争規約も上手に利用しよう
消費者庁への質問を実施する前に、消費者庁が現在何に対し関心を強く持っているのか「消費者庁の温度感」を把握しておかなければならない。
「例えば、去年、一昨年とNo.1表記に関する措置命令が多く、本年も既に多くの措置命令が出されており、No.1表記は消費者庁が力を入れて摘発している分野だと理解する必要があります。最近の事例であれば、「満足度No.1」と謳っているにも関わらず、利用者に満足度についてアンケートを実施した調査結果ではなく、非利用者による“サイトの印象”のアンケート結果に基づく「No.1」でした。このような客観的な調査結果に基づいているとはいえないNo.1表記は消費者庁から指摘対象となる事例と言えるでしょう」(柳澤弁護士)
事業者自身がこの表記は黒なのか判断つかない場合でも、過去の措置命令で取り上げられている表記と類似していれば、消費者庁の調査対象となるかもしれないと考えておくと良いだろう。
「措置命令だけでなく、各業界の定める公正競争規約にNo.1表記をはじめ、『この表記はしてはいけない』という基準が細かく記載されています。公正競争規約に参加していない企業様でも、いわば消費者庁のお墨付き基準といえる公正競争規約も参考にして社内ガイドラインの作成や表記の判断をすると良いと思います」(柳澤弁護士)
景表法に精通している弁護士に聞けばグレーゾーンの表記を判断出来るかもしれないが、コストをかけられない事業者は、過去の措置命令や公正競争規約を見て判断し、それでも分からない時に、消費者庁へ問い合わせをすることで解決策を見つけられるかもしれない。
消費者庁問い合わせ時に意識すべき3つのポイント
ここからは消費者庁に実際に問い合わせをする際に、事業者が意識すべきポイントを紹介する。3つのポイントを意識しておくと良いだろう。
- 根気よく問い合わせる
- 匿名で商品名を変えるなどして、ガイドラインに沿った質問を
- 消費者庁の意見は絶対ではない
根気よく問い合わせる
大前提として、消費者庁へ1度問い合わせをしただけで答えを得られる訳ではないと考えておくことだ。
「消費者庁の担当者は、具体的な事例には回答しない方も多いと思いますが、なるべく事業者に寄り添って対応をしようとされる担当者もいます。一回の問い合わせであきらめずに、丁寧な対応をしてもらえる担当者に当たるまで、根気良く続けてみてはいかがでしょうか。」(柳澤弁護士)
消費者庁の事前相談担当者は複数名在籍している。対応に満足出来なければ、時間帯を変えて問い合わせをしてみるのも手だろう。
「法律的な解釈に変えて問い合わせをすることもできますが、時折問い合わせ中にポロッと本音をいうこともあります。あくまで担当者の感想のようなものでも事業者にとっては大きなヒントになる可能性もあるので、担当者の感想を聞き出すのも良いと思います」(柳澤弁護士)
アナログな方法ではあるが、根気よく問い合わせをすることで求めている回答や何らかのヒントを得られるかもしれない。
匿名で商品名を変えてガイドラインに沿った質問を
問い合わせをする際は、事業者名や商品名を出すべきか迷うこともあるだろう。そのような場合は匿名かつ商品名を変えて質問をしてみると良いだろう。
「掃除機を商品として売り出そうとしている事業者が扇風機などに変えて、「この表記を掲載したいと思うのですが、問題ないでしょうか」と聞くと、実際の商品の表記に役立つ回答やヒントを引き出せることもあります」(柳澤弁護士)
類似した商品で問い合わせることで、そのジャンルの表記に対しどこを問題視しているのかを判断できる。さらに開発段階であれば、一般的な解釈や感想を聞き出すことができるかもしれない。また可能であれば、「このNo.1表記はどうですか」という聞き方ではなく、「これは、不実証広告ガイドラインに書いてあるこの解釈に該当する表記でしょうか」といった形で、具体的に聞くと良いだろう。
抽象的すぎる質問は消費者庁の担当者も一般論しか語ることが出来ない。ある程度事業者が法的解釈を理解した上で問い合わせをすることが望ましい。
消費者庁の意見は絶対ではない
問い合わせ時に理想的な回答を得られたとしても、「消費者庁のお墨付き」ではないことを事業者は理解しておかなければならない。
「問い合わせをした時に「問題ない」と消費者庁の担当者に言われたとしても、当該表記は絶対に問題ないという訳ではありません。違法な表示になるかは実際の表記全体についての消費者の印象と根拠が合致しているかから判断されるもので、電話による断片的な情報では具体的な判断はできませんし、消費者庁はお墨付きを与える役所でもありません。あくまで消費者庁の一担当者の見解を参考程度に聞いていることを忘れないようにしてください」(柳澤弁護士)
景表法の最も重要となる要素は、一般消費者がどのように受け止めたかという点だ。問い合わせは電話で行うため、説明した内容が消費者庁担当者にうまく伝わっていないことも考えられる。消費者庁の回答は絶対ではないことを理解して、問い合わせをすると良いだろう。
メインコピー・キャッチコピーは厳しいチェックを
事業者は一つの商品について、複数の広告表記を作成すると思うが、消費者庁への問い合わせだけではなく、是非とも有識者に評価してもらった方が良い表記がある。それは事業者が該当商品のメインコピーに据えるいわゆるキャッチコピーだ。No.1や初の表記もシンプルかつキャッチーな形で一般消費者に魅力を訴求できる。消費者が最も目につく場所だからこそ、消費者庁への指摘も入りやすく対策を実施しなければならない。
「いわゆるメインコピーなど根幹となる表記は、消費者にアピールできる反面、消費者庁にも狙われやすい表記と言えますので、予算をつけて有識者に評価してもらうのが良いと思います。表記を5段階評価してもらうなど、予算に合わせた形で評価を依頼することも可能ですので、重要な表記は弁護士などの第三者に評価してもらうべきだと思います。効果的な打消し表示の提案などを受けることができるかもしれません。」(柳澤弁護士)
キャッチコピーは目につきやすくシンプルな表記であるからこそ、一般消費者が打ち消し表示を見落としてしまう可能性も高い。だからこそ指摘が入らないように有識者への精査が必要なのだ。
景表法を正しく恐れて対応を
景表法はシンプルな法律でありながら、事業者にとってペナルティが重い法律だ。だからこそ、事業者は正しく理解しておく必要があると柳澤弁護士は考える。
「景表法は比較的マニアックな領域と誤解され事業者が軽視してしまう傾向がありますが、ペナルティが重く事業者にとり重要な法律だと考えなければなりません。違反すれば措置命令、課徴金納付命令があり、事業者の信用失墜にも繋がるからです」(柳澤弁護士)
実際に事業者が景表法を軽視した結果、景表法違反に該当し多額の課徴金納付命令が下った事例もある。一方、景表法を過剰に意識し過ぎると広告が魅力的では無くなってしまうという問題もあり、事業者はジレンマと抱えているだろう。
「あまり警戒しすぎると広告として魅力的な表記が出来なくなってしまう恐れがあります。景表法のポイントは「著しく優良または有利と見せかける」ことが問題であって、適切かつ魅力的な表記を実現するには、景表法を正しく理解することが大切です」(柳澤弁護士)
どのような表記が“著しく”優良または有利もので、そうでないものか、それに沿ったガイドラインはどのようにすれば良いか、まだまだ知らなければならないことがある。次章では柳澤弁護士が考える「理想の法務体制」や「事業者が知るべき行政対応の考え方」について解説する。改正景表法を機にこれから企業法務を強化しようと検討している事業者は、ぜひ次章も参考にして欲しい。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年07月22日
2024年07月22日





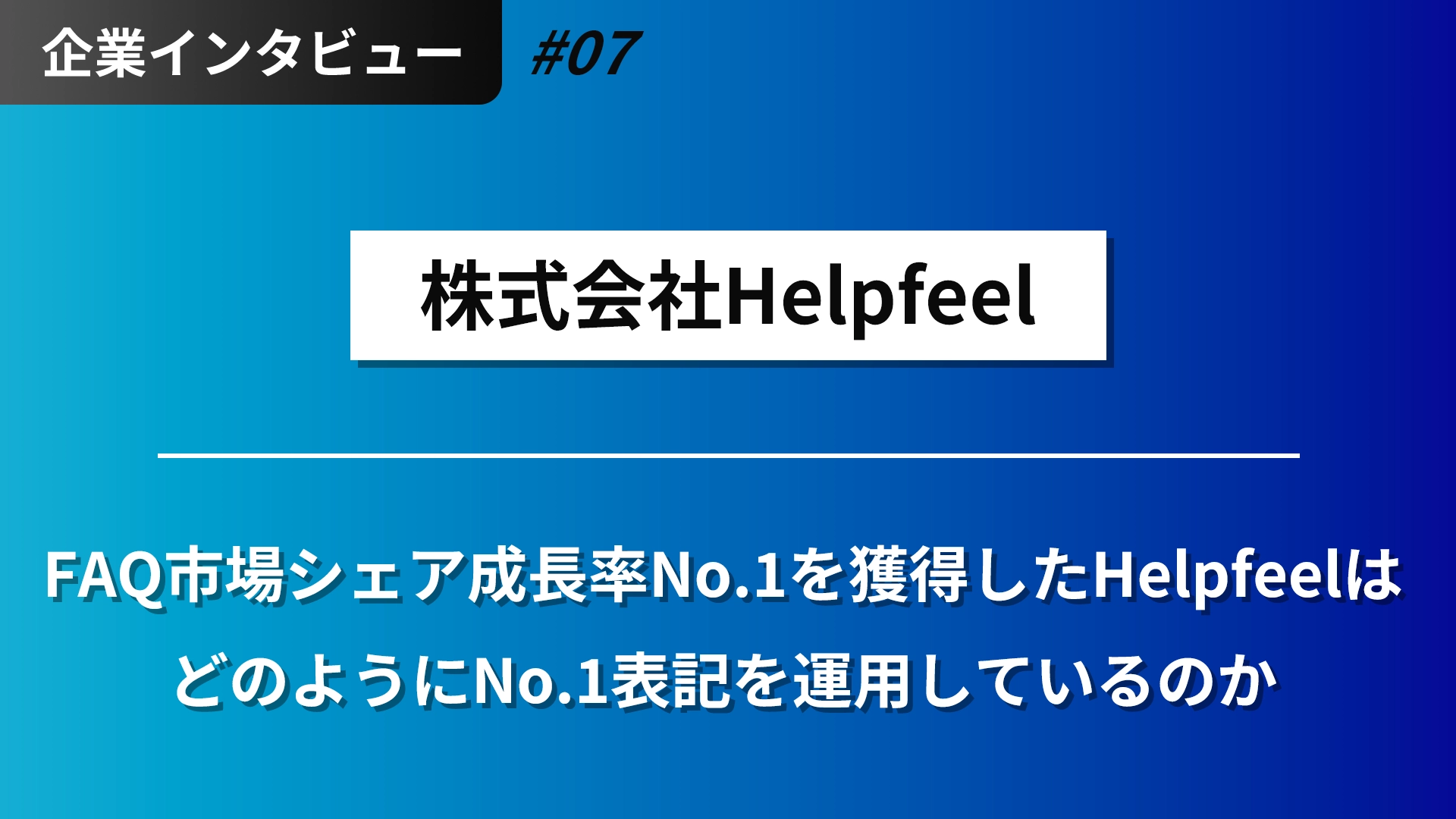

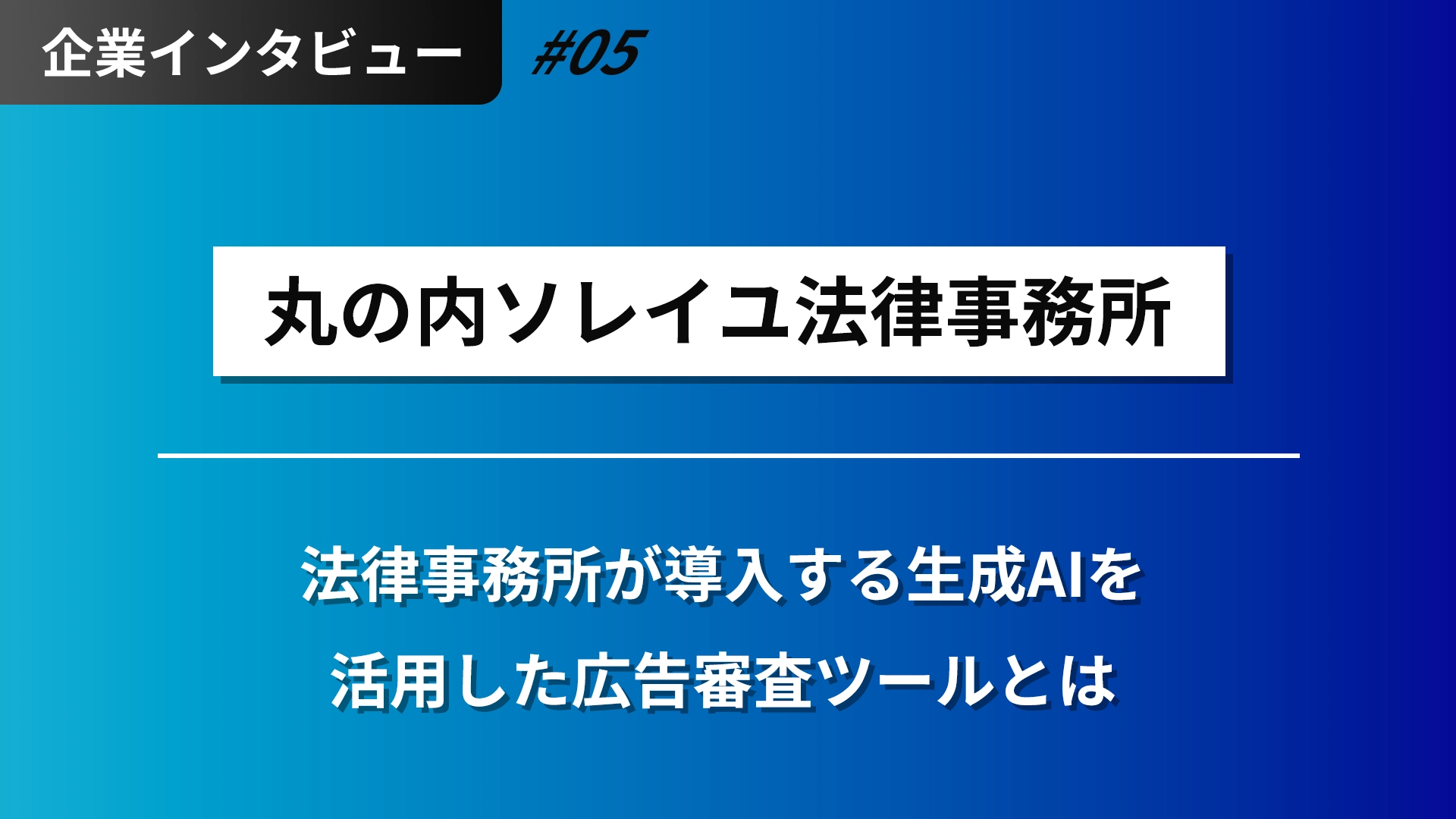
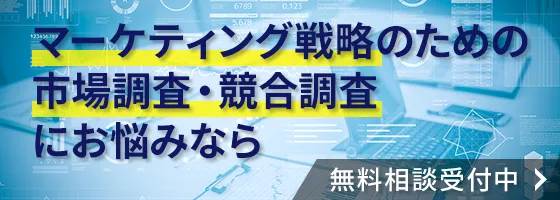
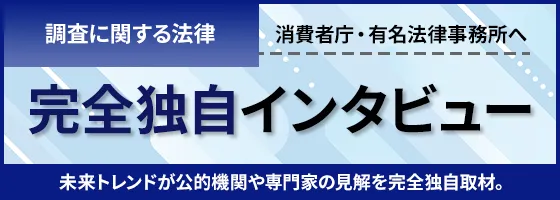
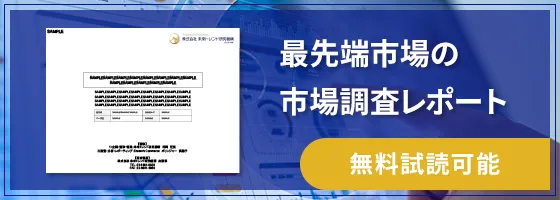


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com