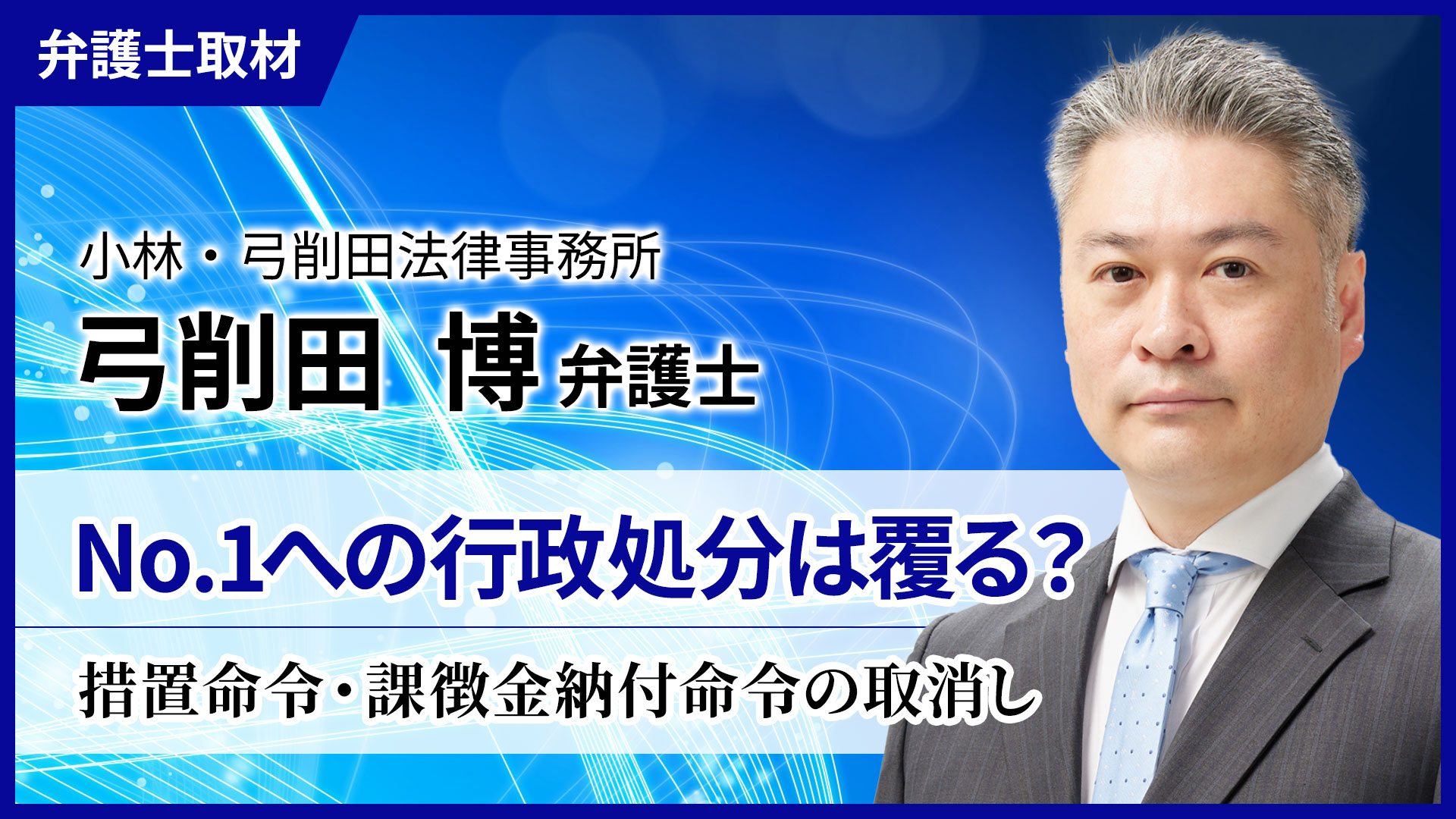
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
小林・弓削田法律事務所
弓削田 博弁護士
ゆげた ひろし
小林・弓削田法律事務所
https://www.yu-kobalaw.com/
知的財産分野を業務の中心に据える知財ブティック事務所。「所属弁護士全員が侵害訴訟・審決取消訴訟を中心とした知的財産分野の紛争案件を数多く経験していること」、「ビジネスの勢いを止めない法的サービスのスピードを重要視しており、原則としてお問い合わせを頂いてから半日以内には返答をしていること」
弓削田 博弁護士(第二東京弁護士会)
https://www.yu-kobalaw.com/lawyers/hiroshi-yugeta/
弁護士1年目から知的財産権訴訟に携わり、以後、長年にわたって特許権・商標権・意匠権・著作権・不正競争防止法違反など種々多彩な知財事件を担当。当事者の代理人としての訴訟・交渉業務に加え、当事者の主張に基づいて判断をする立場である東京税関の専門委員、特許庁の試験委員や法科大学院の知財教員など知的財産権の専門家としての多角的な経験と実績を積む。
自己の持つ経験と知識を総動員し、迅速な対応と、前例や定石に拘らない発想により、常にお客様にご満足頂ける事案解決を目指す。
 本文
本文景表法違反の措置命令・課徴金納付命令の取消しの難しさは?
事業者が景品表示法(以下景表法)を適切に運用せず、消費者庁から問題の表記とみなされた場合、措置命令・課徴金納付命令の処分対象となる。
事業者が措置命令・課徴金納付命令の行政処分対象となった場合、事業者は消費者庁の決定を覆すことができるのだろうか。そこで今回は、景品表示法案件で消費者庁との対応をした実績がある小林・弓削田法律事務所の弓削田博弁護士に話を聞いた。
多くの企業様・特許事務所様に依頼に対応する
措置命令・課徴金納付命令の撤回は可能?
結論を言えば、措置命令・課徴金納付命令を消費者庁が取り消しするケースは、何らかの落ち度が消費者庁側に無い限り無理だと考えておくと良いだろう。
何故そうだと言えるのか。その理由は景表法の実務を知り尽くした調査官と弁護士事務所から出向している主張・立証のプロフェッショナルである弁護士(調査官)が連携して調査するからだ。
「事業者が消費者庁の調査対象となった場合、消費者庁を完全に納得させる資料を提示出来なければ、措置命令・課徴金納付命令の対象になると考えて良いと思います。調査後に後追い資料を提示して事業者の主張を追加で立証することもできますが、調査官を説得出来る材料の資料を用意が出来なければ、評価を変えることは難しいでしょう」(弓削田弁護士)
消費者庁は事業者が仮に訴訟を起こした場合でも、十分に裁判で勝てるレベルの調査を実施する。
「消費者庁の調査では重箱の隅をつつくような調査が行われます。1箇所でも問題のある表記箇所があれば、それをきっかけに他の表記等にも不適切なものはないかと徹底的に調べられると認識しておいた方が良いかもしれません」(弓削田弁護士)
事業者の認識は「消費者庁が調査対象にすべき表記とみなされた広告は、最悪の場合措置命令・課徴金納付命令が下るかもしれない」と考えるのではなく、消費者庁の調査が入った時点で確度の高い証拠を掴んでいると理解しておくと良いだろう。
事業者が行うべき対策
消費者庁の措置命令は厳格であり、問題とみなされた表記を調査時に覆す点はかなり難しいことが分かった。では事業者はどのような対策をすべきなのか。弓削田弁護士によれば、消費者庁の調査への対策よりも、消費者庁の調査が入らないようにするための仕組み作りが重要とのこと。弓削田弁護士は3つの視点が重要と解説する。
- 社外の第三者のチェック
- 調査会社の選定
- 広告表記等の確認
事業者が広告に載せたい表記は、事業者自身の思いが強く、どうしても主観的な要素が入ってしまう。主観的な要素が入ることで、「この表記で問題ないだろう」という視点が、一般消費者の誤解を招く景表法違反に該当する表記の可能性も考えられる。
このような時に、第三者の目でチェックをすれば表記がおかしいかどうかを客観的に判断してもらえるだろう。
「消費者庁から調査対象となった際に「この広告表記の根拠の調査に当たって誰かの意見を聞きましたか」と質問された場合、「自社のみで行いました」と答えるか「弁護士や専門家の意見を聞いて調査を進めました」と答えるかでは調査官の心証もかなり変わると思います。広告の表記の評価だけでなく、適切な運用を事業者自身が行っていることをアピールする姿勢も重要です」(弓削田弁護士)
勿論、企業の法務担当者や一般消費者の感覚に近い担当者を配置して、表記を客観的に判断することもできる。しかし、事業者側の内部にいる人間はどうしても事業者寄りの見方をしてしまう可能性が高い。そのため見分けがつかない時は冷静な判断が出来る弁護士に聞くのが良いだろう。
「顧客満足度をはじめとした調査で、必要な表記は「自社調べ」ではなく、調査専門会社と連携を取りながら調査を実施することも重要です。特に初やNo.1の表記は表記の中でも細心の注意を払う必要があり、難しい調査ほど専門機関の調査が必要です。No.1や初といった表記は簡単に出来るものではありません。「うちならこのNo.1が取れます」という営業に安易に乗ってしまうのは危険だと思います」(弓削田弁護士)
消費者庁に目をつけられないNo.1や初表記とは
事業者が制度作りを構築する過程で、No.1や初表記を行う事業者がどのような視点で表記を運用すべきか分からないことも多いだろう。No.1と初表記それぞれ注意すべき点をまとめて紹介しよう
初表記について
初表記では表記をする際に「どのような領域での初」かを決めておくことで、調査方法を絞ることが出来る。特許を調べる際に求められるレベルの調査(公開調査、知財調査、深掘り調査)が必要であるが、それだけでは十分な調査とは言えない。関連分野の学者が発表している論文もチェックをし、本当に「初」と言えるか調べることも重要だ。
「初表記は該当する特許を調べるだけでは不十分です。競合の事業者が「初」と表記したい特許を持っていなくても、初に関わる周辺の特許を持っている可能性も考えられます。この事実を見落として「初」と表記してしまうと、誤った表記となってしまうため徹底的に調べなくてはなりません」(弓削田弁護士)
また弓削田弁護士は初表記を調査する際は特許に強い弁理士にも意見を聞くべきだと指摘する。
「景表法に強い弁護士も初表記に対しある程度知見がありますが、特許技術に対して精通しているのは弁理士です。弁理士に調査方法や調査結果を評価してもらうことで、「初」と表記出来るかの判断もし易くなると思います」(弓削田弁護士)
特許に強い法律事務所に相談をすれば、弓削田弁護士のような弁理士を兼ねている専門家に意見を聞くこともできる。初表記を検討している事業者は、景表法に強い弁護士だけでなく、特許に強い法律事務所や特許事務所に意見を聞くと良い結果が得られるだろう。
No.1表記に対してのポイント
No.1表記では、表記したいものに対するポイントがいくつかある。
- 網羅性
- 調査対象者の質とサンプル数
- 不実証広告に耐えられる表記
販売実績や成分量等のNo.1表記であれば、唯一無二を示すための「網羅性」、ユーザーに対して調査を実施するのであれば、「No.1表記にふさわしい対象者」となっているかどうか。全国規模のNo.1か地域のNo.1かによって「サンプルの対象者」の数も異なる。事業者によっては「最悪調査が入った際に不実証広告規制に耐えられる表記かどうか」という視点で検討する場合もあるだろう。
No.1表記を実施する事業者は、重要な視点がいくつかある中で、どこにポイントを置くべきなのか。
「私はNo.1調査に関しては全ての要素が重要だと考えています。消費者庁の調査が入った時に納得させられる調査結果となっているかが重要です。そのためには、やはり先にあげたポイントを全て満たした資料を用意しておかないと、消費者庁の調査官を納得させられないでしょう」(弓削田弁護士)
No.1表記が広告表示の主流となり、当たり前のように表記を実施する事業者もいるが、簡単に出来るものではない。だからこそ、どのようなNo.1を表記させたいのかを考えておくことも事業者は求められるものと考えて良さそうだ。
No.1や初の表記が問題となり消費者庁から調査が入ってしまったら、表記を覆すことが難しいと理解できたのではないか。どちらも簡単に表記できるものではない。だからこそ、正しく調査しNo.1や初が言える表記は有利な表記となるのだ。その視点を持って日頃から表記と向き合うのが事業者に求められる姿勢だと言えよう。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年06月27日
2024年06月27日





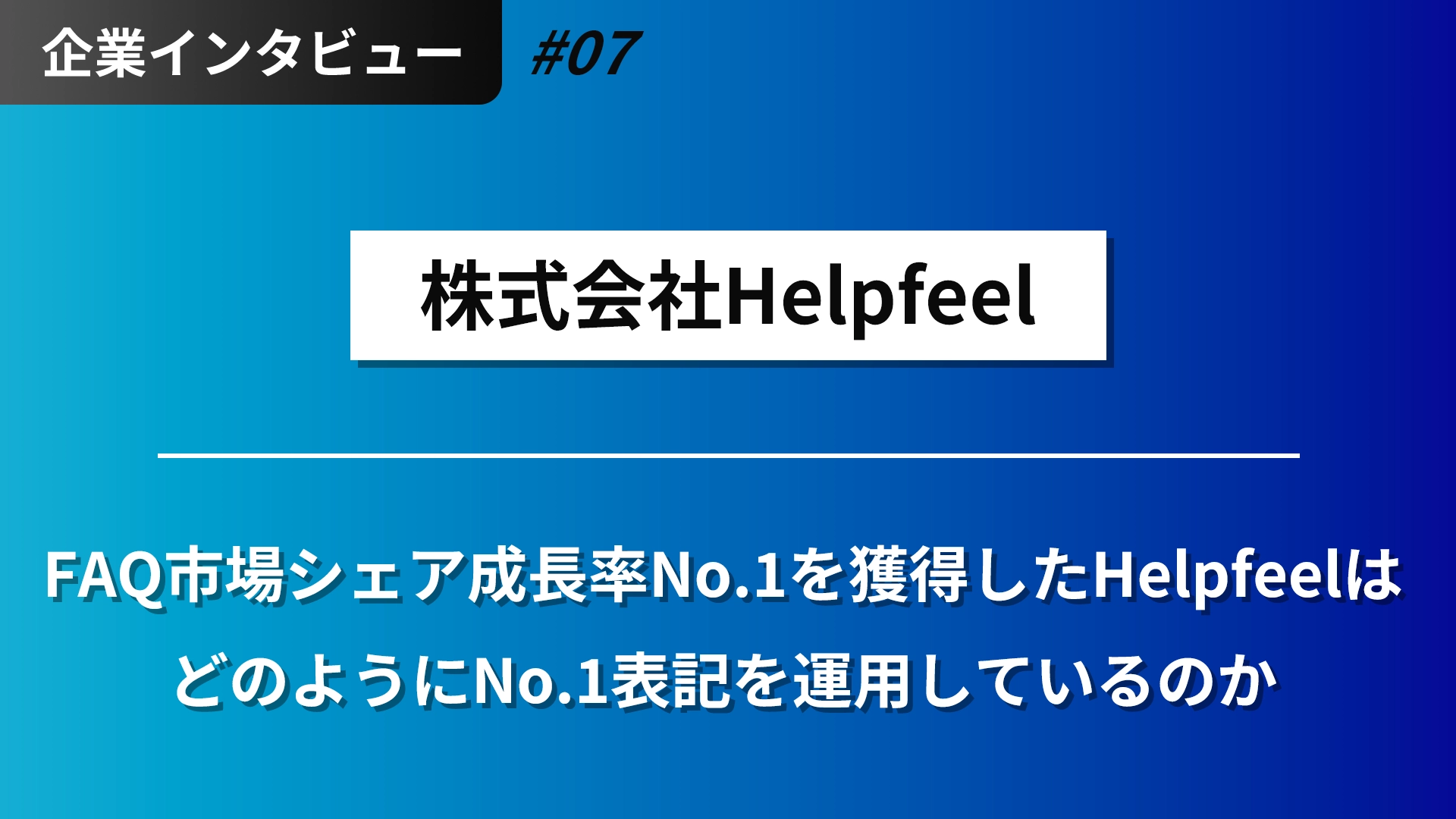

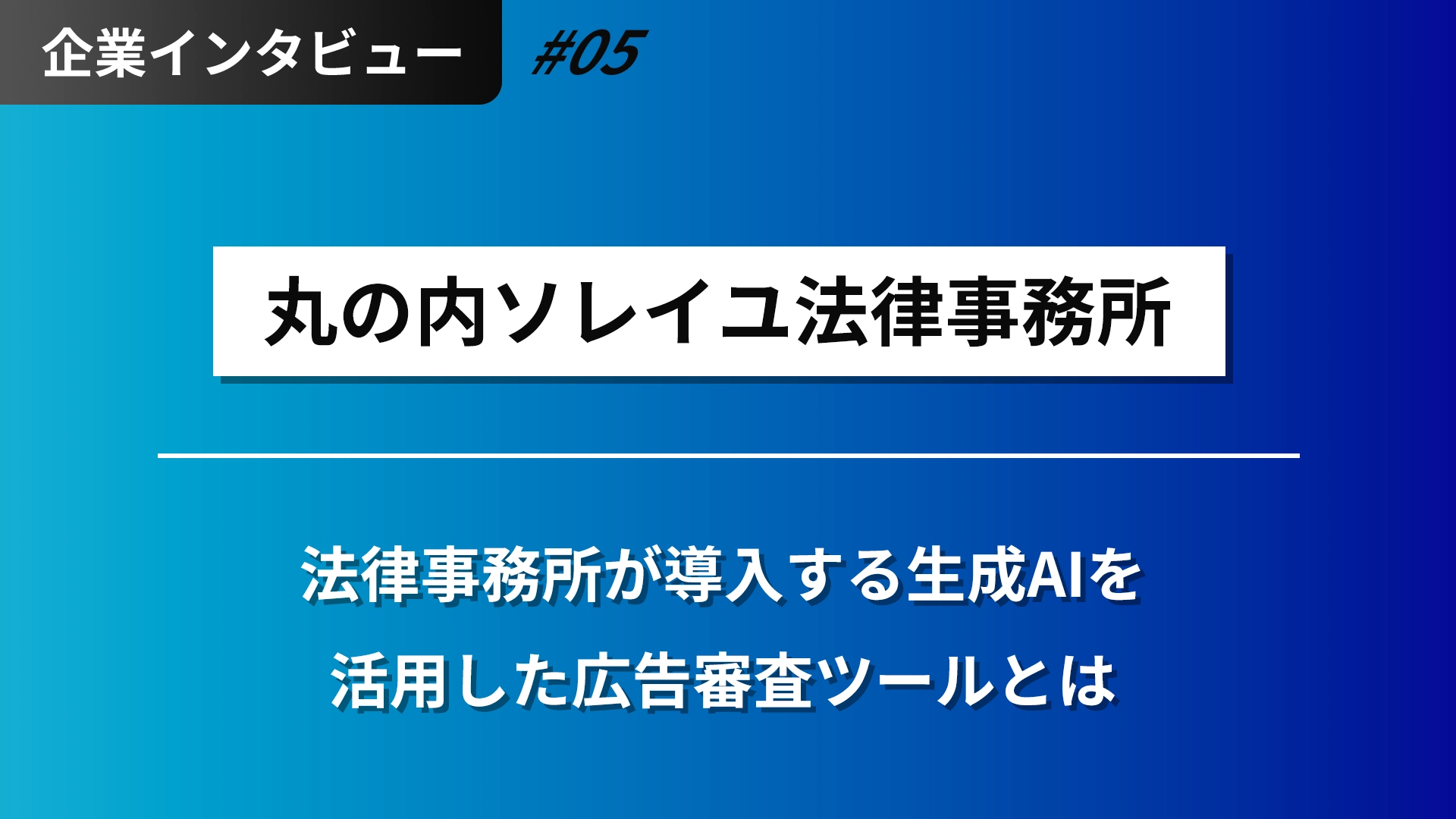
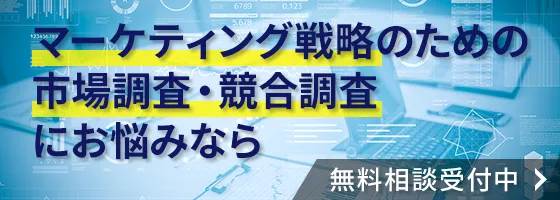
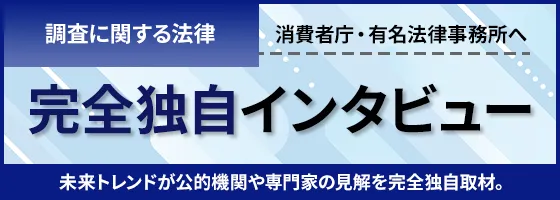
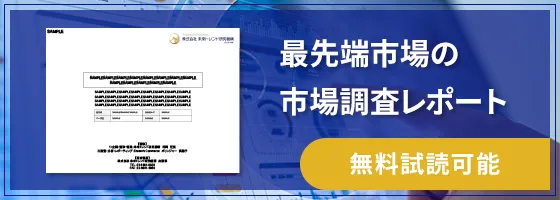


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com