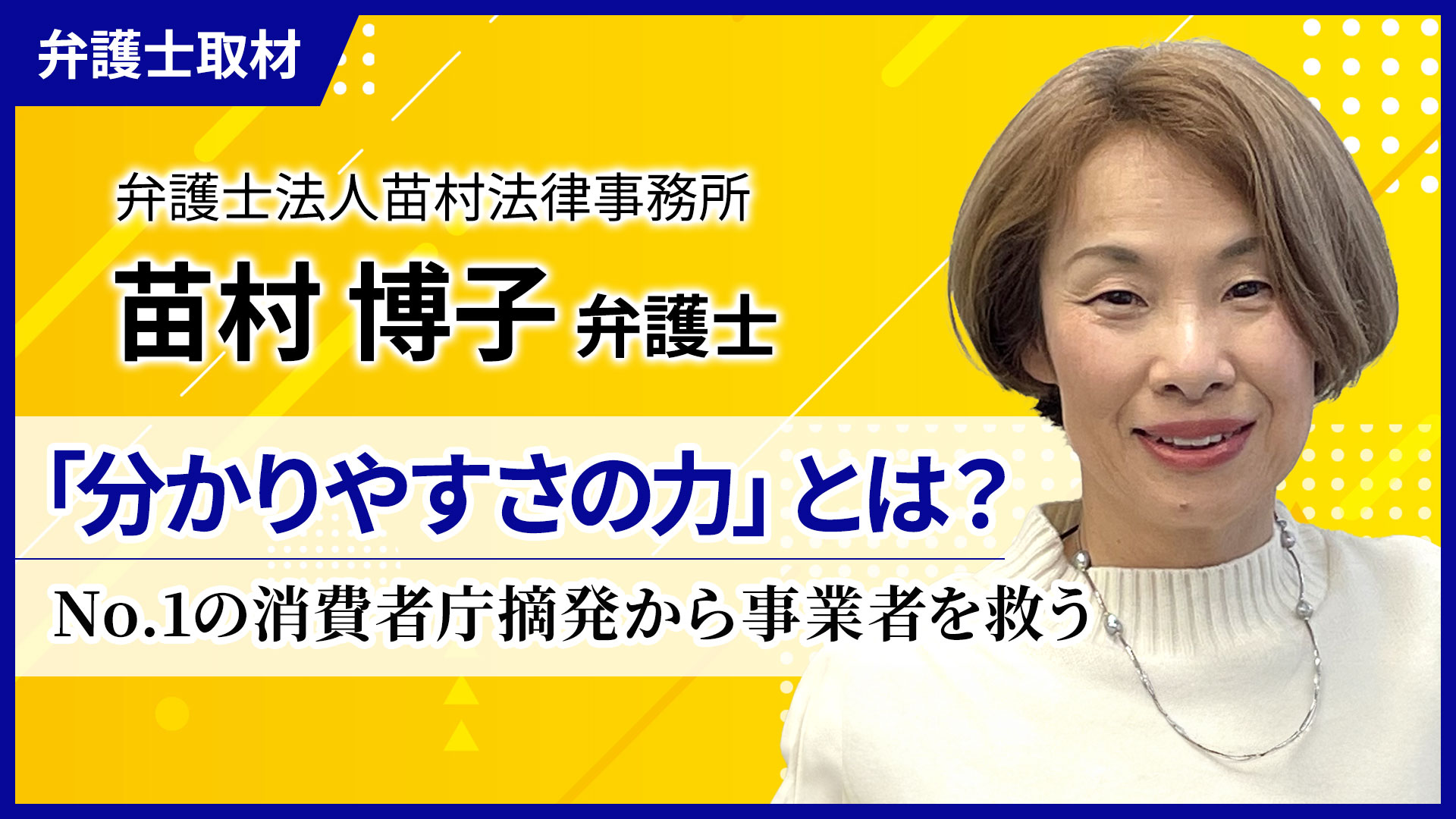
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
弁護士法人苗村法律事務所
苗村 博子弁護士
なむら ひろこ
弁護士法人苗村法律事務所
一般企業法務から知的財産権、海外国際取引など、様々な企業法務に精通している法律事務所。景表法に関するセミナーも積極的に実施し、事業者のビジネスをサポートする。また季刊誌「Namrun Quarterly」を発行し、事業者に様々な法律の知識と苗村弁護士の日常を発信する
https://www.namura-law.jp/nq50/
苗村博子弁護士(大阪弁護士会)
https://www.namura-law.jp/lawyers/苗村博子(なむらひろこ)
日本国内だけでなく、海外ビジネスを含めた様々な領域で活躍。景表法だけでなく、国際法務や知的財産権など、世界の競争法違反の対応や知的財産分野の訴訟など、様々な領域での対応が可能。
 本文
本文消費者庁の調査実態と事業者を助ける「分かりやすさの力」とは?
「No.1」や「初」表記に関する措置命令及び課徴金納付命令は、消費者庁が該当する表記を細かくチェックし処分対象かどうかを判断する。ここ1年以内に消費者庁が発表した措置命令・課徴金納付命令の事例を確認していくと、実態のない利用者に対して行う「顧客満足度No.1」、ホームページの印象を問うだけの「顧客満足度No.1」の表記が対象となる事例が多い。
杜撰な調査を元にしたNo.1表記は今後も厳しい調査が実施されることが考えられ、事業者はNo.1の裏付けと言える客観的な調査が求められる。しかし、適切な調査を実施しても、絶対に消費者庁の調査が入らない訳ではない。消費者庁調査への対策も備えておくことも重要だ。そこで今回は景表法違反に関する執行停止決定を得ることにも成功した弁護士法人苗村法律事務所の苗村弁護士に、事業者が知るべき行政対応についてお話を伺った。
「No.1」や「初」に関し事業者が知るべき視点
No.1や初を表記する際に求められる「客観的な調査」では、どのような視点が必要か。苗村弁護士によれば、以下のポイントが重要とのこと。
- No.1や初の表記したい内容と調査過程の表記に一貫性があるか
- アンケートの母数が一定の数、また実際に使用した人に尋ねたか
- アンケートで使用した設問が恣意的になっていないかどうか
この3つのポイントをクリアしていない調査は、No.1の客観的な調査資料として妥当と評価できない。例えばアンケート内容を客観的な視点で作成しサンプル数を1000以上集め「全国No.1」と言えたとしても、アンケート対象者全員が関西地域に住む人であれば、誤った表記になってしまう。
誰の目からも客観的な調査とは言ってもらえないという事例であれば、事業者でも、表記前に問題を見抜くことは可能だが、全ての調査過程を自社のみで評価するのは難しいと苗村弁護士は分析する。
「消費者庁がNo.1表記の裏付けとなる調査資料に求める要素は「客観的な調査」とは基準が曖昧です。事業者が適切に調査を実施したとしても何らかの見落としがあることも考えられます。可能であれば、弁護士や調査会社のような第三者に相談をして決めることも重要です」(苗村弁護士)
No.1表記を自社調べで実施する事業者は、客観的な資料を自社で作成可能かという視点で検討しておくことが重要だ。
万が一調査対象となってしまったら
客観的に妥当と判断できる調査を実施し、それに沿った表記を掲載しても絶対に消費者庁から調査を委託される公正取引委員会の調査が入らない訳ではない。場合によっては措置命令対象として調査が入る場合もある。このような時に事業者はどうすべきか。苗村弁護士によれば「適切な運用を心がけることが大前提ですが、万が一調査対応となってしまった場合に事業者がどう対応するか、あらかじめ検討しておくことも重要です」とのこと。
公取委の調査が万が一入ってしまった場合、事業者はどのような対処をすべきなのか。措置命令・課徴金納付命令の対象となった簡単な流れを説明していこう。
ポイント 調査官は一般消費者に近い
消費者庁は事業者に措置命令・課徴金納付命令を突然下すことはしない。公取委の調査官がまず任意の調査を実施し、景表法違反に該当すると判断して初めて行政処分になる。「公取委の調査官は必ずしも業界に詳しい専門家ではありません。どちらかというと一般消費者と近い知識・感覚の人が一般消費者目線で景表法の専門家として対象の表記をチェックしていると考えておきましょう」(苗村弁護士)
仮に公取委の調査官が知見のない一般消費者と考えれば、その表記を初めて見た時に「どう感じるか」という視点が最も重要となる。事業者自身が「専門家の目線でこの表記であればNo.1と言えるから問題ないだろう」という業界人の視点で評価しているのであれば今すぐ考えを改める必要があるだろう。
消費者庁との交渉
公取委の調査官が景表法違反とおおよそ判断した段階で、消費者庁は該当する事業者に連絡を取り、景表法に則り本格的な調査を開始する。「措置命令の対象となるかは、公取委、消費者庁との交渉も重要です。公取委の調査が万が一入った時に事業者は弁護士と連携しておくと良いでしょう」(苗村弁護士)
苗村弁護士によると、公取委や消費者庁との交渉時に大きく分けて2つのアプローチがある。弁護士を立てて交渉するケースと、裏で弁護士と連携を取って交渉を進めていくケースだ。
客観的な調査を実施したと強く主張できるのであれば弁護士を表立てることで、調査結果の正当性に自信があり、消費者庁に裁判に発展しても構わないと強気な姿勢をアピール出来る。
もう1つが弁護士と裏でやり取りをしながら、対応を考えるというアプローチだ。「どのような資料を提示するか、どのような点を公取委や消費者庁は知りたいのか、弁護士の目線からアドバイスが可能です」(苗村弁護士)。
調査内容に対し少しでも不安要素があれば、弁護士の助言をもらいながら進めるのも手だ。
不実証広告は消費者庁が行う最終手段
消費者庁が対象となった表記に対し妥当と評価できない場合は、最終手段として不実証広告規制に基づき客観的な根拠を示す資料を提示するよう要求する。
「不実証広告規制は消費者庁が求める資料を15日以内に提示できなければならない制度です。この制度を消費者庁が発動する時は調査が最終段階に来たと判断するのが良さそうです。そうならないためにも初期段階で弁護士と連携をとって対処することが重要となります」(苗村弁護士)
No.1表記の裏付けとなる調査を実施する際、不実証広告規制に耐え得る資料を事前に作成すべきという声は、消費者庁の調査の最終局面で必ず提示するよう求められるためだ。事業者は万が一調査が入った場合でも対応出来るよう、不実証広告規制に耐え得る資料を作成しておく必要がある。
新制度 確約手続の考え方
これまでの景表法で措置命令・課徴金納付命令の対象となった事業者は、裁判で争わない限り消費者庁が決定した行政処分をそのまま受け入れるしかなかった。
しかし改正景表法では事業者が措置命令・課徴金納付命令の対象となった際に、確約手続を利用すれば、表記・事業の体制を改善する代わりに措置命令・課徴金納付命令が免除される。
「確約手続は条件を提示して措置命令等を免除してもらうことになりますが、確約手続の内容を60日以内に作成し、確実に実行しなければなりません。商品・サービス次第では返金対応をどうするかなど、具体的に検討しなければならないので注意が必要です」とのこと。
確約手続は行政処分を免れる制度でもあるが、公表リスクもある。確約手続を利用すれば景表法違反に該当した場合でも簡単に回避出来る訳ではないため注意が必要だ。
景表法の正しい運用
景表法は常に変化するもの。これまで問題無いとされていた表記に対し調査が入ることも十分考えられる。事業者はグレーゾーンを大前提として正しく適切に運用することも重要だ。適切に運用するためには事業者自身が適切な基準を社内で構築しておくことが重要となる。
「品質保証部を持っているのであれば法務部との間で、客観的な評価はこれだと必ず確認できるような体制づくりができますが、そうでない事業者は表示と根拠が適切なものが何かの認識のすり合わせを社内で検討することが必要です」(苗村弁護士)
No.1や初の表記をする際にはどのようなアプローチで調査を実施するのか、第三者機関の選び方や弁護士との連携方法などを調整しておくと良いだろう。
また、調査過程の根拠を示す資料を作成する際に「分かりやすさ」という視点も重要と苗村弁護士は説明する。
「先述した通り、調査官、裁判官どちらもその事業や調査方法に精通しているのではなく一般消費者に近い感覚で判断します。専門的な資料を提示して正当性を主張するだけでなく、誰が見ても判断できるような、分かりやすさという視点で資料を作成するようにしましょう」(苗村弁護士)
専門的な用語や数値を多用し、調査過程の正当性を証明する調査資料を作成したとしても、一般的な視聴者の感覚しか持たないようであればその資料だけで妥当かの判断を行うことはできない。調査過程で作成した資料も公表する表記と同様に、分かりやすい資料となっているかという視点で第三者にチェックをしてもらうことが重要だ。
分かりやすさを意識して調査資料を常日頃から行なっていれば、どのような調査が入ったとしても事業者の正当性を証明することが出来るだろう。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。
その他の弁護士インタビュー
-
 神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」
神田弁護士へのインタビュー「消費者庁が措置事例に至るまでに実施する調査とは」 -
 神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」
神田弁護士へのインタビュー「景表法対策は専門弁護士に相談した方が良い理由」 -
 籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」
籔内俊輔弁護士へのインタビュー「消費者庁が注視する「二重価格」

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年06月14日
2024年06月14日





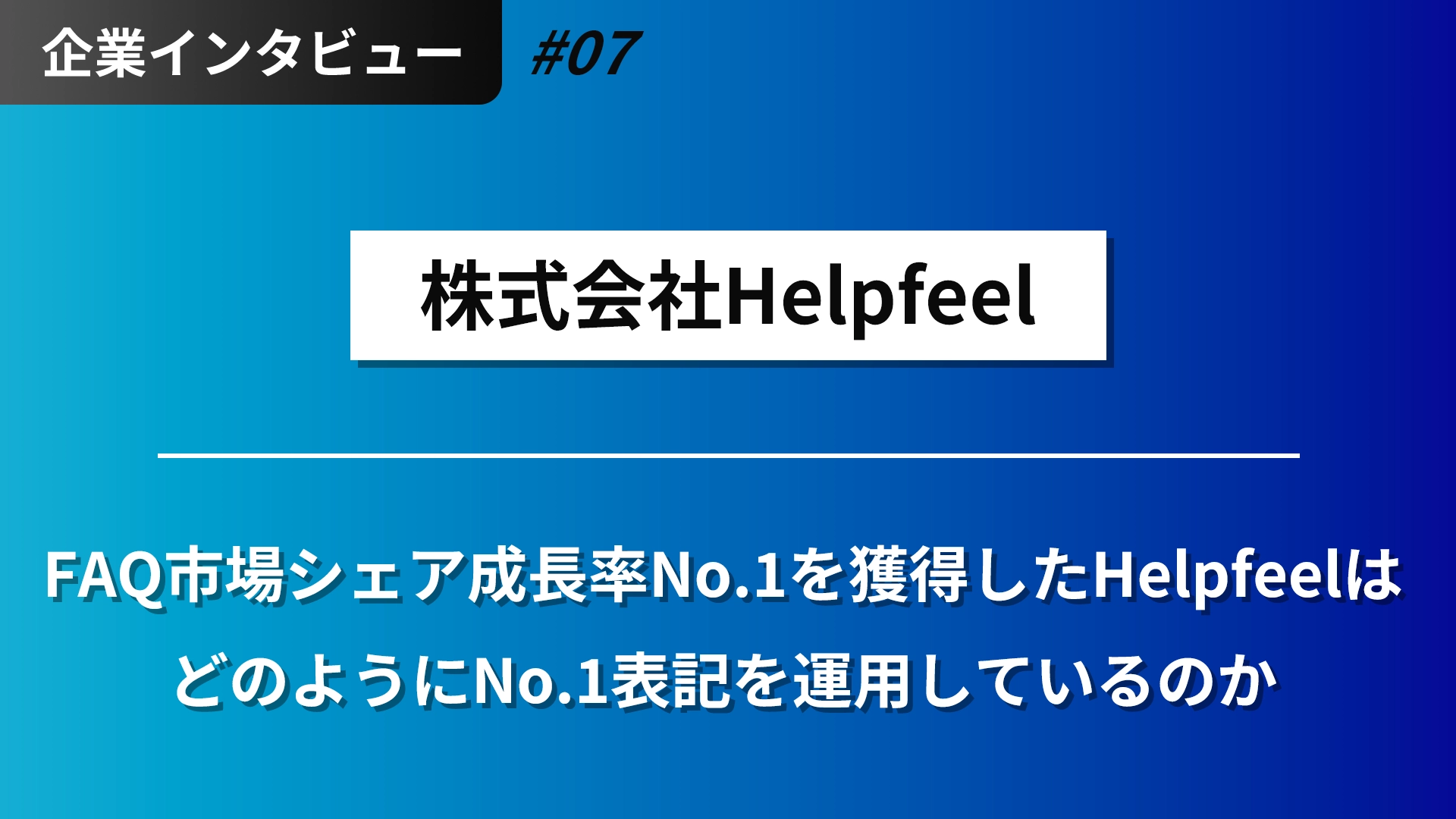

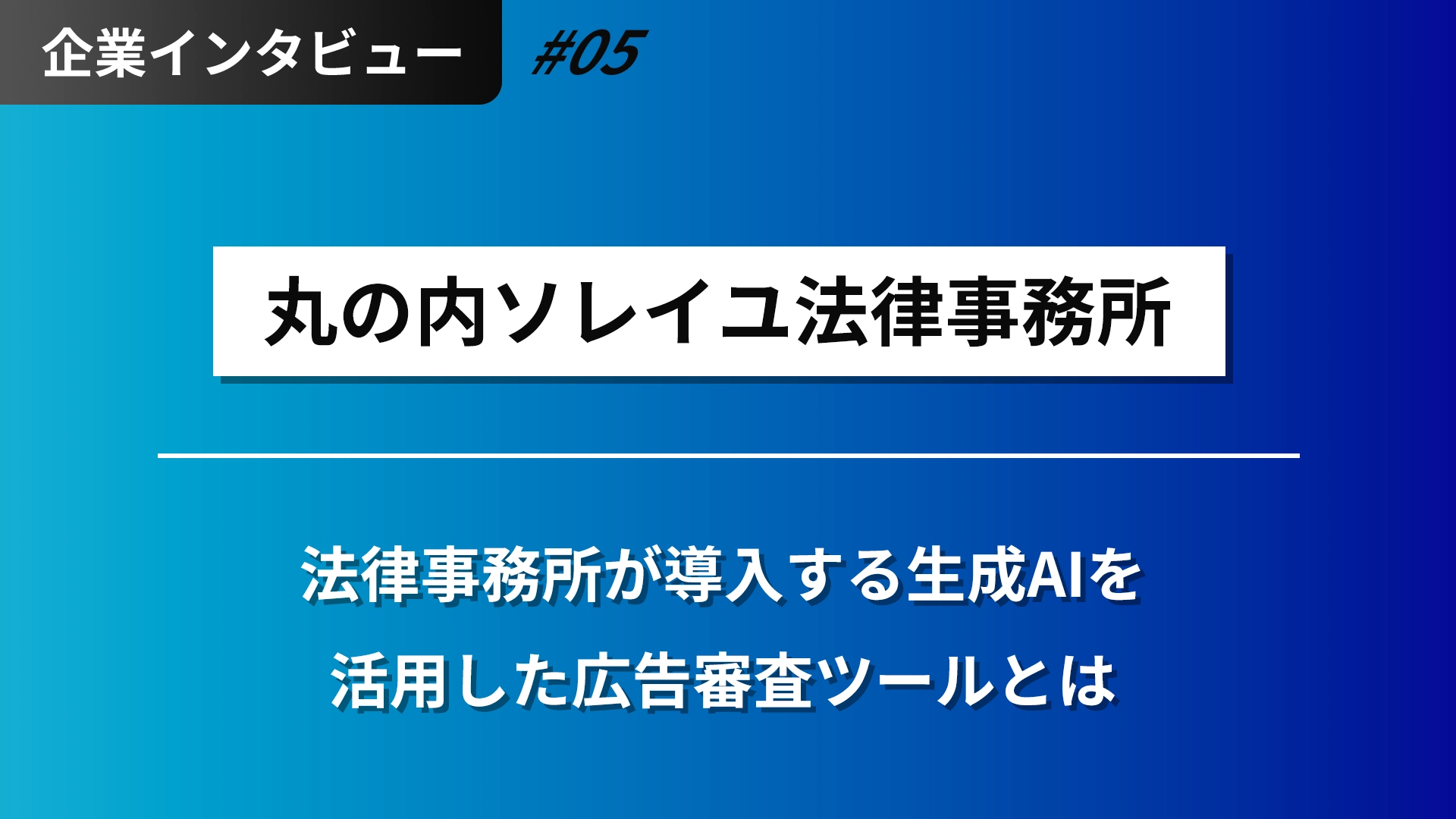
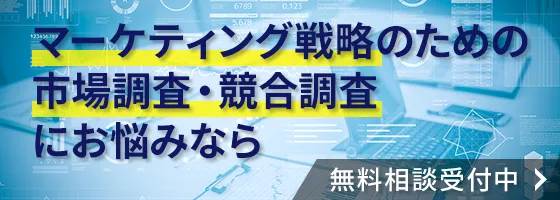
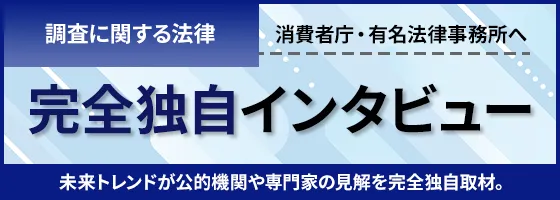
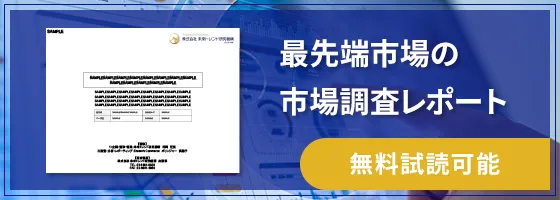


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com