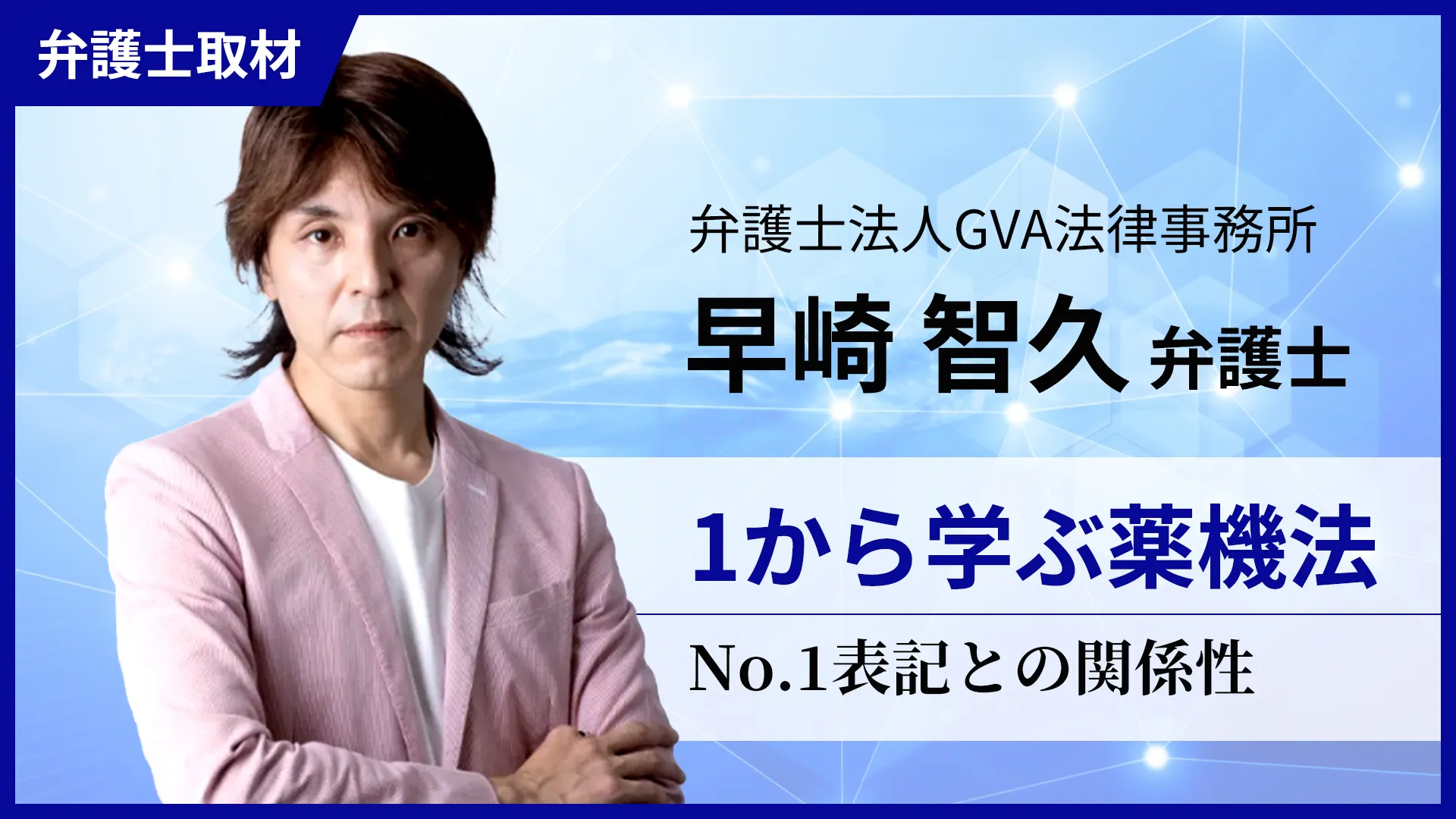
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール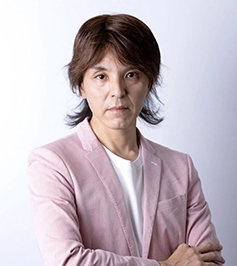
弁護士法人GVA法律事務所
早崎智久 弁護士
はやさき ともひさ
 本文
本文1から学ぶ薬機法 NO.1表記をしてはいけない商品類への対抗策
「No.1」検証調査を外部機関などに依頼・検討する方々に貢献する『No.1調査』支援プロジェクトを始動!
株式会社未来トレンド研究機構(東京都千代田区、代表取締役:村岡 征晃)は、『No.1調査』支援プロジェクトを開始した。本目的であるが、初めて、第三者機関に『No.1調査』検証業務を依頼・検討している方々をお助けしていくためのものである。始動は2024年3月18日~。
医薬部外品、化粧品、健康食品、健康·美容雑貨等は「No.1」「初」などの表記に細心の注意をする必要がある。特に、今回は販売する企業にとって役立つ情報として、「薬機法とNO.1」について、早崎弁護士にお話を伺った。
薬機法が適用される化粧品や医薬部外品などの商品では、適正広告基準やガイドラインにより、商品の効能効果や安全性に関する最上級表現はNGとされているため、商品の内容に関する「No.1」表記を絶対に避けるべきだと早崎弁護士は指摘する。この「最上級表現」というのは、「最大」「最高」「NO.1」と表記しなくても、その言葉の意味が最上級であれば、該当する。そのため、「他社と比べて圧倒的な効き目の高い製品」としても、薬機法違反に該当してしまう。
この点、LPサイトやネット広告の中には「売上本数NO.1」と表記を掲載している場合もある。しかし、「売上」は、商品の効能効果や安全性ではないことから、客観的な事実に基づいたデータを示せば、「化粧品部門売上本数NO.1」と表記できる。この場合であれば、ガイドラインに違反しない表現となる。
しかし、この場合でも記載方法を誤ると景品表示法違反に該当する表記もあると広告主は認識しなければならない。売上本数や成分の中でNo.1かを調査するのではなく、一般消費者が混乱しないように明確な情報を提供することが重要だ。
今挙げた事例だけでも分かるように、医薬部外品、化粧品、健康食品をはじめとする薬機法関連の商品では、広告掲載時の細心の配慮を払うことが必要である。
ただ、掲載可能な表現にするため、薬機法に関するガイドラインが存在するが素人では法解釈を誤って解釈してしまうことも珍しくはない。薬機法関連では、他の商品と比べてルールの数が多く、内容も複雑だ。
仮に広告主が類似商品の広告を参考に表記しても、参考元の商品が薬機法や景品表示法に違反する表記がある可能性も考慮しなければいけない。「他社がやっているから大丈夫」と考えるのは危険だ。知識のない広告主が薬機法関連の商品の広告を掲載するためには、十分な配慮が必要なのだ。
広告主が商品を正しく表記するためにどうすべきか、早崎弁護士は「薬機法関連の商品こそ、第三者のチェックを受けるべきだ」と指摘をする。
薬機法関連の広告では、正確なデータを備えるためにも第三者機関の調査はもちろんのこと、リーガルチェックも必要不可欠と心得ておくことが賢明な判断と言えるだろう。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2024年03月14日
2024年03月14日


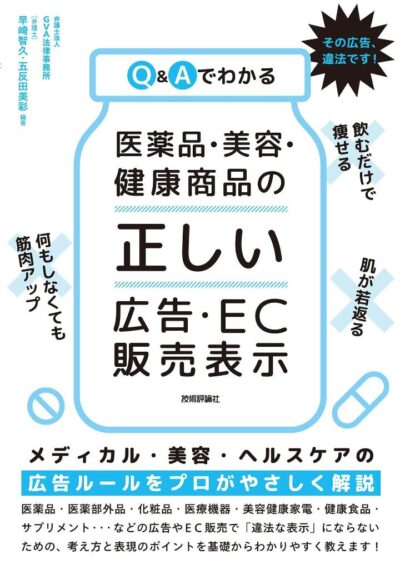
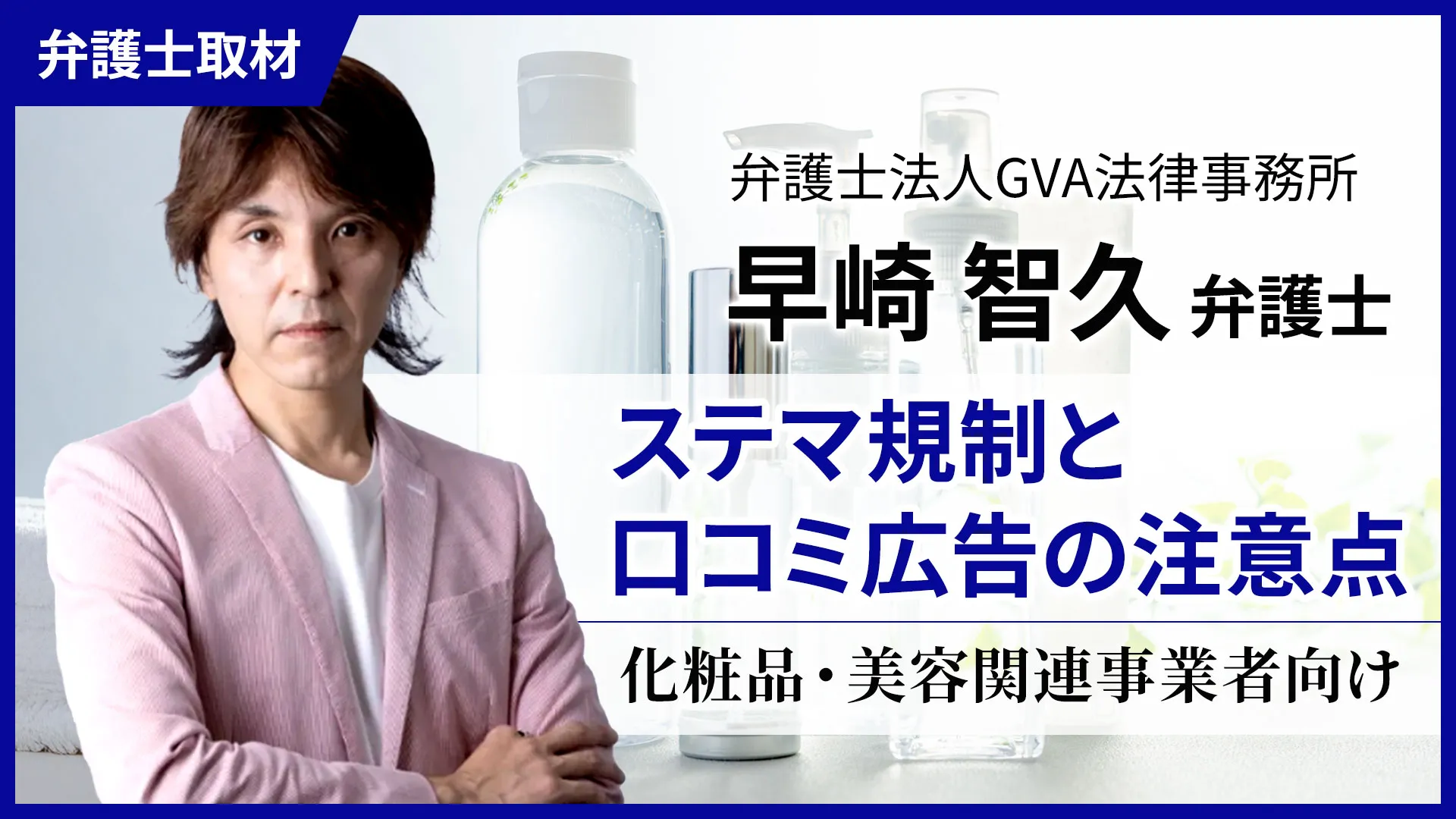
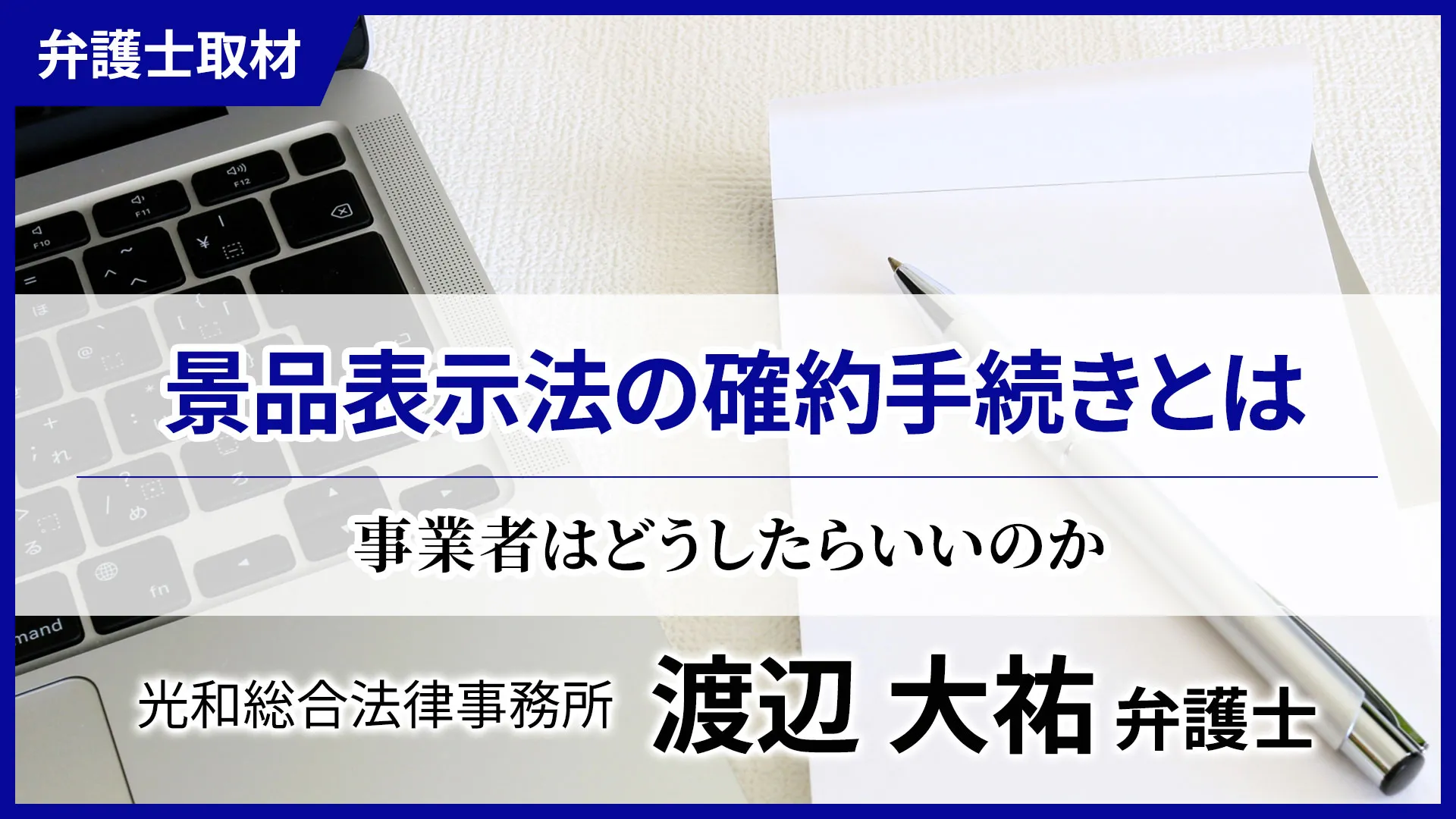




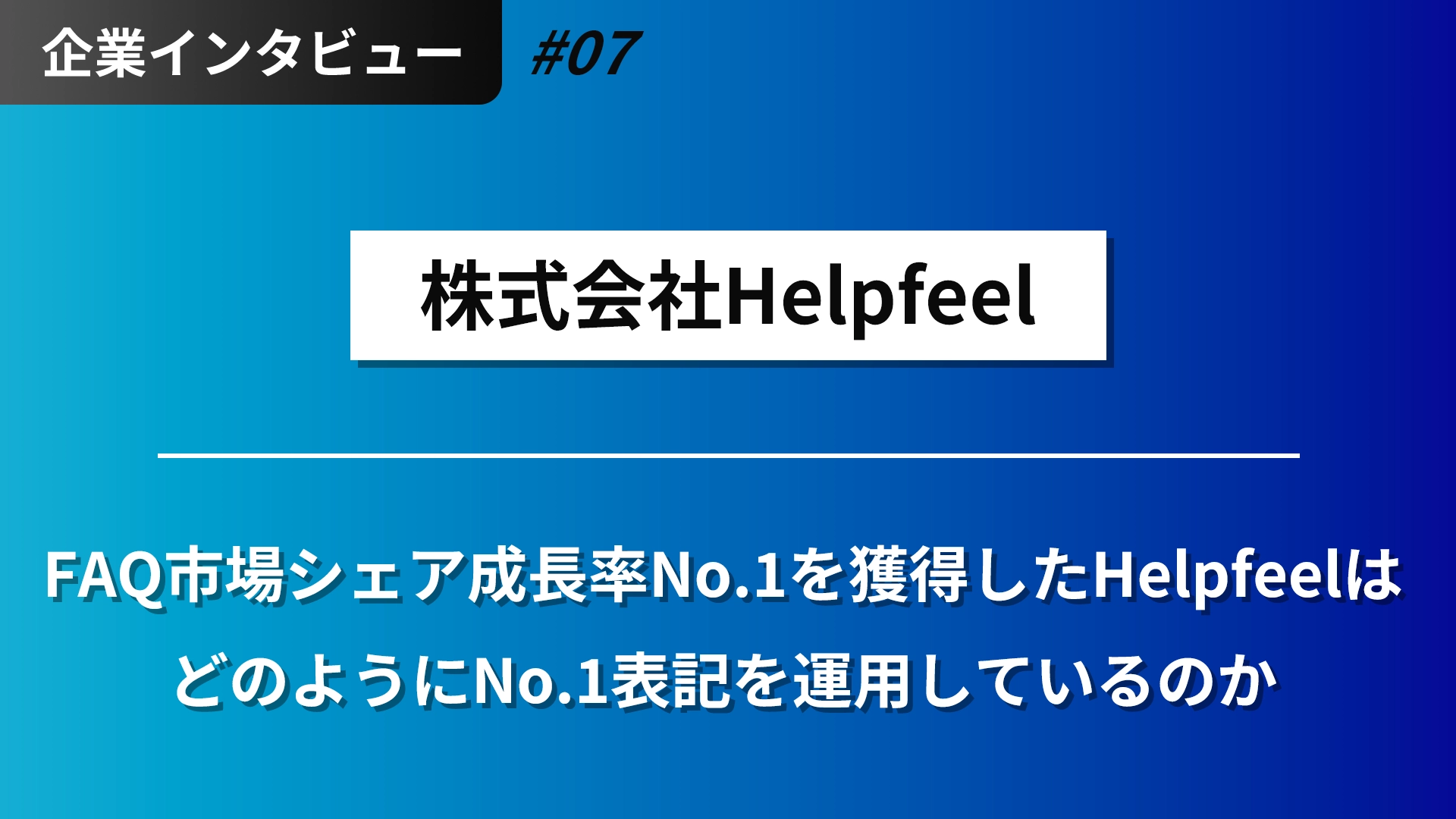

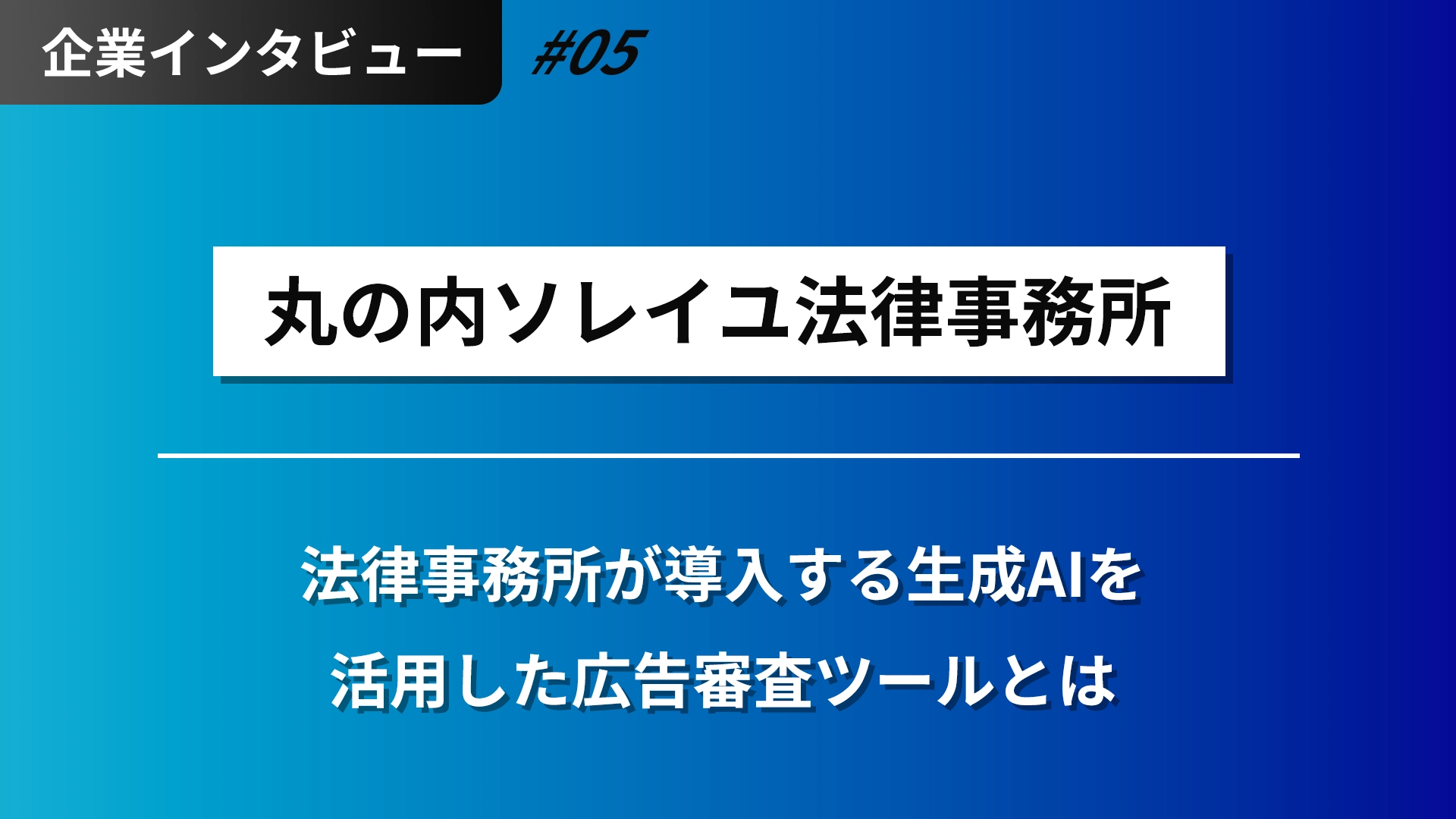
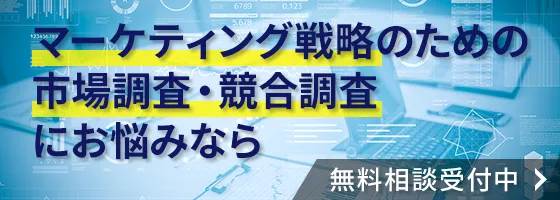
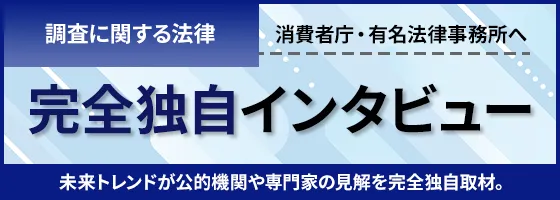
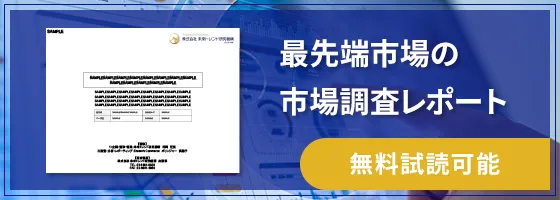


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com