
 弁護士プロフィール
弁護士プロフィール
湊総合法律事務所
野坂 真理子 弁護士
のさか まりこ
野坂 真理子弁護士(東京弁護士会)
https://www.kigyou-houmu.com/profile/#nosaka
湊総合法律事務所ジュニアパートナー。
早稲田大学法学部卒業。
企業法務、広告法務に精通し多数の企業向けセミナーも実施している『こんなときどうするネット 会社で使える書式と文例』(共著、第一法規、2016年)、「労働条件の不利益変更のトラブルはこうして防ぐ」月刊企業実務2009年5月号)、「退職者の他社への再就職・独立をめぐる問題と解決策」ビジネストピックス(みずほ総合研究所)ほか多数執筆。
書籍
- 勝利する企業法務~実践的弁護士活用法(レクシスネクシス・ジャパン)
- 従業員をめぐる 転職・退職トラブルの法務~予防&有事対応~(中央経済社)
湊総合法律事務所
https://www.kigyou-houmu.com/introduce/
上場会社から中小企業・学校・病院・その他団体など200社以上の企業と顧問契約を締結。
景表法だけでなく、契約書のチェック業務、日常の経営判断の適切な法的サポート、至急の経営課題への対応を実施。
企業法務案件を主力として、企業間紛争、従業員や取締役との法律問題、不動産事件、医療事件、債権回収、事業承継、知的財産事件などを取り扱う。
 本文
本文No.1表示向け管理措置指針「情報の共有」について
No.1表示実態調査報告書では、どのようなNo.1表示が問題となるかについては報告があるが、具体的な施策等は限定的である。
No.1表示を目指す事業者が景品表示法に則った運用を行う際に重要とされる「管理措置指針」(事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針)では、事業者が講ずべき管理措置の内容として、以下の7つの項目が挙げられている。
①景品表示法の考え方の周知・啓発
②法令遵守の方針等の明確化
③表示等の根拠となる情報の確認
④表示等の根拠となる情報の共有
⑤表示等を管理するための担当者等を定めること
⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置をとること
⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
しかし、事業者がNo.1表示に適切に対応するためにどのように考えるべきかの具体的な説明は無い。
そこで、㈱未来トレンド研究機構では、7つの項目の中でもNo.1表示を目指す事業者がどう対処すべきかについて、重要な項目を1つずつ紹介する。
今回は「情報の共有」について、企業法務に精通している湊総合法律事務所の野坂真理子弁護士に話をお伺いした。
情報の共有について
管理措置指針について求められる情報の共有とは何か。
管理措置指針には以下のような記載がある。
事業者は、(1)景品類を提供しようとする場合、違法とならない景品類の価額の最高額・総額・種 類・提供の方法等を、(2)とりわけ、商品又は役務の長所や要点を一般消費者に訴求するために、その内容等について積極的に表示を行う場合には、当該表示の根拠となる情報を 確認すること。
・・・事業者は、その規模等に応じ、(上記のとおり)確認した情報を当該表示等に関係する各組織部門が不当表示等を防止する上で必要に応じて共有し確認できるようにすること。
また、事業者が表示等の作成を他の事業者に委ねる場合、当該他の事業者に対しても同様の対応を行うこと。
-消費者庁 事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針より
「表示は事業者自身が行うため、自分自身で表示に対しての責任を持たなければなりません。
No.1表示を行う場合に、その表示と根拠となる調査結果が正確に紐づいているのかなど情報を確認しておく必要があります」
管理措置指針に沿ったNo.1表示を行うためには、No.1の裏付けとなる調査資料をしっかり確認することが求められる。
可能であれば、調査結果でもあるNo.1の裏付け資料を紐付けていつでも説明できるようにしておくと良いだろう。
適切に運用をしている事業者でも、よくあるトラブルがある。
「担当者が部署を異動したり退職したりしたタイミングで、情報が引き継がれないこともあります。
No.1表示を行う際に担当者がその根拠を把握していても、消費者庁の調査が入った段階で、会社が裏付け資料と共に適切な根拠があることを説明ができなければ、不当なNo.1表示であるとみなされてしまいますので、担当者が当該表示の担当を離れる際には、必ず客観的資料と共に引継ぎを行っておくことが重要です。
また、No.1表記の根拠となったアンケートの内容や結果が把握できていなければ、商品・サービスの変更があった場合など、No.1表示をそのまま表示し続けることが不当な場合が生じても気づくことができません。
知らず知らずのうちに優良誤認に該当してしまう恐れがあるので注意が必要です」
表示は常に最新の情報になるように部署内で常に確認しておくことが重要だ。
勿論、No.1表示だけでなく、それ以外の情報も最新の情報を掲載されているかを確認しておくと良いだろう。
調査会社への対応
情報の共有は、「また、事業者が表示等の作成を他の事業者に委ねる場合、当該他の事業者に対しても同様の対応を行うこと」とあるように事業者自身だけではない。
No.1表示の裏付けを調査会社に依頼する場合は、同様に情報の共有を行うことも重要だ。
その際、特に気を付けるべき点は調査会社に依頼する際に恣意的な調査を実施させないよう、資料を適切に共有し、かつ、共有させることだ。
調査会社が適切に調査を実施していたとしても、事業者が提供する資料が恣意的なものであれば誤った結果が出てしまう可能性がある。
また、調査会社が行う調査においても、競合の選定やデータの開示が恣意的にならないように、資料を共有させ注意しておくと良いだろう。
調査会社の提示した調査結果に対し、事業者が責任を持つことも重要だ。
調査会社の選定や対応について、弁護士によって見解が異なるが野坂弁護士は次のように考える。
「事業者によって判断基準は異なると思いますが、調査会社がどのような調査を実施し、過去にどのような表示の調査に携わったかという実績を確認することも重要ではないかと思います」
さらに、調査会社に調査依頼する際に、調査結果を自分たちなりで検証することも重要だ。
「知見がない事業者だからこそ、調査会社に依頼をした際に「このようなアンケートを取ったところ、No.1という結果が出ました」と言われたことを鵜呑みにしてしまうこともあります。
自社の商品、サービスとしてNo.1表示を行うわけですから、そのためにどのような調査が行われたのか、適切な方法による調査であったのか、その調査結果に基づく表示として適切に対応しているのかを掘り下げておくことも重要です。
掘り下げずに誤った表示に気づかず掲載すれば、事業者自身が責任を問われるので注意が必要です」
No.1表示を目指す際は、どのようなアンケートによりNo.1表示の裏付け調査を行なったのか、提示された資料をそのまま確認するのではなく、根拠を調査会社側に説明させると良いだろう。
まとめ
今回の取材で、No.1表示を目指す事業者が「情報の共有」を行う際は、以下のポイントを押さえておくことが重要であることが分かった。
- No.1表示の根拠となる裏付け資料は所内で必ず保管しておく
- 常に最新情報となるよう情報を網羅
- 調査会社に依頼をする際は恣意的な調査にならないよう実施される調査に関する情報を適切に共有する
- 調査会社に依頼をする際は丸投げではなく根拠を確認する
上記4つのポイントを意識しておくことで、管理措置指針に求められる対策が可能となるであろう。
それでも不十分に感じられる場合は、1から景品表示法について解説する野坂弁護士のような有識者に意見を求めることを推奨する。
本インタビューの監修者
 未来トレンド研究機構
未来トレンド研究機構
村岡 征晃
1999年の創業以来、約25年間、IT最先端などのメガトレンド、市場黎明期分野に集中した自主調査、幅広い業種・業界に対応した市場調査・競合調査に携わってきた、事業発展のためのマーケティング戦略における調査・リサーチのプロ。
ネットリサーチだけなく、フィールドリサーチによる現場のリアルな声を調査することに長け、より有用的な調査結果のご提供、その後の戦略立案やアポイント獲得までのサポートが可能。
そんな我々が、少しでもマーケティング戦略や販売戦略、新規事業戦略にお悩みの皆さんのお力になれればと思い、市場調査やマーケティングに関しての基礎知識や考え方などを紹介しております。

 03-6801-6836
03-6801-6836 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com



 2025年08月29日
2025年08月29日


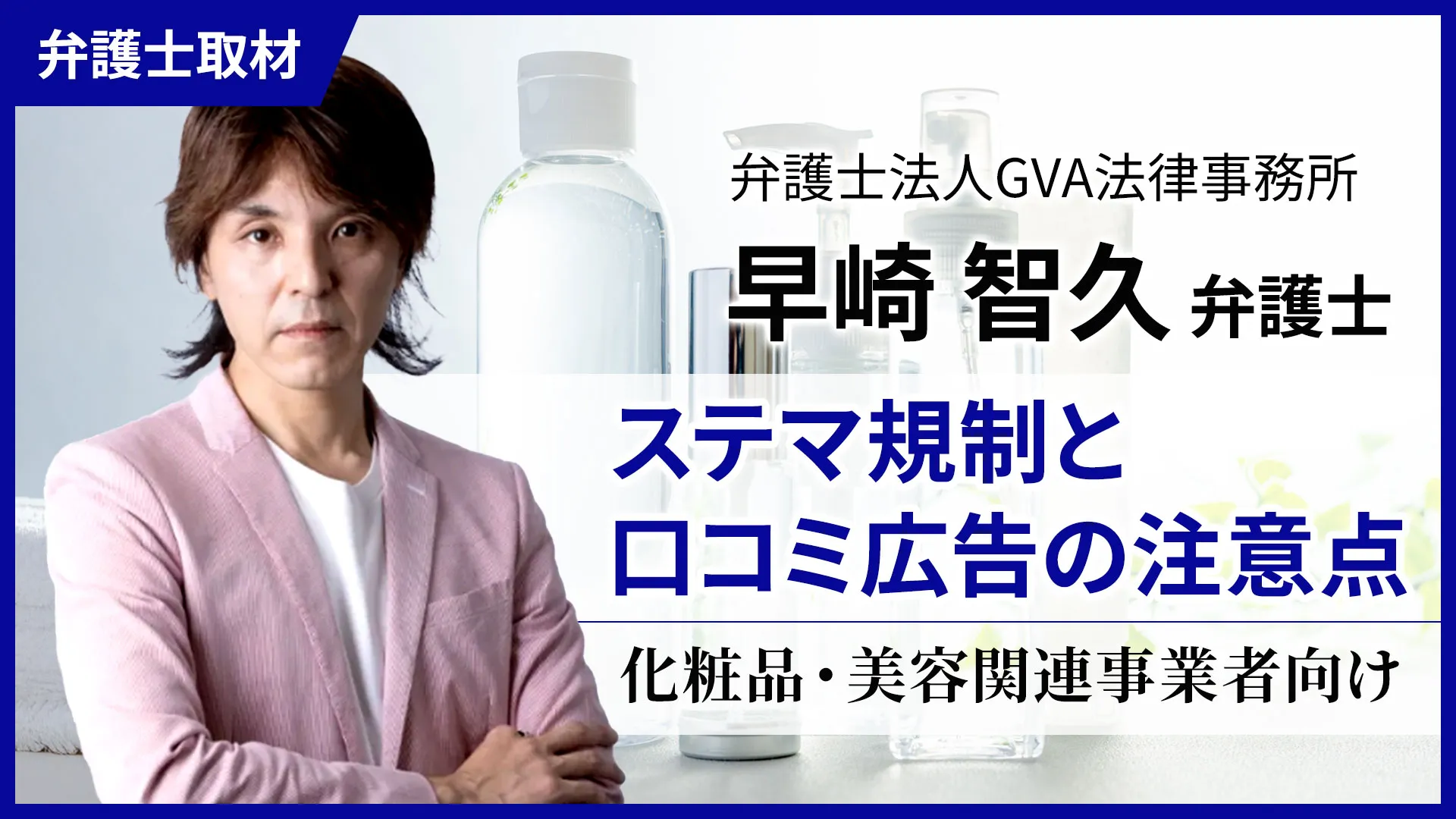
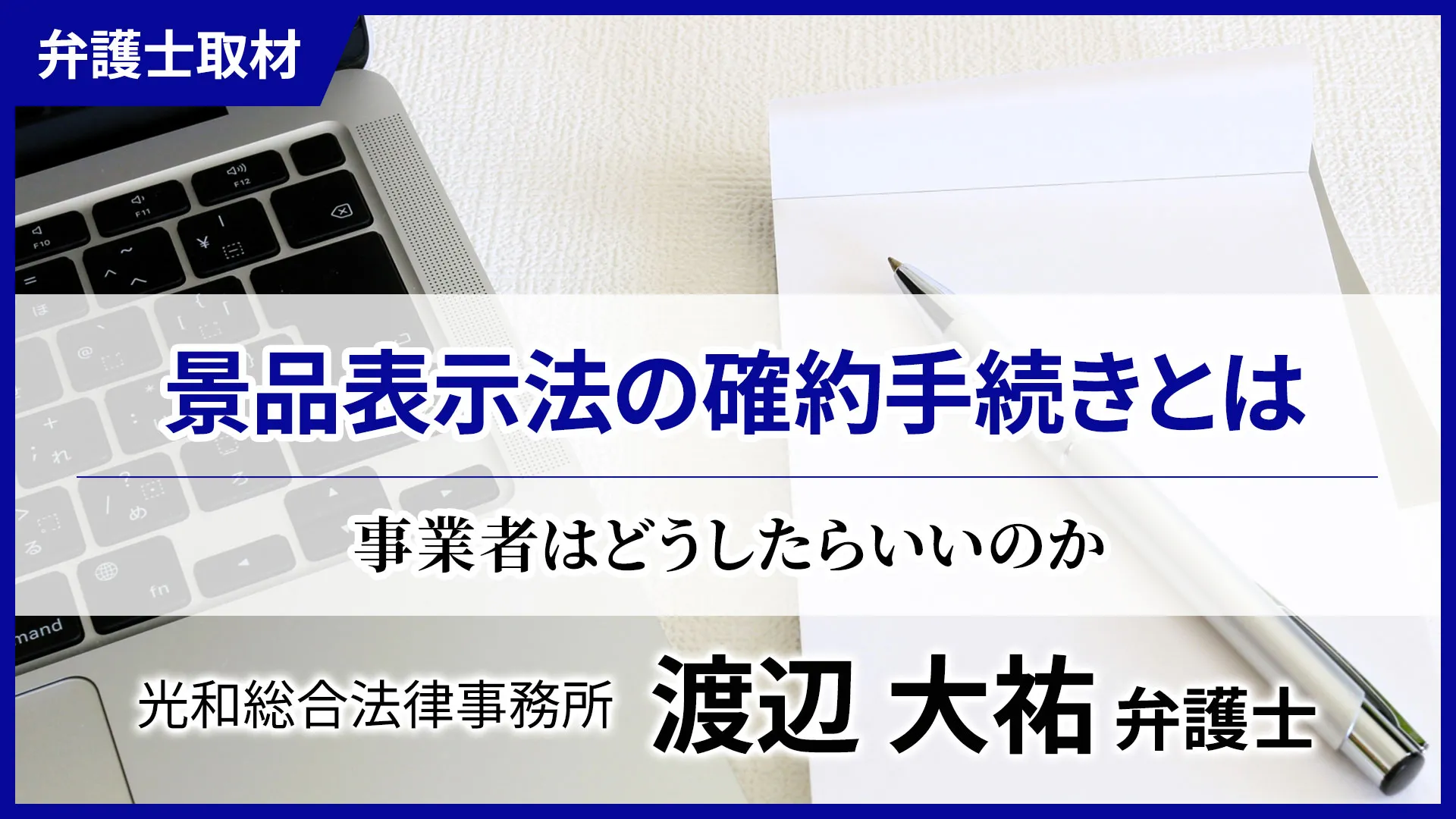




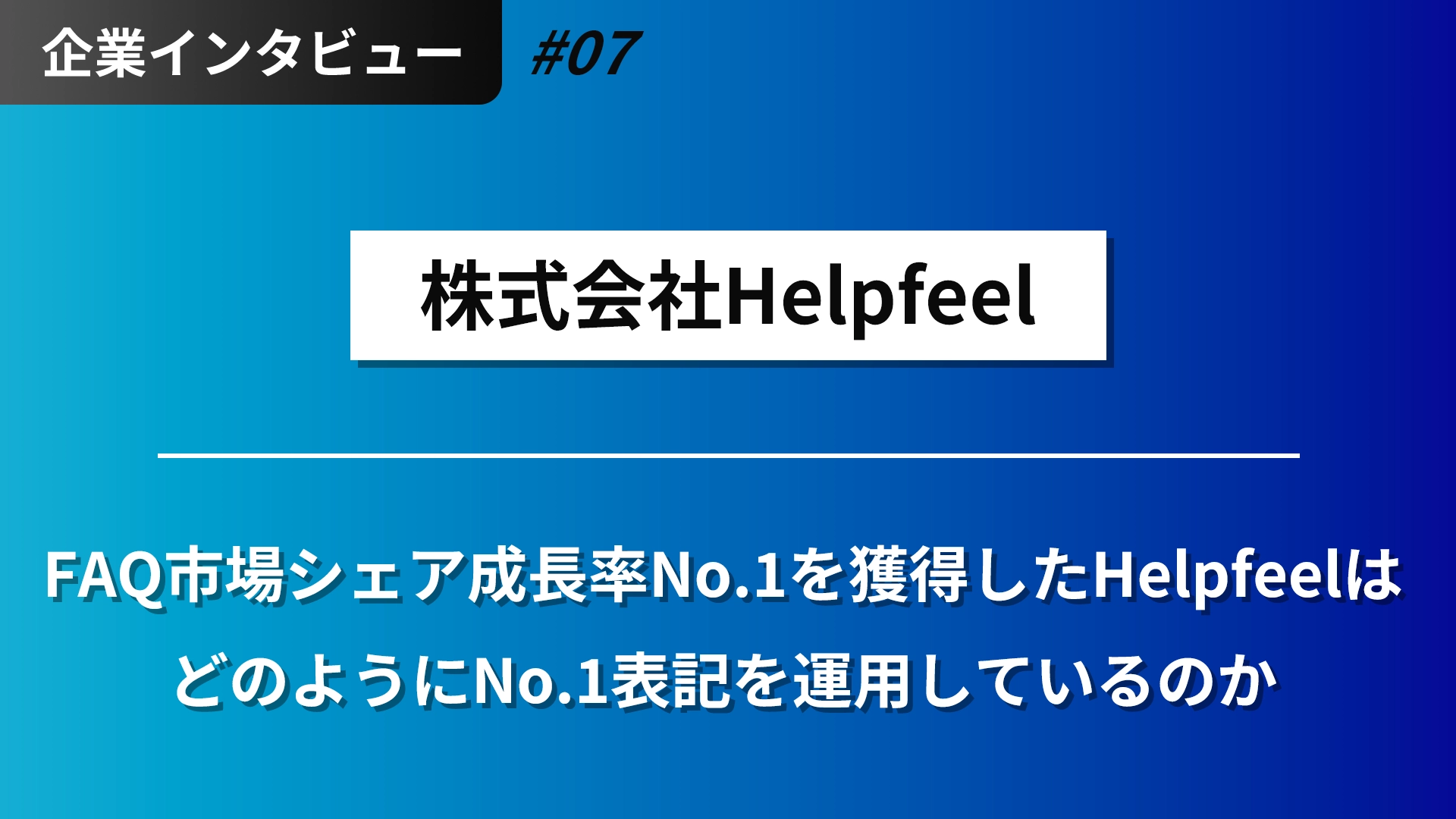

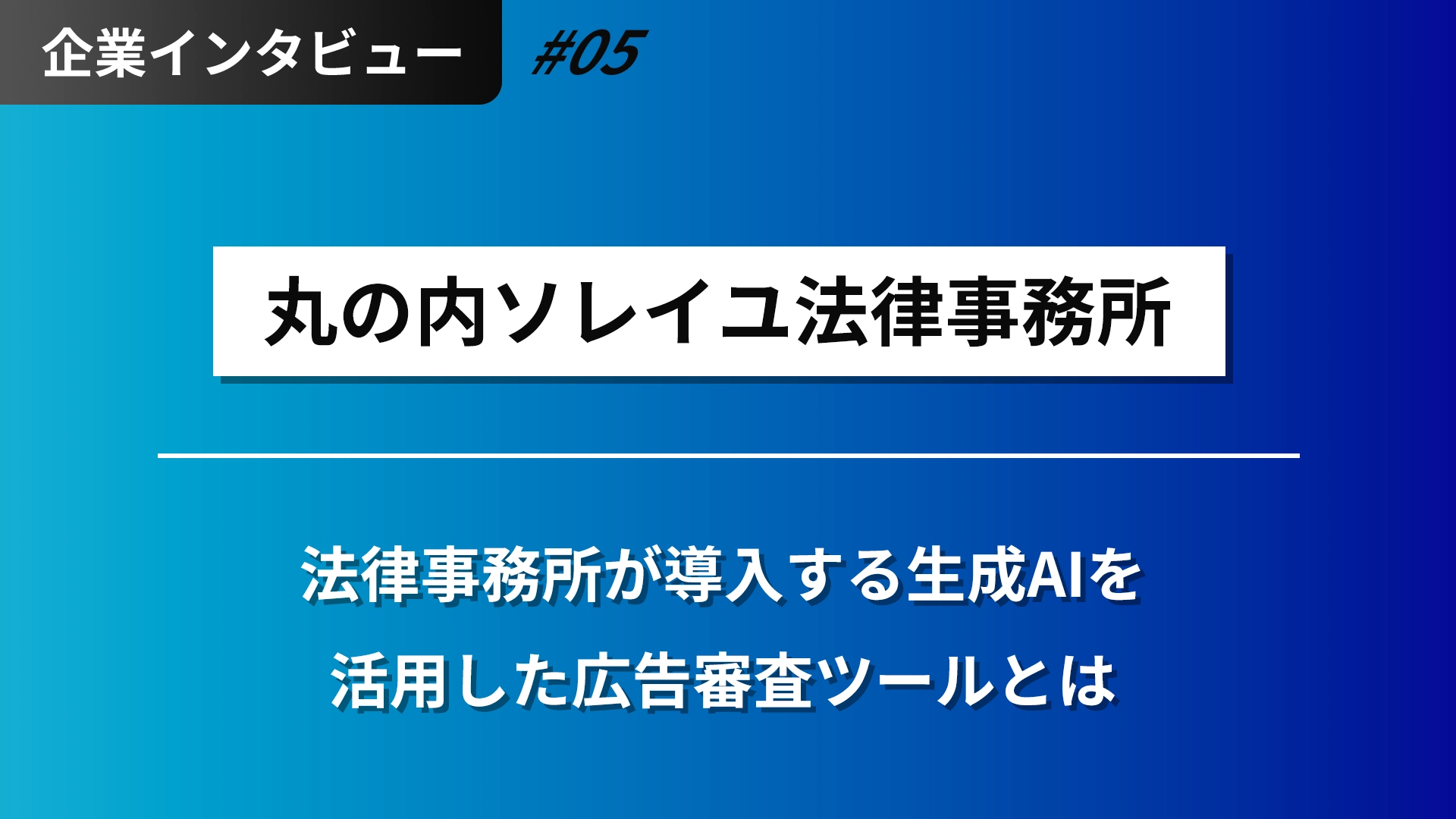
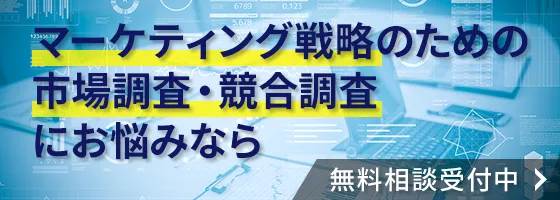
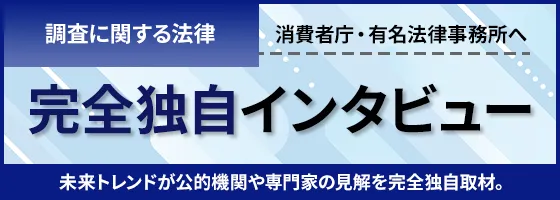
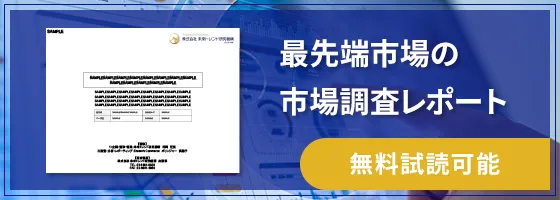


 info@miraitrend.com
info@miraitrend.com info@miraitrend.com
info@miraitrend.com